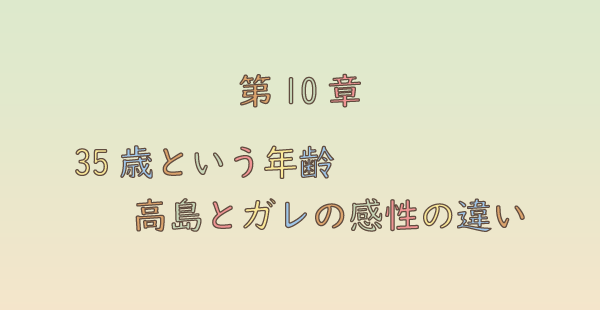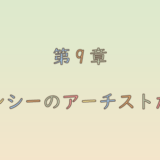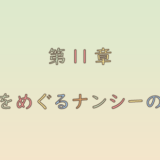ガレ工房で感性の違いを感じる高島
明治時代の35歳は、平均寿命44歳だった当時からすると現在の45歳ぐらいの感覚だろうか。高島という人物を考えるとき、彼が35歳で留学したことはひとつのファクターになる。明治政府は高島のこれまでの森林調査の功績のご褒美として留学させたのだろうと考えられるが、もし彼がもっと若くしてナンシーに行っていたら、別の展開があっただろうと思うからだ。高島より1年早い1884年フランスに留学した黒田清輝は、法律より絵画の道をえらぶ。この時、黒田は18歳だった。黒田の若さが人生の変更を可能にした。
しかし高島が35歳の年齢だったからこそ、ナンシーの名士たちと対等にわたりあえ、ナンシーのアーチストたちにジャポンを説明できたともいえる。
年下の同級生に囲まれた生活、フランス語は上達した高島だが・・・
9月。
森林学校に20人の新入生が入学した。全員共通大学資格バカロレアをパスし、2年間大学で履修後、選抜試験に合格したエリートの若者たちである。18歳から19歳の青年たちは、新入生歓迎パーティで一列に並び、緊張のため頬を紅潮させている。全員、後ろに手を組んでいた。初夏の港に停泊するヨットのようにそこには若さの誇示があり、ナイフの鋭さがあった。
高島は眩しかった。若さという光線に容赦なく照り付けられているようだった。35歳の彼は、何もかも手遅れで、取り返しのつかないことをしてしまったような気がした。この齢になってフランスに留学し、この先何ができるというのか、彼は呆然とした。
35歳、それは不思議な年齢だった。何かをあきらめるのは早いが、青春はとっくの昔に過ぎ去っていた。すぎてしまっているのに、独身で生活感のない彼には、どれも過去という影をもっていないのだった。
いつも可能性という若さと壁ひとつへだてたところにいるようで、それでいて壁には、もはや隣の部屋に行く通路はないのだった。そのくせ、隣からはたえず物音がきこえてくる。もろもろの記憶のなかで、夢と現実の比重は、すっかり現実の方が重くなっているのに、35歳の独身者は、なにか彼方に夢をもってしまう。若さもなく、老いてもいない。しかし生きたというには妙に軽々しく、分別だけをわきまえた年齢、それが35歳だった。
『自分はもっと早い時期にフランスに来るべきだった』それは疼くような悔恨であった。
歓迎会は、先輩学生が女装をした奇妙な踊りでお開きになった。新入生には、この後、先輩たちによる“儀式”が待っている。そのひとつは、木に登ってみせること。二つ目の“儀式”は、辛子をひとさじ食べること。最後の難関は、スタニスラス広場まで行ってスタニスラス像の右手に湯たんぽをぶらさげてくることだった。
寮をでている高島には、この“儀式”は関係がなかったが、30サンチームの会費だけは支払った。それは、翌日、市の消防署員がスタニスラス像から湯たんぽを取りはずし学校へ苦情を言いにきたときの罰金として渡すものだった。先輩たちは、あらかじめこの謝罪金を集めて用意していた。消防署員の方も、森林学校の9月の行事としてこのおふざけを大目にみている。
高島は、歓迎会の後、ブランシュ・ユッソンのもとで、いつものように授業を受けた。きょうのように精神的に萎えているときは、全く学校とは関係のない人とあっている方が気持ちの切り替えができる。
ブランシュ・ユッソンは、高島をみるとすぐに宿題をださせた。彼女は、規則正しく、着実に授業をすすめていった。少し雑談して休憩したいと思っても、彼女は決められた時間がくるまで高島を解放しなかった。
しかしそのお陰で、近頃では授業のフランス語も八割近くわかるようになっていた。おだてることの上手なブランシュは
「最初の頃と比べると格段の上達。頭のいい生徒をもつのは、教師にとっても楽しいわ」
とほめ、高島をやる気にさせた。事実、高島自身も樹の年輪をみるように自分の上達の跡を感じることができた。
高島と同じ年齢のブランシュは、時には姉のような存在で、高島の健康を気づかってくれた。しかし時々、何かのひょうしで本のページやノートを見せるとき、ブランシュの手に触れたりすると、彼女はさっと顔を赤らめた。そんな時、彼女は男をしっているのだろうかと思ったりした。しかし知的な彼女は、男女の話題を極力さけた。その少し物足りない緊張感が、高島は心地よかった。
ブランシュばかりでなく、ユッソン家の人達は、高島に対して丁重で親切だった。ひとつには彼がユッソン家の家計に貢献していたからだった。ユッソン家は、長男アンリの結婚と適齢期の娘マリーをひかえていたので、ユッソン未亡人は、夫の遺族年金と長女ブランシュの小学校教師の給料、借家からあがる家賃だけでは大変だった。東洋からきた日本人は、気前がよすぎるくらい家庭教師料を支払ってくれた。
一方高島は、1年間の留学費として銀千円、フランにして5千フランを支給されていた。当時、一家が一年間暮らす費用は、1500フランだったから、独身の高島は、その3倍以上もの額をもっていたので、優雅そのものだった。彼は熱心に教えてくれるブランシュに心づけとして家庭教師料を上のせしても、彼の生活に影響はなかった。
ユッソン未亡人は、高島の授業が終わると熱いコーヒーとお菓子を出してくれた。そしてしばらく3人で雑談をするのが、55歳の未亡人の楽しみになっていた。
「さぁ、ひと休みしてください、高島さん。この果物をめしあがって」
未亡人は盆にコーヒーとクッキーの他に梅のような杏のようなオレンジ色の果物をのせてきた。
「この果物は、ロレーヌ地方にしかとれないミラベルという果物なのよ。ジャムや果実酒にするのです」
未亡人は、東洋人にナンシーのことフランスのことを教えるのが楽しくてしかたがなかった。すすめられて食べてみると、杏のような味で、金木犀に似た強い甘い芳香がした。
「うまい」
高島が言うと、未亡人はすっかり上機嫌になって
「ミラベルの果実酒も少し召し上がる」
と、いそいそと台所にたった。高島は、上品で気のいい未亡人に49歳で亡くなった母曽能の姿を重ねた。顔も姿も違うが、母親の雰囲気が似ているように思えた。しかしそれは、自分の感傷であることを知っていた。
高島は未亡人が差し出す琥珀色の果実酒を飲みほし
「こんなうまい食前酒をのむと、食欲がはずみすぎて、体が樽になってしまいます」
口に残ったミラベル酒の甘い香りが、彼を饒舌にした。高島は、日本にある果実酒の絵をえがいて二人に説明する。
すると未亡人は
「ナンシーにだってサクランボ酒、リンゴ酒がありますよ」と
台所に行って、次々自家製のリキュールを持ってきた。ブランシュは、母親の陽気さをやれやれといった顔つきで見守っている。
高島はサクランボから作ったキールやリンゴから作ったシードルで、すっかりいい気分になって、ユッソン家を出た。9月のナンシーの夜風は、新しい麻の上着のように肌に心地よい。高島が一杯気分でスタニスラス広場まで来ると、スタニスラス像の下でうごめいている人影があった。影は、像の立っている台によじのぼろうとして虚しい跳躍をくりかえしていた。
「足台がないと無理だよ」
高島の声に、影は動きを止めた。
「森林学校の1年坊主だろう」高島が言うと、影ははじかれたように像から逃げようとした。
「私は森林学校の生徒だ。安心したまえ」
影は闇の中でまじまじと高島の顔を見ようとした。
「私の背中に乗りたまえ」
高島は、石畳の上に四つ這いになった。しばらくして背中に重さがかかった。それと同時に
「やった。ありがとう」
と、小さな歓声が降ってきた。
「カロといいます。ベンジャミン・ピエール・ポール・カロ、あなたのお名前は?」
「長ったらしい名前だな。私は高島だ。日本からきている。それじゃ、明日また」
「ありがとう、高島さん」
カロは、闇の中を黒い兎のように飛びはねながら消えた。
スタニスラス像の指差す右手の手首に、楕円形の湯たんぽがぶらさがっている。闇のなかにハンドバッグを持ったようなスタニスラス像が、一段と濃いシルエットを形づくっていた。
このことがきっかけで、高島はカロとのつきあいが始まった。15歳の年齢差が互いに競合しない気楽さをつくった。
カロは寮からの外出が許される日曜日、高島のアパルトマンにやってきた。二人で食事をつくり、ワインを飲みながらしゃべった。カロは、9月23日に入学したばかりなのに、ちゃんとナンシーの娼婦の名前まで知っていた。
フランス中部のクロワ生まれのカロは、陽気で、高島の部屋にきてもばか話ばかりしたが、成績は20人中、4番目と優秀だった。高島は、カロから授業のわからないところを教えてもらった。留学生組では、高島の年齢と東洋人であることから、これといった友達のいなかった彼にとって、カロは大切な友人となった。
ガレのアトリエを訪ねた高島は感性の違いを実感
学校の友達は少なかったが、ボッブ教授が紹介してくれた園芸関係やアーチストに顔見知りができていた。ガレは熱心に高島に声をかけていた。高島は、ナンシー派の連中やボップ教授が一目おいているガレのアトリエを見てみたいと思っていた。もう花を咲かせているガレのいう“東京”という菊も見たかった。高島はかねてからのガレとの約束を実行することにした。
高島のアパルトマンのあるチャスラン通りからガレの家があるガレンヌ通りまでは歩いて12, 3分。ガレンヌ通りは、ナンシー市の南のはずれにあった。
3階建てのグレイの屋根に白い壁、アール・ヌーヴォーとは何の関係もない、パリ郊外などでみかける上流階級の家がガレ邸だった。(現在は市の輸出入関係の公共建物になっている)
バルコニーもつつましい花柄のレリーフで、市のあちらこちらに建てられている左右非対称の建物のそれではない。門から玄関までの庭には、樅の木が一本、のびのびと天に向かって緑を誇っている。
しかしグレイの木の扉をあけ、一歩家の中に入るとびっくり館のように華麗な装飾の洪水が襲う。応接室のマホガニーの備え付けの家具には、目が痛くなるような細かな彫りがしてあり、観音開きの扉には、「寄せ木細工(マーケットリー)」で花の模様がほどこされている。そばに置かれた椅子は、小鹿のように細い脚がついていて、背もたれにはウイキョウの花が型どられている。テーブルはさらに凝っている。テーブルの表面にも寄せ木細工がほどこされ、その脚と脚の間にも椅子とおそろいのウイキョーの花がすかし彫りでデザインされている。
天井は丸く、中央から蔓草のようにランプが下がっていて、その傘には山型の木枠にガラスがはめこまれている。次の部屋を仕切る緑色のビロードのカーテンには、黄色のアゲハ蝶が飛び、柱にも中国の寺院のように彫刻がされている。部屋全体が、こってり化粧をしてすました女のようで、高島は息苦しくなった。
『なんとゴテゴテとした部屋だ。ここの主人に桂離宮をみせてやりたい』
高島は、出されたコーヒーにも口をつけず新しい檻に入れられた動物のように部屋をみまわした。彼は座っている椅子の脚が自分の体重で折れないかと心配だった。背をもたれかけると罅(ひび)がはいってこわれそうだった。
『こんな応接室を作って住んでいる男が、どうして自分のような人間に興味をもつのだろう』
高島はガレという男が分らなかった。
「お待たせしました。よく来て下さいました。さて、何からお話し、何からお見せしましょうか」
エミール・ガレは、曲馬団の支配人のようににこやかに高島を迎えた。
「変わった部屋ですね。小さな美術館みたいだ」
高島はせいいっぱいお世辞をいった。
ガレは、いつもやけに堂々としている日本人(ジャポネ)が、居心地悪そうにモゾモゾして、部屋の装飾に圧倒されているのをおもしろがった。
その時、ガレ夫人が現れた。アンリエット・ガレは、37歳。4女のジュヴィエーラを出産したばかりだった。アンリエット夫人は、下をむくと白い乳房がころがりおちそうだった。がっしりとした体格、聡明な額に意志のつよそうな薄い唇、黄金の髪、森の奥の湖のように青い目、華やかさにかけるが、家庭を守っていくための堅実さと賢さと忍耐強さをもっているようにみえた。アンリエット・グリムは(1848~1914)プロテスタントの牧師の娘で、グリム家は副業として鏡の販売店を営んでいた。ガレの父親シャルルは、鏡の製造業者であったので、二人はその縁で結婚した。
アンリエットはその時、27歳、ガレが29歳の時である。22歳までに結婚しなければ
“大変なこと”だった当時にあって、27歳の結婚はいかにも遅い。カソリックの国のフランスで、プロテスタントの牧師の娘ということが婚期を遅らせたのかもしれない。
ガレ夫人は穏やかな口調で、高島に挨拶をした。
『女房にするには、こんな女性がいいのだろうなぁ。彼女は、妻としてより母親としてガレを見守っているのかもしれんなぁ』
高島は、美津子のことを思い出し、妻にするには美津子は美人すぎるかもしれないと思った。
ガレの植物への関心と自然観
「まず、工房をみませんか」
ガレに言われて、高島はガレ邸をでた。3分ぐらい歩いたところにオーク材のがっちりした木の扉があった。それが、工房の入り口だった。扉には、枝を左右に伸ばした木の模様が浮かし彫りになっている。
「ウージャンヌ・ヴァランの作です。ほらナンシー・アルチスト誌の編集室にがっしりとした木こりのような男がいたでしょう。彼は家具作家なのです」
ガレにそういわれても、高島はヴァランの顔を思い出せなかった。観音開きになる扉の3分の2の高さに
『私の根源は森の奥にある ガレ』という文字が刻まれていた。
「これは、どういう意味ですか」
「よく質問を受けるのです。森は自然の意味、植物の意味です。植物からインスピレーションを得るということかなぁ」
「植物があなたの芸術の源泉ということですか、いかにもナンシー園芸協会の理事長さんらしいですね」
「植物は、なんでも好きです。すべての植物が私の創作欲をかきたててくれます」
ガレは、刻まれた文字を手でなぞりながらいった。
「日本人には、自然と共に生きるという発想があります。人間も植物の一部で、死ねば土にかえる。人間も自然界のすべての生物と同じように、生き、死でおわる。植物が花を咲かせ、実をつくり、花が枯れてしまうが、その実はまた次の年に芽を出す、すべての生き物は、生と死の間をめぐっているにすぎないという思想です」
高島は、輪廻転生という言葉を説明したいと思ったが、うまく説明できなかった。
「人間も自然の一部で、自然と共に生きるというのは、素晴らしい発想ですね。高島さんもご存知のように、ヨーロッパの自然はきびしい。特にナンシーのあるこのロレーヌ地方は幼児の死亡率がフランスで一番高い土地柄で、自然環境は特別きびしいのです。だから自然と共に生きられないのです」
ガレはすでに冬が迫っている鈍色の空を見上げた。
「なるほど、日本は温帯の国で穏やかな環境だから、自然と共に生きるという考えが生まれたのですね」
高島は、風土が思想を生むことに思いあたり、深くうなずいた。
ガレはこの“森”についてのちの「野菜文様のテーブル」の制作にあたり、彫金師のリュシアン・ファリーズに次のような手紙を送っている。ファリーズは、ガレと多くの共作をした作家である。
「うす暗く、青味を帯びたブロンド色に染まりながら、うっすらと湿った眠りにある森の情景。やがて森は植物たちを抱きしめ、クリスタルの真珠のような露の雫をそっと置いてゆくのです。
こうした情景の中に、この作品の本当の主題が隠されているのです。こうして、私は花壇の住人たち(植物)のやさしい魅力、その美徳をほめたたえようと決心したとき、もう一方の扉が雑木林に向かって開かれたのです。そこに植物を求める者、イデー(思想)を求める者、つまりあなたの<深い森の中から角笛の合図>をひらめいたのです。 ~中略~ われわれの肉体や芸術を養ってくれる植物に対し、またわれわれの共通の祖国である原始林に対して、その耕された大地、その畑に対して、感謝の気持ちをもめて次のように書き込んだのです。
われわれの根源は森の奥にあり
苔むすところ、泉のほとりに」(ガレ著「芸術ノート」に収録)
「野菜文様テーブル」は、高島帰国後の1892年に制作された。「われわれの根源は森の奥に・・・」の銘句は、モレスショットの『われわれが地上に生存するのも植物のお陰だ。植物こそわれわれの根源である』の句からとったものである。
ガレ工房の職人たちの技術力に感嘆する高島
ガレは、木の扉をあけ、高島を招きいれた。レンガ造りの2階建ての工房が左右に並ぶ。右側は、陶器製作所。左側は細工をほどこす工房と家具の工房である。2階建ての工房の中央部だけ、一部3階建てになっている。その中央部の一階がガレのアトリエであった。
二つの建物の中央には、職人たちが行き来する道があり、道の両側に植物が植わっていたが、大半が枯れてしまっている。すでに来年にそなえて一部土が掘り返されている。高島はどんなものが植わっているのか見たかったが、ガレは先にたって歩いていく。
「まずガラスの細工をするところをお見せしましょう」
ガレに案内された部屋は、細長い部屋で、職人たちが窓に向かって机を並べ作業をしていた。
机に置かれた研削機で、ガラスの表面を彫刻している。研削機の金属円板が何百匹もの油蝉のように鳴いている。
近づいてみると、研削機の下に鏡を置き、鏡に削る部分を写し出して削っていた。研削機から水が雫のように落ち、削ったガラスを流している。職人達は、削る部分を直接、肉眼でみられないのにもかかわらず、長年のカンで鏡に写ったものだけで削っていくのだった。
「これが彫刻(グラヴェール)という技術です」
ガレは得意そうに高島に説明した。
「手もとがちょっとでも狂えば指が飛びますね」
「彼らは、みんな10年選手です。ここまでになるのが大変です」と言って、顔をあげた職人に微笑した。
「ピエール、息子さんの風邪はもういいのかい」と、職人の家族の話をした。職人の表情が急に活気にあふれ、堰をきったように息子の話をし始めた。ガレはうなずきながら聞いていた。
高島は、次の職人のところを覗きこんだ。職人は、研削機の横にたてかけた棚から5ミリぐらいの薄さの金属板に取り替えると、ちょっと小首をかしげた姿勢で黙々と研削を続ける。ひょいと花瓶の向きを変えると、ランの花がくっきりと彫られていた。
「みごとなものですなぁ」
「一度、やってみますか」
ガレはいたずらっぽく言ったので、職人は気さくに立って高島を座らせた。その間にガレはガラスコップを持ってきた。
高島は職人の指導を受けて、ガラスコップに四枚の花弁の花を彫ることになった。研削機の金属円板が、眺めていたときよりずっと不気味な音に聞こえる。
「鏡をよくみて」
職人の言葉に、鏡に写ったガラスの側面をみて、こわごわ研削機にコップを近づけた。と、同時に巨大な油蝉の鳴き声がした。
「いけない」
高島は思わず日本語で叫んで、コップを研削機から離したが、すでに遅く、透明なコップには細い白線の傷がついていた。
「もっと、ゆっくりするのです」
ガレが言ったので、再び鶏を狙う狼のように慎重に機械にコップを近づける。花びらだから細かく3回ほど重ねてこすれば一枚の花弁ができるはずだった。だが無残だった。三つの醜い傷が、間隔をおいてできただけだった。次の花弁もみごとに失敗。コップには、鏡にナイフで切りつけたような残酷な跡が残った。
「こりゃ、見ていたよりずっとむずかしい」
高島は頭をふりふり立ち上がった。職人は満足そうに微笑をうかべ、再びランの花を彫りだした。高島は、力を入れ緊張していたのか、わずか10分足らずの時間だったのに、肩と腕が吊ったように痛かった。
ガレは、高島の感心しているさまにすっかり満足し
「“ナンシー・アルチスト”の編集室でびっくりさせられたから、これでおあいこですな」
と朗らかに笑う。
北斎の浮世絵からヒントを得て鯉の花瓶を創ったガレ
高島は、部屋の中央の台に完成した作品が置いてあったので、覗き込んだ。
花瓶が圧倒的に多かったが、その他に香水瓶、器、ランプがあった。ランプの傘には、バラやウイキョウ、あじさいの花が精巧に彫られてあったが、どれも高島が「ほしいなぁ」と思うものはなかった。
『ガレ邸の家具といい、この花瓶といい、香辛料を入れすぎた煮込み料理みたいだ。一体、この花瓶にどんな花をいけるのだろう』
高島は、ガレが茶器を愛でるように両手で包み込んでみているのをみて思った。その花瓶には、透明なガラスに金粉がところどころ散りばめられ、やけに逞しいトンボが彫られている。トンボの複眼が強調され、腹のふくらみもリアルに彫刻されている。『装飾なのだから、もうちょっと可憐なトンボを描いたほうがいいのに。このトンボじゃナンシーの冬も越えそうだ』高島は、やはり感心しなかった。どんなふうにほめればいいのか、言葉がみつからなかった。
高島には、ガレが自慢げに見せる作品が彼の考える“美”というものの範疇にはいらない。彼のなかにあるのは、万葉の時代「さやけさ」の美のすがたであり、藤原朝の「わび」という美、中世の「すき」という美のすがた、江戸時代の町人文化の「いき」という美の形であった。それらの美には、無理なもの、無駄な力んだもの、醜い重いものが排除され、あくまでもすがすがしく、清らかで軽くて、滞りなく明るいものであった。流れる水のような美しさが、高島にとっての美であり、日本人の美の類型であった。
もともと中国から伝わった日本文化であるが、中国から移るとき、重い漢字が日本では軽やかな仮名書きの字の美しさに変ったように一種の軽ろみが日本特有の美しさであった。
しかしガレの作品の中には、そういった軽みの美はなかった。むしろその反対に重いものを支えている美があった。油絵と水墨画の違いに似ている。油絵が、絵の具を塗り重ねていく足し算の美であるとしたら、水墨画はよけいなものを捨てていく引き算の美であった。
引き算の美を美とする伝統の中育ってきた高島には、ガレの作品に美を見出すことはできなかった。
高島はほめる言葉がなかなか探せなかったが、ようやく無難な言葉をみつけた。
「それにしても、すごい技術力ですね」
「彼らのお陰です」ガレは職人たちを見回した。
「あなた自身は、ガラスを吹いたり細工をしないのですか」
高島が尋ねると、ガレは首をふった。
「一応、ガラス吹きや装飾のつけ方は若い頃習っていますが、私が知っているのは原理や方法です。ガラス吹きだけで10年の経験が必要ですから、熟練の職人にまかせています。私はもっぱらデザインだけ」
ガレが若い頃というのは、バカロレア合格後、ドイツのワイマールで鉱山学と哲学を二年間勉強した後の1866年頃のことである。ガレは、ワイマールからナンシーに戻ってきて父親の工場に入って手伝いをするが、1866年、本格的にガラス技術を学ぶためにザール河谷にあるマイゼンタールのガラス工場に入る。そこで彫刻(グラヴィール)技術やガラスに絵付けをするエナメル彩色の技術をまなんだのだった。
高島は、ガレが現在作品のデザインだけを担当していると聞いて、意外な気がした。ボップ教授や“ナンシー・アルチスト”誌のルネ・ヴィエネールが「ガラス作家」と言っていたので、ガレが作品の完成まで一貫して携わっているのだとばかり思っていた。デザインだけと聞いて、浮世絵の場合と同じシステムだと理解した。北斎や広重は、原画を描くが、それを彫る職人と刷り師の技術が合致してこそ始めてなりたつ。ガラス作品の場合も、同じことがいえそうだった。
「ガラス作品の場合、デザインが命ですか」
「デザインは、女性の顔です。美人は顔できまるでしょう。さぁ、次にいきましょう」
ガレはゆっくりとした足取りで、一階の自分のアトリエへと案内した。
アトリエは、玩具箱をひっくりかえしたように雑然としていた。机と棚には、装飾の加工を待っているガラス作品が所せましと並べられていた。花瓶には、枯れてしまったアジサイや花弁を散らしてネギ坊主になったケシ、ウイキョウが乱雑に活けられて、机の上にもつる草や矢車草が散らかっていた。そうした花瓶の間に、日本の能面や仏像の頭部が飾られてあった。大事そうに団扇や扇子が並べてある。竹筒まであるのに高島はびっくりした。
「日本の物もありますね。どこで買かわれたのですか」
「パリの支店にいったときに買ったのです。パリに日本人が美術店をだしていますね」
「林忠正という人でしょう」
「林さんは、大先輩のゴンクールさんとも懇意なので紹介してもらったのです。パリには何軒か日本の美術を扱う店ができていますが、ゴンクールさんがいうには“断然ムッシュ林の店の品物がいい”というわけです」
「私も林さんには一度、ナンシーに来るまでに逢ったことがあります。フランス語がものすごく堪能で、彼は日本人の顔をしたフランス人でした」
高島は、岩下清周に紹介された時の林忠正を思いだした。
この岩下清周(1857~1927)は、品川電燈を創立し、北浜銀行の頭取になった男で、高島が53歳で画家になったとき、彼のパトロンになる人物である。当事の岩下は三井物産のニューヨーク支店からパリ支店に赴任していた。岩下は1883年、明治16年から明治21年までパリに滞在し、経営の腕をふるう。その間岩下のアパルトマンには、日本からやってきた政財界の人達がかならず立ち寄っていた。伊藤博文、山県有朋、品川弥二郎などもアパルトマンに立ち寄ったメンバーで、岩下の居宅は「日本人倶楽部の如きもの」だった。社交家の岩下は、パリ在住の林忠正や留学生の原敬とも親しくつきあっていた。
高島は、後にパトロンの岩下のために「山水百種」と題する山水画を百枚描く。それが明治39年「北海山水百種」と題する画集になるが、その画集の序文に、岩下は高島との交流のきっかけを書いている。
「北海高島兄は予の茜友なり、兄かって職を山林局に奉ず、明治18年命を以って仏国に滞在するや、予も亦当事同国に在り、始めて兄をしる・・・・」
(「北海山水百種」)
高島と林忠正との直接の交流の記録は、まだ発見されていないが、二人は岩下清周を介してしっていたはずである。
「世の中はせまいですね。あなたが林忠正の店の客だなんて」
高島は、ガレが日本人の店で能面や仏像を買っていたのかと思うと、急に親近感をもった。
「しかし、日本のものをどうするつもりですか?西洋的なガラスの花瓶には会わないでしょう」
高島が言うと、ガレはニヤニヤしてアトリエのすみにあった飾り棚から、ひとつの花瓶を取り出した。
「種明かしは、これですよ、高島さん」
透明のガラスの花瓶には、墨の鯉が描かれていた。
「これは北斎の鯉じゃありませんか」
高島は、狐につままれたようにきょとんとしていた。
「やはり画家ですね。この図柄をみただけで北斎だと言い当てるなんて。北斎はそんなに有名ですか」
ガレは「北斎漫画」の「魚濫観世音」からとったエナメル彩色の「鯉魚文花瓶」みつめて残念そうにつぶやいた。
「鯉の上にのった女神は描かなかったのですね」
「あの変な女性は、女神だったのですか?」
今度はガレが驚いた。そしてガレは本棚からレモン色の表紙の浮世絵本をだしてきた。
「ナンシーで北斎に出会うとはね」高島はため息をついた。
ガレが「北斎漫画」の鯉の図のページをあけると、高島は日本では鯉は滝をのぼる勇気のある魚として見られていることや、男の子のための祭りがあって、その日には布で作った鯉を庭にあげるのだと説明した。ガレはおとぎ話を聞く少年のように目を輝かして高島をみつめた。
「それでは、日本人はすべての生き物にそういった意味をつけるのですか?」
「そうです。キリスト教にもあるでしょう、白百合は清い乙女のイメージといったものが・・・あれと同じですよ」
高島がいうと、ガレは大きくうなずき質問をした。
「じゃあ、菊の意味は皇帝の紋章の他にどんな意味があるのですか?」
高島は、菊の花は高貴な花で、菊の花を乾かして枕につめて“菊枕”にすれば長寿ができることや、日本には9月9日に菊の祭りがあること、中国の故事にある“菊慈童”の話をしてやった。その昔、皇帝の寵愛を失った美しい少年は、落ちぶれて山里に住んでいたが、少年は皇帝をずっと慕い続けていた。それを偶然のことから知った皇帝は、少年を哀れみ、少年が永遠に若いままでいられる秘密をおしえてやった。菊の花の露を飲むことだった。
高島の話を聞くとガレの眼は、うるんだように光っていた。高島はふと最初に交わしたガレの握手の手のぬめりを思い出した。彼は上田秋成の「菊花の契り」を話そうかとしてやめた。
「トンボの話も聞きたいですね。日本人はすばらしくロマンチックな国民だ」
ガレは話を聞きたがったが、すぐにこの際いろんなことを高島に聞いておきたいことがあるのを思い出した。
「高島さん、これは何につかうのですか」
ガレが飾り棚から出してきたのは、獅子頭の青磁の香炉とキセル、漆の盆だった。高島がひとつひとつ説明すると、長い間わからなかった問題が解けたように晴れやかな顔をして
「この恐ろしいライオンのような動物は、想像上の動物だったのですね」
と、何度もうなずいた。
「その香炉にはサインは入っていませんか」
「どこに?」
「裏です」
「ないです。しかしこのトレーにはサインが入っています」
ガレは漆の盆を見て
「日本人は、サインすらひとつのデザインにしている。このアイディアを拝借しましたよ」と言い、陶器の菓子入れを棚からだしてきた。なるほど、EキGというサインが入っている。
ガレが日本画からヒントを得て縦のサインを使うようになったのは、かなり早く、1877年頃からである。かたつむりの形をした軟質陶器のデッサンは1880年~1884年頃のものである。透明ガラスにエナメル彩色をした獅子頭の花瓶にも縦サインを入れている。1879年制作の「日本風怪物頭壷」(デュッセルドルフ美術館蔵)と題されたその作品は、備前焼の獅子の頭の形をしたタン壷をそのままガラスに置き換えたものだった。
高島は、ガレが誇らしげにみせる縦サインや日本の陶器をそのままガラスという素材に移し換えただけの作品をみて、なにやら気恥ずかしくなった。梅にバラを挿し木したようなである。もっとも梅もバラ科の落葉高木なのだが、外見は全く異なる。どうも「違う」と高島は思う。
するとガレが突然切り出した。
「高島さん、あなたのもってらっしゃるスケッチ帖を見せてくださいませんか」
やはりこれが目当てだったのか、と高島は脇にかかえていたスケッチ帖をさしだした。
「これ貸していただけませんか。この菊をぜひ、作品の中にとりいれてみたいのです。菊の花弁はエネメル彩でやればうまく出せるなぁ」
最後の方は、ひとりごとのようにつぶやいた。しかしガレが高島の菊を作品の中に取り入れには、少し時間を待たねばならなかった。ガレは「菊とグラジオラス」の園芸論文を書き、充分根回ししてから、作品に作った。
「日本風のデカンタとグラジオラスセット」と題され、1890年のパリ万博に出品された作品に、菊のモチーフが使われている。
透明ガラスに、菊の一折りがエナメル彩色され、エナメルで花弁を盛り上げて、リアルさをだしている。花はすべて下向きに描かれ、あたかも菊の一折りを挿したようになっている。デカンタの中に入れられたワインは、重陽の節句に長寿をねがってくみかわされた菊酒のように仕掛けられているのだった。
ガレの菊のデザインは、花瓶にも表われる。首の長いアラビア風の形をした壷は、黄金色である。壷の首には、管ものの菊がレンガ色で浮かし彫りになっている。花瓶の腹のふくらみには、真正面から菊をとらえ、そこに紫がかった雲をなびかせ、アゲハチョウをあしらっている。壷の注ぎ口近くには、菊の御紋風なものと、日本の家紋を組み合わせ、さらにデフォルメした波模様を金ですかしぼりにする。それはオリエントの魔法の壷のように神秘的で蠱惑に満ちている。(ナンシー派美術館所蔵)
ガレは高島の菊をフランス人というフィルターを通して、オリエントのシンボルとしての花に創り上げたのだった。
しかし菊をモチーフにしたガレの作品は、当時のフランスでどのように評価され、ガレが望んでいたようにどの程度普及したかの記録はさだかではない。