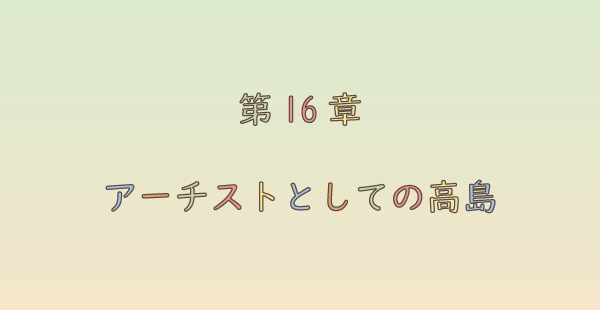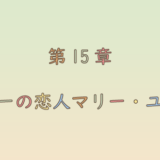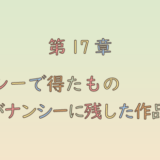リモージュから日本画を依頼され画家への道を考える高島
復活祭の休暇が終わると、陽射しに透明感が加わった。本格的な春がやってきた。
高島は、宮内庁に勤める東京の兄、張輔が送ってくれた朝顔の種のことを思い出した。ガレとの約束をはたすときがきた。
「これが昼顔(リスロン)の種ですか」
ガレ邸の庭師ツッサンは掌にのせて黒曜石のかけらのような種をころがせた。
「種からして大きい。なるほど高島さんがおっしゃるように、この種なら大きな花を咲かせそうだ。ガレさんがいたら喜ぶのに」
ツッサンは、ガレがパリの支店に行っていることを残念がった。
1887年の春、ガレはナンシーとパリを忙しく往復していた。2年後に行われるパリ万博の運営委員会の秘書にも内定していたので、パリに行く回数がふえていた。
ツッサンは、高島の助言で木箱に苗床を作った。種は1つずつ5センチ間隔で落とした。
「日本では、これを昼顔とはいわないのです。昼顔科ですが、フランス語にあるVolubilis(丸葉朝顔)です」
高島は、植物辞典で調べたボリィォビィリィスという言葉を言ったが、ツッサンは首をかしげた。朝顔は、ナンシーにはない花だったので無理はなかった。
「それじゃ、お国には夕暮れに咲く昼顔もあるのですか」
「あります。ピンクではなく、花は白ですが。Yugaoというのですが、花は昼顔に似ているのですが、種類は違うのです。Yugaoはウリ科で、実は食料になります」
「実がなるのですか」
ツッサンは冗談で言ったことが答えになって返ってきたので、種をまいていた手をとめた。
「そんな話をきいたら、主人はすぐにYugaoとかいう花をほしがるでしょうね。ガレさんの花好きは持病のようなもので・・・私はガレ家で好きな植物を相手に暮らしていけるので、こんなに幸せなことはありませんよ。もうひとつだけ願いをかなえてもらえるなら、園芸協会の会員になることです」
「会員になるのは簡単ではありませんか、会費をはらえばいいのでしょう」
「会員の方は皆、立派なお家の方ばかり。私のような身分の者はなれません」
ツッサンは淋しく笑った。
「私からガレさんに頼んでみましょう。あなたは会員になれる資格は充分にあります。花の好き、嫌いに身分もへったくれもありません」
高島の強い口調に、ツッサンは驚いて彼を見上げた。
「高島さん、あなたはいい人ですね」
二人の間にやさしい時間が流れた。ガレがいたら、この種の話をツッサンとすることもなかっただろうと、高島はおもった。この国の強固な階級制度と、日本や中国の異国文化を受け入れる柔軟な精神とは、どこでつながっているのだろうかと思った。そして彼は、古い体制が崩れて新しい政府となった日本では、どのようなことがおこっているのだろうかと考えずにはいられなかった。兄の手紙には、今年(1887年)1月に鹿鳴館に白熱灯がともり、いずれ一般庶民の家にも普及するだろうことや、皇后陛下が婦人服の思召書を発布されたので、日本でも上流階級の間で洋装化が急速に進んでいること、昨年、万年筆という便利なものが売り出され、これは西洋風“矢立”で、インクが筆の中に内蔵されているのだと書いてあった。世の中はめまぐるしく変ってきているが、変らないのは金持ちと貧乏人がいることだと手紙には結ばれていた。
高島は植えたばかりの朝顔の苗床に如雨露で水をやるツッサンを見た。運命に従順な男は、どこか無気力な感じがあった。
アーチストとして注目される高島
ガレ邸から帰ると、ドアに二つのメモがはさんであった。マリーとカミーユ・マルタンからのものだった。マリーのメモには「夕方、まいります」と書いてあったので、マルタンの「アトリエに来られたし」の方からかたずけることにした。
カミーユ・マルタンのアトリエは、ガレのアトリエよりさらにがらくたが飾られている。日本の刀が飾り棚に置いてあるかと思えば、その横にアラビアの盆、さらに横には白骨体の牛の頭が鎮座しているのだった。ギリシア彫刻の立像のそばに、西洋の鎧、その後ろになぜか日本の槍がたてかけてある。そしてもう一方の壁は、アラビア文様の布がピンで止めてあり、天井からもアラビアのランプが吊り下がっている。部屋を一層せまくしているのは、熱帯性の棕櫚の鉢植えだった。床にもペルシャの絨毯が敷きつめられていたが、絵具で汚れていた。ところどころ擦り切れて白っぽくなっている。もともと古い物を買ってきては敷いたらしく、絨毯は相当な年代物だった。
まるでオリエントのどこかの街の骨董屋にまぎれ込んだみたいだった。マルタンの前にキャンバスがたてかけてなかったら胡散臭い骨董屋の主人だった。
マルタンは機嫌がよかった。
「ちょっとでもあなたに早くしらせておこうと思って・・・わざわざ呼び出して申し訳ない」
前置きをしてからマルタンは、リモージュの国立陶器学校が日本画をほしがっていると聞いたので、高島を推薦したというのだった。
リモージュは、フランス中部にある磁器の町で、当時はセーヴィルと並ぶ磁器生産の地として知られていた。もともとヨーロッパに普及していたのは、軟質陶器(ファイアンス)で、磁器の歴史は比較的新しい。ヨーロッパに最初の磁器工場がマイセンにできたのは、1710年である。マイセンの陶工たちは、中国磁器を研究して、同質のものを作ることに成功し、マイセンはヨーロッパの磁器を独占する。
しかしフランスが中国に派遣した宣教師のひとりが、江西省景徳鎮の精細なリポートを本国におくり、科学者レオミュラールやブランカによって磁器素地を完成させた。1768年、セーヴィルに工場が作られ、ルイ15世が王立製陶所に指定したので、セーヴィル窯全盛時代が続く。セーヴィル焼きは、鮮やかな青紺地に金の文様が入っているのが特徴である。
リモージュは、セーヴィルに比べると一歩も二歩も遅れをとっていたが、それでも19世紀には、二十八の磁器工場ができていた。リモージュ磁器の特徴は、白地にヨーロッパ伝統の花や風景を入れた製品である。
リモージュの製品を有名にしたのは、フランス人ではなくアメリカ人である。1839年、アメリカ人のデヴィッド・アヴィランドーがリモージュにやってきて、アメリカ人好みの文様の磁器を作り、盛んにアメリカに輸出した。
このアヴィンランドーのもとで磁器絵付けをしていたのが、先に述べたブラックモンである。ブラックモンが“北斎漫画”からモチーフをとったジャポニスムが大当たりをとったので、リモージュの窯ではモチーフになる日本画をほしがった。リモージュの国立陶器学校は、パリの装飾美術館の館長、ラジョレにこの一件を依頼する。
ラジョレは、パリ装飾美術学校の卒業生で、パリにくるたびに顔をだすマルタンから、最近、日本人から直接日本画を習っていることを聞いたので、リモージュからの話をしたのだった。
マルタンは高島に強調した。
「あなたの日本画が、教材になる。いや、日本画は陶器の絵にもなるかもしれない。素晴らしいことじゃありませんか。フランスと日本の文化の橋渡しをするのですから。ガレさんにもずいぶん日本画を貸してあげているのでしょう」
マルタンは、高島がガレ工房にしていることを公にするだけだといいたげだった。
「一体、どんな絵を描けばいいのでしょう」
「今まで高島さんが描かれていたあの絵でいいのですよ。あなたは、ナンシーだけじゃなく、リモージュにも“日本”を根付かせることができるのです。それをできるのは、あなた以外にありません、高島さん」
マルタンの口調はだんだん熱っぽくなり、高島がいっこうにのってこないのをじれったがった。高島が、マルタンの言葉を理解したのは、六月になって正式にパリのラジョレ館長から依頼の書面が届いてからだった。これは大変なことになった、と思ったが、体の重心が妙に上にあがってしまい、気持ちが集中できなかった。ナンシーに来て初めて森林学校の図書室で、ガレや園芸協会の人達の前で絵を描いたときの興奮を久しぶりに思いだしたりした。
森林学校を卒業する異色の生徒高島
高島は、リモージュのための制作に取り掛かる前に、フリッシュ教授から依頼された植物解剖図の残りを完成させることにした。きのこ類の部分が残っていたので、急いで完成させた。(ナンシー森林学校に現存)
学校の方は、卒業式が近づいているので、時々、顔を出す程度でよかった。フランス組では、卒業試験が行われていたが、高島のような留学生は試験をうけなくてもよかった。
カローは、今度の卒業試験の成績で赴任先が決まるので必死だった。
高島はほとんど顔を出さなくてよかったが、7月になると園芸協会の定例展示会が町のペプニエール公園で開かれ、ここには顔をださねばならなかった。
展示会は7月10日から1週間、公園内で開かれ、花と野菜の部門に分れていた。高島は協会からの依頼で花の部門をガレやクルース等と一緒にまかされた。仕事は入場者料50サンチームを受けとるというものだったが、来るのは会員とその家族が大半だったので、受付に座っているだけでよかった。時々会場を見回って、展示された花が大丈夫かを点検し、ほとんどはやってきた会員たちと花の話をしていた。
ガレは8月14に開催される園芸協会主催のカーネーションの展覧会のことで頭がいっぱいなのか、カーネーションのことばかりしゃべっていた。
「日本にはカーネーションはありますか」
「アンジャベルと呼ばれています。オランダから入ってきたので、オランダ名のまま呼ばれているのです」
高島の明晰な答えに、ガレは明らかに失望していたが、フランスのように日本には種類が多くないと言うと、ガレは初めて納得した。花のことになると、ガレは途端に子供じみた競争心をむきだすのが、高島はおかしかった。
ガレは、今度のカーネーション展にはアメリカの「ツリー・カーネーション」を交配させた大輪のものを出品するのだと気炎を吐いていた。フランスで栽培されている露地のカーネーションが60センチの高さなのに比べ、アメリカで改良された温室カーネーションは茎も太く、2年で2メートルもの高さになるので「ツリー・カーネーション」と呼ばれ、19世紀末には温室栽培が始まっていた。
「日本の青」を使ってリモージュから依頼にとりかかる
ガレは、高島の植えてくれた昼顔がつぼみをつけていると報告した。
「青いつぼみですよ。日本の陶器と同じ青の色です。花が咲いたら写生し、ガラスのデザインにしてみせますよ」
ガレは、決心を打ち明けるように言った。高島は、ガレが言う“日本の青”の言葉に、リモージュの絵にも紺を使った作品を入れようと思った。
7月は、公園での園芸定例会を除いて、ほとんど部屋にこもってリモージュのための作品作りにかかった。時々、マリーが食事を運んでくれたが、制作に熱中していたのでマリーとの会話もちぐはぐなものになった。しかしマリーは意外にも怒らなかった。むしろ彼女はかいがいしく部屋をかたずけ、制作の邪魔にならないように歩くのにも心を配っていた。勝気できまぐれな、神経がむきだしにでている娘という印象が強かっただけに、高島がサンドイッチを食べている間に、絵皿の位置をかえないで、手早く掃除をする彼女をみるのは驚きだった。ひとにはいろんな面があって、その人のいい面を引き出すのは、その人への愛(おもい)なのかもしれないと思った。
リモージュのための制作は、高島とマリーとの間に思わぬ副産物をもたらした。
7月中に高島は、10点の日本画を描きあげた。しかし其の内の2点は気にいらなかったので、描きなおすことにした。雅号は、日本海に面した萩の海からとって“高島北海”とした。
高島は、実に勤勉に絵を描いた。ひどくせっかちな性分であることを自覚していたので、計画をたて、完成までに余裕をもたせた。もう一度やり直さなければならないというところに自分を追い込まなかった。彼は授業にでるのと同じように、朝、勤勉に絵机に向かった。
高島の心は、やすやすと肉体を抜け出し、紙と絵筆に集中した。その瞬間の恍惚感、充実した孤独。肉体の重さを感じないですむ軽やかさ、明晰な酔いともいうべき昂揚、絵筆の先の意志・・・彼は頭の中にすでに描き終わっている絵を、紙の上になぞっていった。
しかし日によってそういう状態になれないことがあった。絵筆の先が妙にざらついて感じるとき、彼は筆がなじむまで紙の上にただ筆の線をひいて、筆が自分のもう1本の指になるのを待った。そんなときは、せっかちな彼だが、驚くほど辛抱強かった。
図柄をかんがえるとき、兄の張輔が船便で送ってくれた「光琳百図」(文政9年発行)や「都鄙秋興」(安政4年)の和とじ本をめくってモチーフを探して、自分流に合成した。
10点の作品は、思ったより早く完成したともいえるし、遅かったともいえた。外にでると空が高くなっていた。夏になっていた。
8月に入るとすぐに森林学校の卒業式があった。8月2日、森林学校61期生の27人は、中庭の普仏戦争の戦没兵士の碑の前に並んで、記念写真を撮った。20人がフランス人で、留学生組がイギリス1人、ベルギー2人、ルーマニア3人と高島の7人だった。昨年10人足らずいたイギリス人の中で2年間学んだのは、わずか1人になっていた。
5月から写真撮影の実技を教えているティリィオ教授が、大きな声で「動かないで」と、黒い布をかぶって写真機をのぞいたままで左手をあげた。枝がおちるような音がした。その音と共に、森林学校の2年4ケ月の幕が閉じた。
フランス人の20人は、卒業後、軍隊に入隊することが決まっていた。徴兵後、それぞれの森林の赴任地に配属されるのだった。
「高島さんとはもう会えないのかな」
「僕は来年の3月までいますから・・」
「マリーさんのこと、よろしく」
「えっ」
「隠さなくてもいいですよ。あの日、彼女への伝言をわざわざ言いに行ってくださったのですから。あなたは紳士的だったし、今も僕の友人です」
カロは高島の手を握った。トルコ石みたいな眼の青みが一瞬濃くなった。
高島は、マリーとの間を釈明したいと思ったが、その時イギリス人が挨拶にやってきたので、中断してしまった。その夜は、学校のレストランで教授たちをまじえてのパーティが開かれ、高島はかねてから用意していた2枚の水彩画をカローに渡した。ふたりはマリーのことに触れることはなかった。
8月は別れの季節だった。カローは故郷クロワに帰っていった。ひとつの季節が終わった寂寥感があったが、もの思いにひたっているわけにはいかなかった。高島は翌日から、描きなおしの2点にとりかからねばならなかった。
リモージュに10点の日本画を寄贈
カミーユ・マルタンの提案で、リモージュに寄贈する前にナンシーで一般公開されることになった。
「この10枚の掛け物を装飾美術学校の校長宛パリに送る前に、この心優しいアーチストは親密な内覧会に我々を招いてくれた。 ~中略~ この種の作品についてすべての発想を理解する方法を我々は知らない。主題はないのか、すべてが主題である。最小の細部が、この日本人にとって完全な絵画となる。空に向かって真っ直ぐに伸びたやわらかで大胆な葦、足もとの川の流れ、空中のハエがここではすでに複雑なテーマである。タカシマ氏の作品群の中で注目することは、構図と形式についてさえも、多くの多様性を持っていることだ。 ~中略~ 」
(E・グーチェル・ヴェルール ナンシー・アルチスト1887年8月21日号)
ナンシー・アルチスト誌の記者、グーチェルは、高島の10点の作品について、その構図や形式の多様性、日本絵画の持つ装飾的な伝統を絶賛した。そして記者は最後に「我々国家がしかるべき方法で、この芸術家に対して感謝の意志を表すことを望んでいる」と結ぶ。
高島は、今度もまた日本美術の伝統や構図の奇抜さ、自然への観察の鋭さを指摘され、それを賞賛されたことに、多少の物足りなさを感じるところがあった。今回の10点は、彼なりに力を注いでいた。筆の勢い、水墨のぼかし具合、簡潔な省略、それらを日本美術の伝統という言葉だけでかたずけられるのに不満があった。それほど彼はこの2年数ヶ月のナンシー滞在中に自信をもつようになっていた。自信は、多少、彼の作品を上達させた。
高島は、無事、森林学校を卒業し、リモージュへの寄贈をはたす。この時期、ナンシーでもっとも充実した日々をおくっていた。
園芸協会の展示会で注目される日本の花々
東部園芸協会主催の展示会は、彼の生活をさらに充実させた。展覧会は、ロレーヌ地方やアルザス地方ばかりか、リヨンあたりからも園芸家たちが自慢の花を出展した。
高島は、ナンシー園芸協会の会長、シモンから東洋部門の花の秘書をまかされた。会全体の理事長であるガレは、展覧会場をみてまわり、並べ方に指示を与えた。そして時間があると東洋部門の高島のところにやってきた。
ガレは花の部門に、江戸菊やチューリップ、カンパニュラ、ジャスミンなど数多くの品目を出品し、高島が植えてやった朝顔も出店した。樹木の部門にも“中国の柏”やカナダの西洋さんざし、ヒマラヤ産の桜桃など、庭にある珍しいものをごっそり展示会場に運んだといったかんじだった。その中のジャスミンとカエデは、2年前にも展覧会に出して会場をわかせたものだが、今回は品質改良させていた。ジャスミンの白い可憐な花が、会場に眠たくなるような甘い香りをただよわせていた。
展示会場には、ルモワンヌの牡丹と芍薬、中国のハクモクレンも展示されていた。森林学校のボップ教授は、菊を一鉢出品していた。高島が教授に知恵を授け、ふつうは9月に咲くのを1ケ月早くに咲かせたのだった。
ボップ教授は妻とふたりの息子を連れ、一家総出で会場にやってきた。高島はボップ夫人や息子たちに、牡丹の根が薬用になる話やカエデは日本では赤く色づく話をしてやった。
ガレも暇があると、朝顔が心配になるのか見にやってきた。朝顔の鉢植えは、高島とツッ・サンとで蔓をはわせる輪と添え木を作った。ガレはそれが自慢だった。
「皆、びっくりしていますよ。こんな大きな昼顔は見たことないって。そこで僕は説明するのですよ、これは昼顔(リスリン)ではなく、朝顔(ボリィビィリュス)だってね」
ガレは朝顔の無事を確かめ、それだけを言うと次の会場へ忙しそうに戻って行った。
マリーがブランシュと一番下のルイーズの3人でやってきたのは、展覧会の3日目だった。マリーはツバの広い帽子に、マーガレットの花をさしていた。そこだけに陽が差し込んだように明るい。百合のつぼみのような細いウエストに、レモン色のリボンを結んでいる。
彼女はわざと高島の視線を避け、展示会場を昂然とみわたしたかと思うと、窓際に行ってしまった。もうすっかり会場を見てしまったという様子で、開け放された窓から外をみていた。
高島は、教授の家族にしたようにブランシュとルイーズにも花の説明をしていった。
「マリー、来てごらん。とてもいい香りの花があるわよ」
ルイーズが言うと、ブランシュは
「放っておきなさい」と、マリーを一瞥した。
高島には、マリーが何をすねているのかわからなかった。彼は説明を続けた。
マリーは帽子に差していたマーガレットをとって、一枚一枚その花びらを窓からとばしていた。窓からの光が、彼女の白のドレスをすかし、薄い肩の線を浮かしていた。
『彼女は自分を噛んでいる』
そう思ったとき、高島は以前にもこのような女をどこかでみたような気がしたが、それがどこだったか思い出せなかった。
東部園芸会は、大盛況のうちに終わった。高島は、リヨンの園芸新聞の記者に取材され、日本の自然のことを語った。そしてその新聞に載せるための花鳥画2点を寄贈することを約束する。
「ナンシー園芸中央協会報告書」は記している。
「高島氏は、ナンシーで自分の国の植物をみて感嘆しているのを私は(J.フッサットの報告書により)知った。それから植物が丹念に世話されているのをみて、高島氏はノスタルジーにおちいらないですんだ」
(1887年8月14日)
同じ報告書には、高島が植えた花についても書かれている。
「森林技師の高島氏によってもたらされた日本の新種の珍しい昼顔は、ガレ氏のアトリエの壁を美しくおおっている」
ガレは高島が植えた朝顔を、後に作品に残している。
朝顔の青紫の花弁をクリスタルガラスに生けた「ひるがお文クリスタル花器意匠」のデッサン画(1889年作)。透明なグラスに朝顔の花と葉、蔓がデザインされ、グラスの口が朝顔の形になっている。グラス全体が朝顔の花の精をおもわせる。
花のエロティシズムをガラスで表現するガレ
1892年の「10月の昼顔」と題された花器は、秋の冷気の中で枯れようとしている昼顔を劇的にとらえている。
「上部は翡翠色の茎、瑪瑙色の種、葉脈の出た葉、それにオパール状に輝く水滴などがみられます。一枚の花序がかすかな薔薇色で配されています。もう初霜がやってきたことを思わせるように、幾筋かの霧が描かれています。中央には、このふるえるように寒い季節に残った最後の昼顔の蕚からおちた一枚の花弁がクリスタルの奥深く消え入っております。これを拾ってくれる人に感謝するために、昼顔はヴェルレーヌの詩をつぶやきます。
あなたは私の憂うつを拾うのですね」(ガレ著「芸術ノート」)
ガレは、「10月の昼顔」の作品をていねいに説明する。花器の中に、今年最後の昼顔というドラマチックな世界を創りだし、明日には霜にうたれて枯れてしまう花のあえかさ、花の生命のあやうさを文学的に表現した。ただ単に昼顔をモチーフにするのではなく、劇的な舞台を設定し、そこに昼顔の花の精を表現していた。そして自分を感情移入していく。ガレの芸術性の真骨頂があった。そこでは、ガレ自身が最後の昼顔の化身となっていた。昼顔に投射することによって、自分を花と同類になりたいとう一種のナルシズムがひそんでいた。
花を愛した世紀末の芸術家には、オスカーワイルドやプルーストがいる。
ワイルドの「獄中記」には、
「花々を欲情の一部とする私にとっては、薔薇の花びらのなかに涙が待ち受けていることがよく分る。杯状の花や、曲線の魂そのものとのあいだに、ある微妙な交感が成り立ち、
私の資質は、つねにこれに感心したものだった」
という一節がある。
またプルーストには
「自然のなかのものは、そこに無限の美が体現されているから価値があるので、どんなに美しくても、それ以外の価値をもつような特殊な形などは存在しない。林檎の花にしても赤いさんざしの花にしても、そうだ。それらの花に対する私の愛は、無限である」
と、「アミアンの聖書」の序でのべている。
プルースト、ワイルドと同じ花への同質の思いが、ガレにもうかがえる。その点が、花をモチーフにしながら、ドームと全く違う。ドームにも「昼顔」をモチーフにした花器がある。(ナンシー派美術館蔵)
ドームの「昼顔」の花器は、昼顔の花そのものの形体を花器にしている。青と乳白色のぼかしを使ったガラスの花瓶は、昼顔の花弁の薄さをうまく表現しているが、ガレの「10月の昼顔」にあるような濃密な花のエロチィシズムは感じられない。それは、同じように花を愛する園芸家でありながら、ガレとドームとでは花への思いいれが異なっていたからである。
ガレが、アトリエの壁を這う昼顔をデッサンしていた頃、高島はアパルトマンでようやく落ち着いた日々を迎えるようになっていた。
9月に入って、ユッソン家の長男、アンリが結婚した。東部鉄道に勤務しているアンリは勤務先がエピナールというナンシーから40キロばかり行った町に変ったので、結婚を機にナンシーを離れた。女の館となったユッソン家に、高島は世間の眼を気にして足は遠のいた。時々、女中のバレットがユッソン未亡人やブランシュの手紙をもってやってきたので、休日に招かれていくことはあった。
しかし高島はビエネールやカミーユ・マルタンといる方が実際はずっと気持ちがくつろいだ。
高島はリモージュに日本画を寄贈したことで、新しくナンシーや隣町のマルセヴィルから招待を受けることがあった。
貴族から招待され町の名士になっていく高島
ムールト川を越えたマルセヴィルのクルーという貴族からパーティに招待をうけたのは、秋の初めだった。アベル・クルノーという貴族は、回教寺院のモスク風の館に住んでいる画家だった。ビエネールの友人であるその貴族は“クルノーの城”と呼ばれるモスク風館の中を得々と案内してくれた。
廊下にはヤシの鉢植えがあり、部屋にはペルシャ絨毯が敷かれ、アラビア風のカミーユ・マルタンのアトリエをもっと豪華にして整理した感じだった。
「ユニークな館ですね」
高島は、ガレ邸とはまた違うこってりとした装飾過多の部屋にあきれていると、アベルは
「祖父がこんな妙な館を建てたのですよ」
と、微笑していった。そばにいたビエネールが、アベルの父親、シャルル・クルノー(1904年死亡)は、考古学者でロレーヌ博物館の館長をしていたことを話した。偉大な画家ドラクロアと一緒にモロッコに旅行したことがあるのだと注釈をつけた。画家のドラクロアといわれても高島には、何のことかわからなかった。
「ドラクロアはとても偉大な画家です。“キヨス島の虐殺”や“自由の女神”という作品は美術史に残る傑作です」
アベルは、ドラクロアという名前をいうときだけ力をこめて言った。アベルは、父親と自分とで収集したものだといって、東洋のコレクションをみせた。中国の陶器、象牙や翡翠で細工した置物、アラビアの壷、日本の浮世絵と陶器、鍔(つば)や根付といったものまでがなにの整理もされず、一室に飾られていた。さすがに貴族だけに、ガレやヴィエネールの日本コレクションより量も質も高かった。
「フランスでこんなに日本のものを沢山みられるとは思いませんでした。ここがフランスの町だということさえ不思議です」
高島は、眼をむいた英仙の女の顔や収斂した指先のどこにアベルやヴィエネールが、美を見出しているのかつかめなかった。しかし彼らにとって英仙や北斎がただエキゾチズムだけのものではないことはわかった。
「フランスが、外の世界に眼をむけているとき、フランスは最もフランス的なときなのです。今は、その意味で最もフランスらしい時代です。フランス人というのは、文化交流を求める国なのです。他の国から文化を吸収し、自分流に消化する。消化できるというのが、僕は文化の高さだと思います」
アベルの言った言葉を、高島はパーティの帰り道に反芻していた。他の国の文化を受け入れるというのは、受け入れても消化できる自信があるからだというアベルの意見にフランス人としての誇りをみた。日本人は、いつそんな風に言えるときがくるのだろうか、と彼は思った。日本人だって昔は中国や韓国から文化を取り入れ、それを自国流に作りなおし、今では日本独特の文化にまでしてしまっているではないか。例えば、茶。かつては薬だったものを、今では茶道という精神修業の文化にしている。
高島は、ぶつぶつひとり言をいいながらアパルトマンの階段をあがった。部屋についてからも、彼はなにか興奮していた。なじみの女たちの宿に行く気にはなれなかったが、このままベッドに入る気にもなれなかった。彼は再び部屋を出て、夜遅くまで開いている店にいった。
「今夜は連れなしかい」
店の主人が声をかけてきた。
店の中はむせかえるような煙草の煙でけむっていた。アブサンを一口のんだ。炎が喉を通った。強いアルコールが彼を孤独にした。隣の男がしゃべりかけてきたが、高島は男が何度も何度も「ジェポネ」「ジャポネ」というのが妙に耳障りだった。
彼は店をでた。
アルミハクのような月がでていた。いしだたみの上に建物の影が黒い布を敷いたようについている。彼は、自分が孤独なのか、孤独を楽しんでいるのかわからなかった。あと半年で日本に帰るという思いが、彼の焦燥感をかきたてたり、反対に陽気にさせていた。しかし半年は、結構ながかった。
高島は歩いていた。気がつくとユッソン家の前にきていた。二階の部屋に灯りついている。マリーの部屋だった。彼はその灯りをしばらく眺めていた。窓が不意に開かれ、彼女が顔を出しそうな気がした。が、そんな偶然を信じるほど彼は若くはなかった。高島は、おつかいに行って道草を食った子供のようにあわてて自分のアパルトマンに帰った。その夜、マリーの顔を思い浮かべようとしたが、浮かぶのはマリーのうなじやウエストの細さ、開くと蛙の足のように広い手だけだった。
翌日、ユッソン家の女中が洗濯物を持ってきてくれたとき、マリーに渡してほしいと手鏡をあずけた。リモージュの作品を描いているとき、食事の用意をしたり、絵皿を洗ってもらったお礼の手紙も添えた。
その日のうちにマリーから手紙が届いた。
ふたりが逢ったのは、次の日だった。言葉は逢った途端に薄っぺらな口実にすぎなかった。なぜ今まで迷っていたのか、そうなってしまった後では、以前の逡巡がこっけいに思えるほどだった。高島の中でストイックに守られていたものが鳳仙花の種のようにはじけてしまった。
しかしはじけて飛んだ種は、大地に根付くことがないのを知っていた。その終わりの予感が、二人を奔放にした。まだ半年もあると思っていた時間は、今ではあと半年しか残されていないという焦燥感と不安に変り、高島を追いつめていった。ふたりは、広がった野火の中を逃げまどう二匹の獣のように激しかった。
甘い汗の匂いのなかで、マリーはほつれ髪をかきあげながら言った。
「ピエール・ロティの“お菊さん”を読んだわ。私はナンシーのお菊さん。日本につれて行って」
高島はマリーの顔をみつめ、それから抱きすくめた。マリーは彼の腕の中でも「連れていって日本へ」と繰り返していたが、その声はしだいに弱くなっていった。