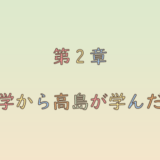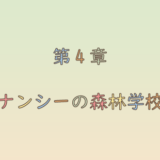高島がパリではなく地方都市ナンシーに留学した意味
人生の時間は、同じ速度で流れているのではない。その人の人生を決定づける時は、時計の針はゆっくりと重く動いている。高島にとって35歳から39歳の4年間は、彼の人生を決定づけるほど重要な意味をもつ。彼の人生だけでなく、美術史においても。高島がパリに留学したのではなく、フランスの地方都市ナンシーに住んだことは重要。
人口6万人の仏国北東の拠点ナンシー
1885年4月14日、朝8時。
宵ぱりのパリの街は、ようやく眠りから醒めたばかりだったが、パリ東駅の広場はすでにごったがえしていた。辻馬車が後から後からやってくる。1台の馬車が、強引に割り込んだ。主人をみつけた犬のようにポーターが馬車に寄っていった。ポーターは、馬車から降り立った客をみて一瞬目を見開いた。
濡れているような黒の髪の下に、支那の陶器のようなつるりとした顔があった。2つの目は、切り裂いた闇のように細く黒い。ぶ厚い唇は少しつきでている。
身長は1m80cm。明治時代の男としては高島は飛びぬけて大柄だった。この美丈夫な体形が、フランス留学時代に東洋人の蔑視から彼を救った。さらに彼の懐中には、1年間の留学費として日本円で千円、5千フランがあった。千円は家1軒分の大金である。今でも海外旅行を快適にするものは、身なりとお金である。高島はシルクハットをかぶり、ウエストを強調したフロックコートをみごとに着こなしていた。フランス語は生野銀山時代に身につけていた。旅人として、彼は完璧だった。
パリ東駅の構内はゴシック寺院の大伽藍に似ている。違うのは祭壇がないことと、祭壇にあたるところが、ぽっかり吹き抜けになっていて、汽車が煙を吐いていることだった。
構内は、汽車の石炭と煙草と酔っ払いが柱の影でした小便の匂いが、女たちの長いドレスの裾でたえずあおられていた。女たちが通ると、それらの匂いと香水の香りが混じった異臭の渦ができた。しかしコルセットでおもいきり腰をしめつけた女たちは、水鳥のように尻をふりながら構内を動きまわっていた。ホームを急ぐ乗客の中に、金モールで飾った軍帽に、反りのサーベルをつけた軍人の姿がひときわ人目をひいた。1870年の普仏戦争でドイツ領になったアルザス地方の主都、ストラスブールに向かうドイツ軍人だった。
車窓の風景は旅のアペリチーフにしてメインデッシュだ。ナンシーに向かう車窓の風景は旅人に多くの気付きを与えてくれる。
高島が見たフランスの田園風景
なだらかな起伏のなかに麦畑が続き、この国が豊かな農業国であることを改めて感じさせる。麦畑の彼方は靄の中に消えている。
のびやかな平地に、大きな荷物をおいたような林が現れた。ブナの林だった。
しかしその林は、日本のブナ林とどこか違う。高島は透視図のように福島や岡山で調査したブナ林と重ね合わせた。ヨーロッパでは、平地に林がある。川には堤がない。水面は、畑や人家と同じ高さだ。洪水の時、どうするのだろう。土手のない川は、田園に灰緑色の布を敷いたように野放図にのびている。日本とフランスの林が大きく異なることを思えば、森林に対する考え方も違ってくるはずだ。日本では川を治めた者が国を治めるといわれてきた。そんな治山治水の国からやってきた者が、フランスではたして学ぶべきものがあるのだろうか。高島は車窓を食い入るようにみつめた。
靄が切れて朝日が差し込んだ。
ブナ林のすみずみまで光がいきとどき、光は光を集め空中を浮遊し、そして霧散していく。今まで眠っていた世界は、光の粒子を当てられ輝きを増していった。
日本の4倍の国土をもつ国で、高島は好奇心という強靭な胃袋で、この文化を咀嚼しようとしていた。
汽車がナンシーに着いたのは、夕方の四時をまわっていた。パリから280キロ、七時間かかったことになる。
「巴里ヨリ凡七時間、当所ハ巴里ヨリ直西ニ当リタルモートル県ノ首都ニテ、此県ノ一半ハ独逸国ヘ割譲シタリシヨリ、今日ハ国境ヲ距テル甚近シ。市街海面ヨリ高キ、約二百メートルニテ丘陵ノ間ニアリ。人口六万余。府中ハ高塔傑閣衛ヲ挟ンデ起コリ、車輪馬蹄ノ響キ日夜、雷鳴ノ如クナリシモ、一タビ市外ニ出レバ頬ニ田舎ノ趣ヲ呈セリ」
(大日本森林報告)
高島は、ナンシーが「巴里ヨリ直西ニ当タリ」と書いているが、正しくはフランスの北東部である。この記述の中には、ロレーヌ地方という言葉がでてこないが、ナンシーはロレーヌ地方の中心都市である。
高島が留学した頃のナンシーは、1870年の普仏戦争で、ロレーヌ地方の隣のアルザス地方がドイツ領になったばかりか、ナンシーから50キロ北にある大きな町、メッツもドイツ領になっていたので、ナンシーはフランス北東部の拠点であった。
高島は、ナンシーの歴史や風土についてほとんど何の予備知識も持っていなかった。そのためかえって偏見にとらわれずに見ることもできた。彼は素直に驚嘆し、失望し、第二の故郷になるかもしれない町の美しさに感動した。
駅は、パリ東駅に比べると比較にならないほど小さい。ベージュ色の駅舎の屋根の部分には、ゴシック風の彫刻がほどこされているが、つつましやかなものだった。1852年6月17日に、この駅に初めて汽車が通って以来、すでに30年以上たっているので、駅はすすけて少し疲れている。
女たちの服装も地味で、野暮ったくみえる。地方にやってきたという感はぬぐえない。
高島は、パリの日本大使館の蜂須賀公使がしきりにナンシーは美しい町だと言っていたのを思い出し、どこが美しいのだと舌打ちしたい気持ちだった。
駅の広場には何もなかった。
まだ葉をつけていないプラタナスの並木がさらに殺風景さを作り出している。今日あるデパート”プランタン“の前身”マガザン・ルニ“もまだ建っていなかった。
しかし高島のナンシーへの落胆は、半時間後に一変する。
駅の近くにホテルを取ると、明日行く森林学校の位置を知っておくために町に出た。
彼は地図を広げた。
町はスタニスラス広場をはさんで、旧市街と新市街に分かれている。駅のあるのは、新市街だった。
フランス人ではない王が創った町ナンシー
高島は、ナンシーの中心に位置するスタニスラス広場に向かって歩きだした。通りに沿って石の家が並ぶ。石は砂岩である。砂岩の褐色が、明るいやわらかさを作り出している。
家々の戸は閉められ、人の気配もしない。家が並んでいる、ただそれだけの事実が、国によってどうしてこうも変わるのだろう。
「何か取り澄ました町だなぁ」
彼は通りを観察する。商店がある。果物屋だ。果実は店の中に木箱ごと並べられている。
ひと盛りいくらの値札もない。看板も地味で、持ち主の名前が軒に出ているだけだから、中をのぞいてみないと何の店かよくわからない。商売熱心とはとても思えない。きちんとおさまって落ち着いている。騒々しくない。なんとなくとっつきにくい町である。彼は萩の町の賑わいと無意識で比べていた。
サン・ニコラ通りを二百メートルもいかないうちに、正面に山吹色に輝く門が見えた。黄金の蔦をからませた門は、まるで夢への誘いのようにこ惑的で、凝視していないと瞬時に消えてしまいそうにあやうい。門に吸い寄せられるように足を速める。数歩も行かないうちに、彼は息を呑んだ。パリで蜂須賀公使が「ナンシーは美しい町ですよ」と言っていたのは、これだったのだとわかった。
門の奥に、典雅な白亜の建物がある。窓の淵飾りもバルコニーも金色に輝き、三階建ての屋根の周囲には、ギリシアの神々の彫像が建物を守っていた。建物の中央の三角形の時計台には、三人の美神が衣をなびかせている。時計台のてっぺんに、フランスの三色旗が黄昏の空にうなだれている。市庁舎だった。
白亜の建物から管弦楽器のファンファーレが鳴り渡っているようだった。広場を囲むように市庁舎、劇場、美術館、ホテルが建っている。建物は少しずつデザインは異なるがどれも白と金を基調にして仲の良い姉妹のように広場に向かって手をつないでいる。
その広場の中央に、長衣を着てカツラをつけた男が虚空を指差す銅像があった。像が指差す方向には、黄金のアーチに飾られたネプチューンの噴水が、白い水の花をさかせている。ベルサイユ宮殿を真似た噴水は、息苦しいまでの過剰な飾りで、眩いばかりの空間を作り上げていた。ナンシーの市民が誇るスタニスラス広場である。広場の中央の像は、この広場をつくったスタニスラスの像だった。
スタニスラス・レッキンスキー(1677~1766)は、名前からも分かるようにフランス人ではない。ポーランド国王だったが、北方戦争で敗北し、国王の座を追われ、フランスの支持で、国王の座に返り咲く。しかし今度はロシア軍に追われてフランスに亡命する。彼の娘がルイ十五世の后だったことから、フランス国王に支援され、ロレーヌとバロア(ロレーヌ西方)の地方を譲り受けて支配するようになる。1738年のことである。
流転の王、スタニスラスは、ナンシーを生涯の地と決め、情熱をもって当代一流の都市に作り上げる。スタニスラスは、ナンシー生まれの建築家、エマニュエル・エレ(1705~1763)に広場を設計させ、町の主要な建物を作らせた。
スタニスラスが死ぬと、フランス王国と併合され、ナンシーは一地方の都市となる。スタニスラス広場は、当時のまま時代の中を生き抜いてきた。町の美しさは、他国の王によって造られたのだった。
地図の横に書かれた広場の説明を読み、高島は再び新しい気持ちで広場を眺めた。百年も前に作られたものと思えないほど、新しく、どこにも老朽化がみあたらない。
しかし百年の間に、建物の持ち主は次々と変わって来たはずだった。そこには、時代を超えて残ってきたものの威厳と荘厳さがあった。
高島は故郷の萩城を思った。かつて五層の美しさを誇った天守閣は、明治維新になると、
これからは新しい時代だという理由で、古いものはどんどん取りこわされた。庶民の汗で立てられた天守閣は、あっ気なく、今度も庶民の手で取り壊されたのだった。明治元年に廃仏毀釈で、寺院や仏閣の取り壊しの時である。ひとつのことが駄目になると、それに関連したすべてのものを葬ってしまう。何かがあると、すべて同じ方向に洪水のように流れこむ。
「日本人って妙な国民だ」
日本にいた時は、気にもとめなかったことや、当たり前だと思っていたことが、こうして異国の地に身をおいてみると、その違いがわかる。高島は、日本とフランスの文化に対する考え方の違いを考えずにはおれなかった。異文化の前に立ちすくみながらも、スタニスラス広場の背後にあるものを学び取っていかなければならないのだと、自分に言い聞かせた。
夕方六時前だったが、まだ外は明るい。
街にあるアール・ヌーヴォーの装飾過剰な屋敷
広場からドミニカン通りにでると、急に人の数がふえる。「新市街」の中心の通りだった。商店街が並んでいた。
「萩に似て、風格のある町だ」
高島は半時間前に失望を感じたのも忘れ、格式のある街並みを好ましいと感じ始めていた。
通りの建物が、妙にごてごてと飾りたてた建物であることに気付いたのは、ドミニカン通りをすぎ、サン・ジュルジュ通りにさしかかった頃だった。
青銅の観音開きの扉には、葉を落とした木の枝の浮き彫りがしてあり、窓はこんもりと葉を茂らせる木の形になっている。枝の間にはガラスがはめ込まれていた。窓の淵には、緑の木を連想させる瑠璃色のタイルの装飾がほどこされていた。バルコニーは、渦巻文やギリシア雷文花鳥文に埋め尽くされ、眩暈をおこしそうなほどの過剰な飾りが付いていた。建物全体が、着飾ったおしゃべり女のようだった。
その上、建物の柱や尾根の上につきでた煙突には、こけおどしのような妙なくぼみがあって、見る角度によってそれは泣いている人の目にみえる。
次の建物は、さらに変わっていた。
恐竜の骨を横に並べたようなベランダを支える二本の柱も奇怪な動物の浮き彫りがしてある。建物の一部分は、一つの彫刻だが、全体をみると、装飾過剰で、不安定である。パリでみた左右対称の建物とは全く違う。
次の通りに入っても、執拗なほど装飾のある建物が目につき、それらはどれも最近建てられたものだった。「旧市街」では見られなかった建物群だった。アールヌーヴォの建築である。
「こりすぎている。こんな家に住んだら疲れるだろう」
高島がアールヌーヴォーの建物をどれだけ理解したのかはわからないが、少なくとも彼は木と白い漆喰と石でできた塀のある萩の武家屋敷の街並みの方が美しいと感じていたことは確かだ。塀の内側からのぞく庭木の緑、質実剛健な門、“萩”という言葉の響きさえ彼は美しいと思った。
高島が訪れた1885年頃から1900年にかけては、ナンシーの黄金時代であった。ナンシーの繁栄を作ったのは、優秀な人材だった。普仏戦争でアルザス地方がドイツ領になり、ブルジョア、知識人はドイツ領に住むことを嫌ってナンシーに移り住んだ。
しかし彼らはナンシーのブルジョア社会には入れなかったので、自分たちだけの社会を作り、しだいに財力を蓄えていく。
彼らは、自分たちの力を誇示するものとしてルネサンス様式の“パステイッシュ”の建物や、奇妙な装飾過剰な家をたてた。後に“アールヌーヴォー”と呼ばれる建物である。
ナンシーのアールヌーヴォーの建築ブームは、1880年頃から始まり、1900年にピークに達する。これは、パリのアールヌーヴォーとほぼ同時期である。ギマールがパリの地下鉄の駅をデザインしたのが、1900年である。(ナンシーには、アールヌーヴォーの建築物が53軒現存する)
ナンシーを栄えさせた豊かなた原材料
ナンシーを栄えさせたもう一つの要因は、豊かな資源。ロレーヌ地方は、木材、岩塩、石炭、鉄、羊毛を産出し、これらは近代工業に必要な原材料であった。特に鉄は、1878年にトマ方式が発見され、今まで鉄の含有量の低かったロレーヌ地方の鉄が見直されるようになる。石炭の方は、ドイツのザール炭田と地下層がつながっているので、豊富だった。
その上、これらの原材料を運ぶのに、ナンシーの郊外を流れるムールト川が、水路としてひと役かった。豊かな資源をもつロレーヌ地方は、十九世紀に飛躍的に発展をとげる。その真っ只中に高島は留学したのだった。
高島は再び地図をひろげた。どうやら森林学校を通り越してしまったらしい。前方にムールト川が見える。ナンシーの町はそこで終わっていた。1時間も歩けば郊外にでてしまうほど小さな町だった。