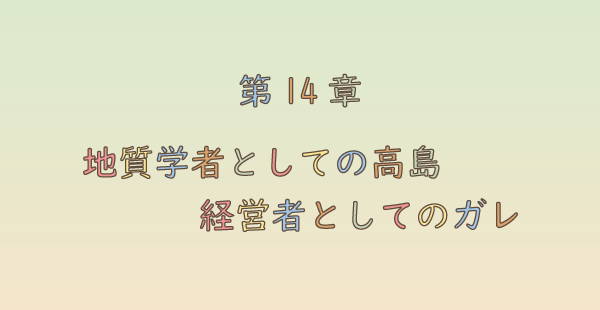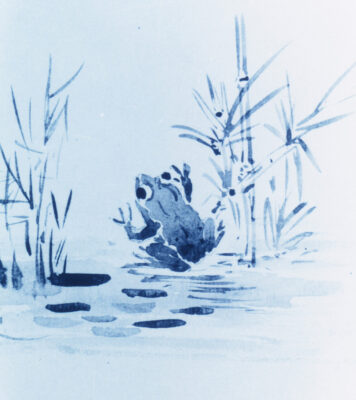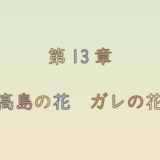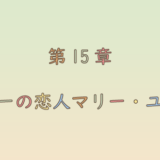高島にとって名峰は「人生の理想」の象徴
82歳で没した高島の人生で、彼がゆるぎない自信をもっていたのは、山を描くことだった。山に関しては「誰にも負けない」、なぜなら自分はその山を実際に歩いて足の裏に記憶しているからというのが、高島の自信の根拠だった。ワラジの底から伝わってくる玄武岩や花崗岩の感触から何億年も前に形成された山を知ることができたからだった。高島は、日本の地質学の祖といわれる和田維四郎(つなしろう 1856~1920)とも一緒に山林調査を行っている。なによりも高島自身、山が好きだった。山の清澄な大気、天にむかってすっくとそびえる山のいただきを見るとどんな鬱憤も消し飛んだ。山の頂点を目指す、それはこの男の権力志向のあらわれでもあった。
ガレにとって高島はどんな存在だったのか。
ガレにとって高島は有用な人間だった。そのために丁重にもてなした。ガラス工芸品を制作し販売する工房にとって、流行のデザインを取り入れ、新しい手法の商品を作ることは必須だった。世はジャポニスム時代、猫もしゃくしも“日本風”にうかれていた。支那と日本の区別も分らず、なんでもオリエント風なものはジャポンだった。明治時代、日本の絵柄の型紙が何万枚も輸出され、壁紙や服地、あらゆる日常品のなかにプリントされた例でもわかる。そんなジャポニスム全盛時代に高島が現れたのである。その日本人は背が高く、国立大学に留学できる知性をもち、絵画をたしなむ教養人だった。パリに支店をかまえ、ナンシーのアーチストたちを工房に所属させ、「ガラスの芸術性」を追求していたガレ工房の経営者は「時の人」であった。時代の旗手ガレは、新しいものへの挑戦を求められた。高島は新しいモチーフの提供者としてうってつけの人材だった。
ナンシーの画家たちは競って日本画に挑戦
1886年7月、高島はナンシーで2度目の夏を迎えようとしていた。
彼はすすめられてナンシー大学ホールで開催された「芸術友の会」(SOCIETE DES AMIS DES ARTS)に日本画を出品した。出品者はカミーユ・マルタン、ルイ・エストー、ヴィットマン、写真屋で絵を描くティロット、「ナンシー・アルチスト」の編集者で画家のヴィエルノー等56人だった。
ルイ・エストーは、日本画からヒントをえたモチーフと構図の作品を出していた。扇面の中に影絵のようにして雨合羽を着た3人の児童を描き、扇面の周りを竹と雀であしらった。竹と雀は、高島が以前に教えた墨絵をアレンジしたものだった。扇面の中は西洋の雰囲気で、外はオリエントといった具合だったが、奇妙な感じは全くなく、斬新でその中には新しい世界の展開があった。漆器に西洋料理を盛った新鮮さがあり、二つの世界はうまく溶け合っていた。
高島はエストーに教えた墨絵がこんな風にアレンジされ、しかも墨絵の良さを十分いかしていることに、駆け寄って握手を求めたい気持ちになった。エストーから日本画の装飾性を教えられたおもいがした。
カミーユ・マルタンの作品は、日本画そのものだった。題も「日本風」とあって、梅と鶯を墨絵で描いていたが、高島はこちらの方は買わなかった。日本画の筆の勢いもなく、ただエキゾティックな新奇さを狙っただけの作品だった。しかしやってきた人々は、マルタンの作品の前に長く立ち止まって
「おもしろい」
「ユニークだ」とほめた。
ヴィットマンのボージュの渓谷を描いた油彩は力作だった。画面の3分の2のところに渓谷を流れる急流を配し、周囲をモミの木で囲んでいた。急流の配し方や樅の遠近のとりかたは、日本画の風景画から盗んだことが明白で、高島をニヤリとさせた。日本画はさまざまな形でナンシーの芸術家の中に取り入れていた。それを見ることによって、日本画の特徴を高島はより鮮明につかむことができた。第一に構図、第二に省略、空白のいかしかた第三に黒と白の世界の無限の組み合わせ方だった。高島は、油絵は塗りこめられるごとに立体感を造っていることを知った。日本画と西洋画の違いは、針葉樹と広葉樹の違いに似ていると思った。ヒノキやマツ、スギの針葉樹は、削ったままの白木の肌が美しい。しかしヨーロッパに多いナラやブナの広葉樹は、木の材質が堅牢で木肌が荒く、削ったままでは美しくないが、塗装をするときれいになる。針葉樹は日本画の絵絹のようなうるおいがあり、広葉樹にはカンバスのような味わいがある。絵画もまた、その国の風土と大きく拘わり合っていることを高島はあらためて感じた。
この展覧会の高島の作品評は彼を面映くするほどよかった。
「高島は、実に不思議な巻物を出品している。彼の意志的な簡素さで、この作品は素晴らしい装飾的効果とまれにみる優雅さをもっている」
(ナンシー・アルチスト 1886年6月20号)
自分の作品が賛美されるのにすでに慣れっこになっていたが、それでもほめられると悪い気がしなかった。
ブランシュ・ユッソンはいつの間にかナンシー・アルチストの購読者になっていて高島がいくと赤鉛筆を入れた記事を、まるで自分のことが載っているように見せた。そんな時の彼女は、35歳より10も若い娘のはしゃぎようだった。
森林学校のボップ教授も雑誌評を読んでいて、教授が執筆中の「森林テクノロジー」の本の口絵に是非日本画の木の絵を頼みたいと言った。ナンシー・アルチスト誌からは、日本画論を書いてほしいと原稿依頼がきた。高島は、ユッソンに文章をなおしてもらい小文を次号にのせた。
「日本画の場合、独自で予見出来ぬ画法の簡潔さが問題である。筆跡は、意図的で正確であるが、下書きはしない。制作はいわば即興である。いくつかの目印の点々は作者にとって組み立てのために使われ、対称性を探すことなく、まずなによりも眼に心地よくなければならない。 ~中略~」
(ナンシー・アルチスト1886年7月4日号)
高島は日本画の即興性や眼の心地よさを強調した。それは彼自身が心がけていることでもあった。ナンシーに居ながら彼は日本画を描き、日本画について考えていた。そうした中で自分の将来の方向をめぐらせた。
7月に入ると学校は夏休みに入った。
ガレはパリ支店の移転を無事終え、陶器の町リモージュで開かれる展覧会の講演に行った。
ルモワンヌは夫婦でイタリアに旅行するのだと言っている。
高島はかねてから計画をたてていたことをいよいよ実行に移すことにした。バカンスを利用して森林学校のエノン技師と一緒にアルプスに写生に行くことだった。
その頃、パリの黒田清輝もベルギー、オランダ旅行を計画していた。黒田は1886年のこの年、画家に専念する決心を固め、旅先でヨーロッパの風景に接し、スケッチしたいと考える。黒田にとってパリ滞在3年目の夏である。夏休みは、今も昔も留学生にとって見聞をひろめる旅の季節だった。
バカンスに念願のアルプスを描く
高島が旅の支度をしているとマリーが現れた。マリーは気まぐれな天使のように気が向くとやってきて、半時間ぐらいとりとめもないことをしゃべってぷいと帰っていった。何かを言いにきたのだろうが、高島はそれをあえて聞かなかった。こわれやすいクリスタルガラスのような神経をもつ娘に、真正面からぶつかっていくことに戸惑いを感じていた。姉のブランシュは35歳という年齢もあって神経質だが、教師という仕事柄、冷静で他人と自分との距離のとり方を知っていた。しかし19歳のマリーはまるで山の天気のように変わりやすく、相手を傷つけ、相手を傷つけたことで自分を傷ついていくタイプの娘だった。高島はいつもマリーには傷つけないように心をくばっていた。
マリーは、高島がアルプスにいくのだというと
「なんだ、つまらない」
と、明らかに失望の色をあらわした。高島はそんな言葉におかまいなく、服を揃えながら
「アルプスに行ったことある?」
と聞いた。
「山なんかに行ってどうするの。私はまだ海をみたことがないの。海をみてみたいわ。ノルマンディーの海、見たいわ」
マリーは、部屋中を駆けながら歌うようにいった。
「海、僕は海辺の町でそだったので、海より山の方がいい」
「誰といらっしゃるの?」
「森林学校のエノン技師と」
「アルプスへ登るの、危険だわ」
「登山が目的じゃないのです。モンブランを描くんだ。ずっと憧れていた。ヨーロッパ一高い山だろう」
「山がそんなに好き?女の人より好き?」
マリーは壁にもたれて小首をかしげるようにして高島を見つめる。
「山と女性は比較できないよ。でもどっちも好きだね」
「どんな女性が好き?」
高島は、マリーが何を望んでいるのかわからなかったが、なにか自分が不得意な世界に引きずり込まれそうな気がした。
「どんな女性が好みだと思う?」
反対に質問を切り返して、この問題からのがれようとしたのに、かえって彼は相手の世界に引きずりこまされた。
「私が聞いているのよ。でも高島さんは無口でエレガントで柔和な女性が好きなんだろうと思うわ。日本の女性には、そんな女性が多いように思う」
「そのうえにもうひとつ、美人であることを付け加えてほしいね。マリー、あなたのように美人がいいよ」
彼は年長の男性としてサービスからそう言ったのだが、それがまたもやマリーの罠にかかることになった。
「無口な女ってこわいよ。高島さん、ご存知、女は黙っているときも嘘をつくのよ」
「おしゃべりでやかましい女よりましだろう?」
「嘘をつかれても?」
「それもいやだね」
高島は早くに降参して次の話題に移りたかった。彼は19歳の小娘を相手に女性論を言い合おうとはおもわない。彼の最も苦手とするものだったから。彼はマリーという娘の気持ちをつかみかねていた。彼女が自分に関心をもっていることはわかっていたが、それをどんなふうに扱っていいのかわからなかった。マリーは、ランのように女っぽいところがあったが、ランの中には昆虫が寄ってくると雄しべが急に伸びて虫を払いのけてしまう珍種があるように、うっかり寄っていくと振り払われてしまいそうな気がした。
高島は決して無粋な男ではなかった。後年、娘の園子に化粧の仕方まで教えるほどの男であった。彼は口紅を濃くしたときは、頬紅も濃いめにつけないと顔のバランスが崩れると娘の園子にアドバイスした。娘の白地の帯に自ら紫陽花をえがいてやるほど、娘をかわいがり、娘の服装にも気を使った。
しかし男女の機微に敏感という方ではなかった。
高島は、マリーとの距離をおいた。彼は慎重だった。2年先には日本に帰らなければならないという運命が彼を用心深くさせていた。
マリーはどこかで苛立っていた。しかし彼女自身も、本当はこの異国の男に何を望んでいいのか分ってはいなかった。2年後に男がナンシーを去っていくという決定的な審判を彼女はいたいほどわかっていた。だから高島の方が動けば、自分が逃げ腰になることもわかっていた。それなのに高島が慎重だと苛立ってしまうのだった。そういった矛盾がいっそう彼女を混乱に陥れ、エキセントリックな言動へと駆り立ててしまう。
「でも高島さん、無口な女って、結局のところ自分が言うべきことを何も持っていないだけかもしれない。無口であるのではなく、無知なだけかも」
「しかし西洋の諺に、雄弁は銀ナリ、沈黙は金なりってあるでしょう」
「それは、ふだん雄弁な人が黙っているから価値があるので、言うべきことを持たない者がただ黙っているのとは違うと思うわ」
「しかしおしゃべりな女は疲れさせると」
「あらゴメンナサイ。私、おしゃべりでずいぶんあなたを疲れさせたみたい。失礼しました」
マリーは急に眼を三角にして高島をにらんだかと思うと、ドレスの裾をひるがえして部屋を出て行った。高島は一瞬、自分の何が相手を怒らせたのか分らず、痴呆のようにつったっていた。追いかけていくべきだと思ったが、動かなかった。
「まぁいいや」彼は自分を制した。
高島は翌日ナンシーを発った。
ナンシーからディジョン、リヨンに向かい、リヨンからさらに乗り継ぎの夜汽車に乗ると翌朝、シャモニに着く。
7月のシャモニは、氷河見物の観光客でにぎわっていた。
1786年8月8日、シャモニに住む医師ジャン・ガブリエル・パカールとカモシカ狩りの狩人ジャック・パルマの2人がモンブランを征服してから、シャモニは注目されるようになる。
18世紀末からシャモノを訪れて氷河見物をするのが流行し始め、有名人たちがぞくぞくここにやってくる。ゲーテは1790年にシャモニを訪れている。ジョセフィーヌ皇后などは、68名のガイドの大部隊を組んで1914メートルのモンタンヴェールに登ろうとした。
7月4日、高島はシャモニの近くのゴルからセント・ロウレントを描く。
7月12日、今度はシャモニの北側にあるフレジェールからモンブランをえがくことにする。
フレジェールに行くには、シャモニから3時間ほど歩かねばならなかった。途中の山道には高山植物が咲き乱れていた。ガレだったらさぞかし喜んで、一歩も進まずに座りこんで写生しそうなエーゼルワイスやキスゲが短い夏を咲きいそぐように風に揺れていた。草いきれがする。薄荷の匂いのする大気が世界を包んでいた。一台の馬車とすれ違っただけで犬一匹出会わない。白く乾いた道が緑と空の紺碧の間から伸びていた。高島は炎天下の山道をリズムをとって歩いた。
山道を上り詰めたところに、レ・プラという小さな村があった。標高1877メートルのフレジェールの中腹にある村だった。そこからはモンブラン連峰、シャモニ針峰群がパノラマ状に広がっていた。
「ボンジュール、モンブラン」
同行のエノン技師が両手をひろげて言った。
高島はモンブランに向かって大きく深呼吸した。それから写生する場所をみつけるため、さらに少し歩きまわった。よけいなものが入らず山だけがくっきり見える場所をさがすためだった。
夕方、山の麓のホテルでエノン技師と落合うことにして、木陰に陣をとった。
モンブラン連峰は、何頭もの白馬がたてがみをなびかせているようにつらなっていた。彼の鉛筆は、視線より早く動こうとする。山を描きなれている高島には、ひと目見れば、描く対象を何度も見ないでも描くことができた。見て描くよりもその方が、ずっと形よく描くことができた。
しかし高島は、記憶が望む理想の稜線を避けた。視線がとらえたものを的確に紙の上に再現しようとした。ややもすると主人のもつ綱を振り切って走り出そうとする犬のように彼の鉛筆は勝手に走り出そうとした。
小さな山のひだも彼の視線はみのがさない。彼は視線をゆっくりとていねいに移動させる。視線は対象物に垂直に突き刺さり、地質をさぐり、山頂の気温をかんがえさせ、風の匂いをかぎとる。山に関して、彼の視線は妥協を許さない。視覚に占領され、彼の頭はからっぽになる。二つの瞳孔は、草原を走る獲物を狙う鷲のようにモンブランの稜線をなめていく。静寂さの中で、彼は視覚の悦びを味わった。
高島は鉛筆を置くと、淡く水彩をほどこした。後日、これをもとに大作に仕上げるつもりだったので、目の前に現物があるときに塗っておいたほうがよいと考えた。念のためモンブラン連峰の全景をスケッチの端に枠囲みで描き添えることも忘れなかった。
彼はモンブランに執着した。モンブランがアルプス最高峰だったからである。4807メートル、富士山より高いということだけで高島は気にいった。彼は高い山が好きだった。
高島はナンシー留学前に、山林局の役人として北海道と四国を除いてほとんどの山々を踏破している。そうした山林調査の中で、彼が気に入った山々をスケッチに残しているが、その大半がその地方で最も高い山々である。「津軽岩木山」や「駒ケ岳」「海門岳」「右田岳」など。
高島が山に託した思い
高島とって山とは、まず形のいい高い山でなければならなかった。周囲の連山から抜きん出て高い霊山は彼にとってこの世でもっとも美しいものであった。それは“こうありたいと思う精神の姿”であった。山は不屈の意志の象徴であった。
だから彼は、時には高い山を絵の真ん中にすえるという子供じみたことを犯してしまう。一番大事なものは、自然と中央に描いてしまうのだった。
高い山は、権威の象徴としてもみられるが、高島のなかにもそうした権力志向がなかったとはいえない。世は薩長の時代である。長州人の彼には、時の外務大臣、井上馨が後ろ盾になっていた。高島はフランスに留学し、前途に強い希望をもっていた。ヨーロッパ最高峰のモンブランは、高島に帰国後の自分の姿を重ねるにふさわしい山であった。
彼は、不屈の精神、清澄な精神のシンボルとしてのモンブランを描きながら、どこかで自分もまた人々を率いる立場になるとことを考えていた。
セザンヌが描いたサント・ビクトワール
高島がアルプスを描いていたころ、セザンヌも故郷のエクス・アン・プロバンスでサント・ビクトワール山を描いていた。
セザンヌにとって1866年は大きな3つの出来事があった。
十数年間も父に隠していた内縁の妻と正式に結婚したこと。父と和解し、その父が死んだため多くの遺産を相続したこと。もう一つは、親友のゾラがセザンヌをモデルにして挫折の画家の物語を書き、これが原因で喧嘩別れになったことだった。
45歳、高島より9歳年上のセザンヌは父の遺産が入ったことで生活が安定して、故郷のエクスで安心してサント・ヴィクトワールを描くことができた。セザンヌは標高1011メートル、三角形を横倒しにしたようなジュラ紀の石灰岩でできた山を愛した。
「このサント・ヴィクトワールをご覧なさい。なんという勢いだろう。なんと太陽をかつぼうしていることか。そして夕刻、すべてが沈みこむとき、なんと憂愁をたたえていることだろう」
と、セザンヌは書いている。
セザンヌは夕日をうけて「憂愁をたたえた」山にかぎりない親近感をもち、壮年に入った自分をダブらせた。
セザンヌは、故郷でも孤独な存在だった。人生の盛んな時期をとっくにすぎているのに、彼の名声は彼の自負と正比例していなかった。
セザンヌは角度を変え、何度もこの山を描いた。自画像を描く時のように。そして彼は印象主義の上に確固たる形態と構成を復活させ、サント・ビクトワールを透徹した構図で描きあげた。セザンヌは、サント・ヴィクトワールという自然を、目に見える外観を超えてある絶対的なシンボルにまで高めようとしたのだった。
高島には、セザンヌほどの構図や形態に対する試みや思考錯誤や闘いはなかった。それは、高島にとっての山が、最初から理想の象徴であったからだ。だからセザンヌのように角度を変えて、季節を違え、時刻をずらして一つに取り組む必要はなかったのである。セザンヌにとっては、サント・ヴィクトワールは彼自身であったが、高島にとっては、山は自分の理想とする姿であったから、その山は完璧なのであった。高島は、大きな山に向かい、自分もまたあのように悠然とした人物になりたいと願った。
だから高島は、嵐になる前の山や雨の日の山岳図は描かなかった。雷の中に一瞬うかびあがった不気味な山も描かなかった。理想の姿であるからこそ高島の描く山は、山頂に雪をいただき、裾野には滝があり、豊かな緑の木々が茂っていた。高島は、山をそびえる桃源郷として描こうとしたのだった。
セザンヌのサント・ヴィクトワールは、晩年になるほど前景がほとんど抽象化され、山だけが鋭い形を成していく。しかし高島の山は、晩年になっても山を正確にとらえることに変りはなく、むしろ山の裾野の雰囲気は一層、理想郷のおもむきを呈していく。高島自身は、自ら著した山岳論「写生要訣」の中に次のように言う。
「日本山水画の特色は実景を理想化せる点にありて、西洋画の精を写実につくするものにことなり。然れども画に於ける理想の、因って出る所の本源は実景にあること勿論なれば青年画家が、技能練習の上に於いては、流派の何たると問はず、先ず実景を研究せざるべからず」
日本画は風景を理想化するが、西洋絵画は風景の写実を念入りにすると高島はいう。そしてどちらの場合も、風景のなりたちを研究すべきだという。つまり山を描くなら、山の構造を研究すべきだという。山岳を描く画家のために著された80頁からなる「写生要訣」には、描くための技法と、山岳の形態をそれぞれ具体的な山を例にとってことこまかく解説している。
第一章は、山岳画についての総論で、第二章には地球の地殻の構造に始まり、どのようにして山ができるか山の成立が書かれている。山岳を形成する火成岩と水成岩とにわけ、それぞれの山岳の形態の特徴を示す。
「火成岩の中の花崗岩からなる山岳は、甲州駒岳、鳳凰山、飛州槍岳、越中立山の如く其外郭は危峭突元の状をなすこと多く、其内郭も亦畧外郭ニ類セリ、是等の諸山は土砂の崩壊せること少なく、且其半以上は往時氷河作用の為めに、削磨せられし形跡あるを以って山形一層の峭抜を極む・・・・」
と花崗岩からなる山の特徴を書いていく。そして駒岳、立山の図をそえる。
第三章は、山岳に付随する滝や洞について述べ、第四章はでは山岳を写生するときの注意をかきつらねる。高島は、山岳を描くためには、山の地質をみきわめることだと、繰り返す。
こうした科学の目を絵画の中に持ち込んだのは高島だけではない。レオナルド・ダ・ヴィインチは人体の腕を解剖しながら「モナリザ」を描いたといわれているし、遠近法を研究したパオロ・ウッチェルロ(1397~1475)も、幾何学を勉強し、それを遠近法にいかした。
高島の絵画論“心華”とは
しかし明治時代に山岳絵画論を地質学の面から確立しようとした高島の功績は大きい。当時、この本は画家たちの間で興味をもって読まれた。山岳にこれほどまでこだわり、その絵画論まで著した高島にとって、絵画とは何であったのか。
「要するに画は心華なり、性霊なり、又能く人の心を動かす能力あるものなり。しかし
模様は単に曲線の配合色彩の調和其宜を得て、人目を悦ばしむるものたるに過ぎず、しからば即ち画家は如何にしてよく人心を動かすに足るべき心華を筆墨の上に発せしむべきかのみ、而して之れを、心裏に会得するにあり」(「写生要訣」より)
絵は感動だと高島はいう。画家は心に感じた華を描くべきで、そのためには、しっかり描くもの性質を見きわめなければならないと言う。
高島にとって、心華となるのが山だった。彼は美人にみとれるように心をときめかしてモンブランを描き、ピレネーの山々を描き、富士山を描いた。セザンヌのように、ゴッホのように彼は自己と闘いながら絵を描くタイプの画家ではなかった。同じ山水画でも富岡鉄斎の山が荒れ狂うような心象を語り、饒舌なのに比べ、高島の山水画は、清潔感はあるが、お行儀のいい子供に似ている。しかし心の華である美は、それほど快適なものではなく、調和のとれたものではない。美はむしろ危険で、破壊的で、狂暴な力を秘めたエネルギーである。それは、愛が一見、誠実さや信頼に支えられているように見えながら、その実、嫉妬や猜疑心、独占欲といった暗いエゴであるのと似ている。もし高島が、恐ろしい山を描こうと思っていたら、彼の作品は全く変っていただろう。山林調査で山を歩き続けていた彼は、ひとたび天気が変れば山が狂暴な野獣となることを知っていた。しかし彼は、五月晴れや秋空の中にそびえる山だけを描いた。彼はあまりにも山への憧れが強いため、やさしい感傷に陥ってしまった。リリシズムとは、悲哀と歓びの同時存在、同量の存在であるのに、彼は歓びだけを拾ってしまった。セザンヌが「私の描くリンゴには歴史がある」と語ったように、物との交感なしに絵画は生まれない。自然もまた、人間のイマジュ以外に存在し得ない。山を「不屈の精神」のシンボルとして描こうとした高島であったが、彼の描いたのは「不屈の精神の勝利」であった。「不屈の精神」そのものは、強烈なエゴによって他者を打ち負かすものであるからだ。それは、高島得三という人間が、富岡鉄斎やセザンヌやゴッホほどアクの強い人間ではなかったからだといえる。高島は、どこまでも教養人であり、地質学森林学をおさめた学者であり、恵まれた環境で育った温厚な人柄の人間であった。
もし高島が、強烈な個性の持ち主であれば、ナンシーであれほどまでに多くの人々に好意をもって迎えられなかったであろう。高島はガレなんかよりずっと親しみのもてる“感じのいい(サンパテック)”人物だった。
高島は日本人として初めてアルプスの山中で絵を描いている自分に得意になっていた。彼の心は満ち足りていた。山岳画家への訓練を積んでいる自分に満足していた。
高島はモンブラン連峰を描き終えると、アヌシー湖からアルプスを眺めたスケッチをし、意気揚々とナンシーに帰ってくる。
彼のスケッチ帖には、アルプスの木々や高山植物を描いたものは一枚もない。徹底して山をえがいた。ガレもアルプスに行っているが、ガレはもっぱら足元の高山植物だけをみている。
ガレは「芸術ノート」に書き残している。「ナンシーでは貧弱なモクレンが、アルザス地方のヴォージュで大輪の花をつけている」ことや、「アルプス山麓の湖畔の村では、ローズマリーをミサに行くときつける」こと「薬用のセージやラベンダーがこの村の家々の壁に半野生にはびこっている」こと、さらに「クマブドウの木が、アルプスのマイナス15度の寒さに耐えて濃い緑を茂らせている」ことを書く。
ガレの視線は、地上の植物の上を蝶のように飛び交う。高島は、山ばかりを眺める。二人とも最も興味あること以外には全く関心を向けない点で似ていた。
ガレの花好きの背景
「この菊ですか」
「どんな花を想像していたのですか」
「“東京”ねぇ。東京は大都会ですからもっと大輪の菊かと思って・・・」
高島は、当てがはずれたといった表情で、ガレ邸の庭の菊を見下ろしていた。ガレから“東京”が咲いたから見にこないかという誘いがあったからやってきたのだった。高島は、クルースの家でガレと顔を合わすたびに「一度、自分の家の庭をみていただきたい」といわれていた。“東京”という菊が咲いたのを口実に、ガレは彼を誘ったのだった。
しかし肝心の菊は、嵯峨菊のような細い花弁の、卵大の黄色のなんの変哲もない菊だった。消え際の線香花火が、一瞬明るくなったような、どこかたよりなげな菊である。この花がなぜTOKYOなのかわからない。
「フランスで交配された菊です。名前には深い意味はありません。きっと日本に興味をもっていた人がつけたのでしょう。これなどは、“北京・パリ”という名前がついています」
ガレが指差したのは、ピンクの釦のような小菊だった。ガレはせっかく招いた高島を失望させてはと思ったのか、次々と菊を紹介した。
“アベオール”という菊は、海岸のパラソルのように陽気な花で、“10月の太陽”は白い碁石のような貧相な小菊だった。
菊の花壇の横には、人の背を越すほどのウイキョウがレースを広げたように細かい花をつけていた。その横には、バラ園が続き、さらに行くと花を散らした“きささげ”の高木があった。
「ずいぶんと広い庭ですな。一体何種類あります」
「数えたことはありませんが、数百種類のものが植わっています。ノートをつけているので、それをみればわかるのですが・・・」
ガレは友達に玩具のコレクションを自慢するように得意になって案内した。植物の種類は豊富だったが、朝市の八百屋のようにどこか雑然としていている。しかしガレの花瓶のように、この庭もある熱気を孕んでいた。海岸の岩の窪みの水溜りにイソギンチャクやウニや赤星のようなヒトデがいるように庭には、マリーゴールドやペチュニア、ルピナスといった草花が植えられ、9月の疲れた太陽の下で狂おしい芳香を放ち、香りと色の宇宙を形作っていた。
高島はガレの後からついて歩いた。二人が並んで歩けないほど花壇と花壇の幅は狭く、蛇行していた。花壇の中にはすでに花が抜かれて、掘り返されているのもあった。ガレは、夏の盛りをすぎた花壇を酔っているかのように歩いた。時々、立ち止まってカンパニュラ(風鈴草)に頬を近づけたり、アスターの葉裏をめくって虫がついていないかを点検した。
高島は『この男はふつうの花好きの人間とはどこか違っている』
と、ガレの後姿をみつめた。それは、ラン探しに森にいったときにも感じた疑問だった。同じ園芸家でも、クルースやルモワンヌたちは、花を交配させて新種を創り出す創造の喜びに熱中している人間だったが、ガレは花そのものに淫しているところがあった。花好きの人間が抒情詩の対象とするような愛し方ではなく、ガレのはいわば自分の欲望の象徴として花を愛しているように思えた。
高島は、ガレが花のなかに官能の世界と呼び交わす、なにか抽象的な秩序のようなものを見ているような気がした。ガレが、カンパニュラの花を顔に近づけているとき、彼は自分の肉感を花々に投射することによって、自分を花の同類としているような一種のナルシズム的な感覚を味わっている気がしたのだった。『どこか気持ちのわからない男だ』
高島は、ガレの花への傾斜が釈然としなかった。
庭の突き当たりに温室があった。その入り口に庭師のツッサンが、ランの株分けをしていた。
「ようこそいらっしゃいました。主人は、日本の昼顔の種を心待ちにしています」
小柄なツッサンは、手をとめて人なついこい微笑を高島におくった。
「なにがなんでも日本の種をお持ちしなければならなくなりましたね」
「私も楽しみにしています。日本の昼顔は、赤ん坊の帽子ぐらいあるのでしょう」
「いや、そこまでは大きくありません。しかし日本のは、こちらの昼顔より3, 4倍はありますが、ナンシーでも同じくらいの大きさになるかどうかわかりません。湿度と温度がちがうし、土が違うから」
高島は、あまり期待されては失望させると思い、あわてて修正した。
「でも青や紫の昼顔があるのでしょう、夢のようです、おおいに期待しています」
ガレはいっこうに分っていない。それをみたツッサンも、主人を弁護する。
「うちの主人は、日本の植物には目がないのです。日本のカエデをおみせしましょう」
「そうだ、高島さんにみてもらおう」
ガレはツッサンの思いつきに有頂天になって歩き出した。
日本のカエデは、1メートルも満たなかったが、緑の葉をせいいっぱい茂らせていた。ツッサンは、種からここまでに大きくしたのと自慢した。
高島が、カエデは秋になると紅葉して赤くなると言うと、庭師はナンシーの土質と温度、湿度の違いからか、葉は黄色に変るだけだと答えた。
「それじゃ、日本ではカエデが紅葉して山が燃えているようになるのですか」
ガレは夢みるようにつぶやいて葉に触れた。ツッサンは信じられないといった表情で首を振った。
カエデの横には、アメリカから取り寄せたという胡桃が植わっていた。
「ここには、いろんな植物があるのですね」
「そんな風にしたいのですが、まだこれからです」
「どうして花がすきなのですか」
「私の環境です。家族中が花好きでしたから」
高島は、環境だといわれてガレの花好きを少しは理解した。それは、彼自身も漢方医の家に育ち、庭に薬草が植えられて、花に親しんできたからだった。
ガレ自身は「芸術ノート」の中に、花好きについて次のように書いている。
「私の家庭には花に対する愛がいきわたっていた。それはいわば遺伝的な情熱であった。天の助けであった。私はいささかながら自然学の知識が身についた。私はあの“ロレーヌおよびフランスの植物相”の著者であるゴドロンの植物特集旅行の後を尋ねあるいた」
ここに書かれているゴドロンなる人物はドミニック・アレキサンドル・ゴドロン(1807~1880)のことである。ゴドロンはナンシー大学の理学部の第一人者で、医者でもあった。さらに彼はナンシーの植物園の館長だった。ガレは少年の頃、植物園に出入りし、ゴドロン教授から植物学の手ほどきをうけてきた。成長してからも教授のもとで植物についておしえてもらい、いわばガレの花の先生であった。ゴドロンが教えたのは、ガレだけではなかった。彼はナンシーの園芸家の指導者であり、大先輩であった。1887年、ゴドロンの部下であり、森林学校の植物学の教授M・フリッシュが「D・A ゴドロン その人生と仕事」(NOTISE SUR D.-A. GODRON SA VIE ET SES TRAVAUX)を書いている。
ゴドロンの薫陶を受けて育ったガレは、マニアックなまでに花好きであった。現在、ナンシー植物園に残されているガレが残した植物ノートには、彼の自宅の庭に植えられていた花の名前が全て記録されており、菊の章には83種の菊の名前が書き込まれている。ガレが好きだったバラやランの数となるとその何倍も多い。その記録帳は、A5版の分厚い台帳になっていて、花の種類ごとに分けられている。現在、ナンシー植物園では、ガレの記録帳をもとにガレ邸の庭の復元が進められている。
ガレはひととおり庭を案内すると、自分のアトリエに高島を連れていった。
「写生する花が、アトリエのすぐそばにあるのは便利です」
ガレは庭できってきたバラとカンパニュラを花瓶にさした。
前回来た時と同じようにアトリエはひっくりかえっている。こもっていた空気が、いけてある花の香りと花瓶の水の匂い、それに絵具と埃の匂いが混じってゼラチンのように固まっている。
しかしいかにもものを創る人のアトリエらしく、雑然とした中にある秩序があった。そこには、庭を歩いているときに感じたガレのナルシズムの影はない。能面も、竹筒も団扇も前と同じ位置にある。前回、気付かなかった団扇の奥に陶器の狛犬があった。高島はさっきまで感じていたガレへの不可解さが溶解し、親近感に変っていくのを自分の中に感じとる。
「一度、あなたの絵がガラスの作品になるところをみせてください」
「ああ、前にもそうおっしゃっていましたね。ガラスの製造は、マルゼンタールというところでやっているのですが、ガレンヌにも実験用の窯を作っています。それをおみせしましょう。そのかわり、日本画をみせてくださいよ」
ドーム工房の台頭
ガレは抜け目なく交換条件をだしたが、それは高島のプライドをくすぐるものだった。
ガレは1886年になって陶器の窯の横に作った実験用のガラス窯に高島を案内した。
「ガラスの製法は、企業秘密なのです。高島さん、あなただから見せるのですよ。ドーム工房の人達に口外しないと約束してくださいますか」
ガレは、いやにもったいぶった言い方をした。
「この世界は、苛烈な競争社会でしてね、いい作品を作ると、すぐに真似られてしまう。職人の引き抜きも激しい」
ガレの眉が険しく波立ち、つむんだ口のまわりに皺ができていた。ガレの端正な鼻梁の下に隠されている冷徹な経営者としての計算をみるおもいがした。
しかしこの時期、ガレがガラスの製造に神経質になっていたのは、無理のないことであった。ナンシーには、ガレ工房の他にドーム工房があった。当時は、ガレ工房の方が名実ともに上であったが、ドーム工房もガレが警戒するくらいに頭角を現してきていた。
ドーム一家は、普仏戦争でストラスブールがドイツ領になったのを機にナンシーに移り住んだ。ドームは、ストラスブールでは日常品のガラス食器、時計用のガラスを製造していたが、ナンシーに移ってからはガラス工芸品に力をいれるようになった。
ジャン・ドーム(1825~1885)には、優秀な息子がいた。長男のオーギュスト(1853~1900)はパリ大学で法律を学び、三男のアントナン(1864~1931)は、国立工芸学校を出ていた。兄弟は工房を経営し、弟がガラス工芸品のデザインと製造を担当した。
高島がナンシーに留学していた1885年から88年は、まだドーム工房はガレの存在をおびやかす存在にはなっていなかった。しかしドーム工房は経営が安定したのを契機に、1891年に芸術ガラス部門を設立し、いよいよガラス工芸品の制作にのりだす。高島がガレ工房を訪れて居たころ、ドーム兄弟は91年の芸術ガラス部門への設立準備を着々と進めていた時であった。ガラス窯では、アントナン・ドームによってひそかに実験が行われていた。
当然、ガレはそれを知っていた。ドーム工房はもともとガラス製造所であるから、ガラスについての技術や職人の腕は確かであった。今は、圧倒的にガレ工房が優位にあるが、いずれ力をもってくるだろう。ガレはそれを警戒していた。ガレが、工房の職人たちを大事にするのは、他の工房に引き抜かれないためだった。経営者としてのガレは、給料面でも神経をつかっていたが、それ以外にも職人たちが自分の工房で働くプライド、生きがいを与えることも忘れなかった。そのためには、職人たちのリーダーとしてのカリスマ性を自分が持たなければならないことを知っていた。ガレが率先して万博や展覧会に出品するのは、注文をふやすと同時に、芸術家エミール・ガレの名を高め、彼のカリスマを作るにも役立ったからだった。
ガラスを実際に吹いてみる・・・・ガラスは生きている
ガレは、高島を工場の二階へと案内した。
ガラスの炉は、ムーフラ窯と呼ばれる陶器焼の窯の一室の端にあった。ガラスを溶かす炉は、一階と二階を貫いて添え付けられ、職人たちの作業場は二階になっていた。
炉は、三つの赤い口をあけていた。石炭の火力によって1800度の高温にまであげられた炉の中は、船底に入るような轟音をあげ燃え盛っている。
炉の中には、飴状になったガラスの壷が数個はめこまれている。日本では“ネコ壷”と呼ばれる壷で、壷の数だけの溶けた色ガラスが入っている。
二人の職人が、壷に“吹き竿”とよばれる二メートルの鉄棒(現在はステンレス製)をつっこみ、溶けたガラスを竿にからませて巻きとっている。二人とも、ちらりとガレをみただけだったが、水を与えられた野菜のように彼らの表情に生気がやどった。
ガレは高島に説明した。
「作品の大きさによって、竿に巻き取るガラスの量を見積もるのです。これができるのに1年かかります」
ガレの言葉の最後は、炎の音に消されてしまった。
職人達は、壁に貼られた作品の形状の書き込まれた紙をみながら、作業を続ける。竿に巻きとったガラスを、「やっとこ」で指定の形にしていくのだが、これがひとすじ縄ではいかない。溶けたガラスは、アメのときのようにどろどろで、巻き取ったガラスはたえず竿を回していないと床に落ちてしまう。
しかし吹き竿は、細いもので1.2キロ、太い竿で1.9キロもあり、そこにガラスを巻きつけるので、かなりの重さになる。それを回しながら竿を吹く。
ガラス作りは、時間との闘いである。1800度に溶けたガラスは、竿に巻きとって吹いていくうちに、真紅から血の色、茶色、ねずみ茶色とみるみる変色する。夕焼けを何百もの倍速でみているようだ。
職人たちは、長い吹き竿を軽やかに回転させながら、竿の端のガラスを吹いていく。サーカスの曲芸をみているような軽快さである。
ひとりの職人は、大きなホウズキにふくらんだガラスを、濡れた新聞の上にころがせて形を整える。花瓶の胴の部分を作っているのだ。鈍い音がして、新聞紙から湯気がのぼる。何回か、新聞紙の上をころがせると、ガラスの表面がなめらかになっている。
次の職人は、再び竿を溶けた壷の中に入れる。胴を作っている間に、花瓶の口になる部分の温度が下がってしまったのだ。再び熱せられたガラスは、たった今、屠殺されて取り出された獣の内臓のように濡れて真っ赤に光っている。職人は、アメ細工の要領で、ハサミで花瓶の口を作る。威勢よく伸ばしすぎた部分をハサミで切り取る。床に落ちた三日月型のガラスは、熱帯の花のように赤く艶やかだったが、見る間に変色し、ねずみ色の鋭いナイフになった。
職人は、あらかた花瓶の口の形を整えるとバーナーで硬くなりつつあるガラスをあたため、さらに念入りに形を点検する。職人が合図をおくると、そばにいた助手が大きな「やっとこ」をもってくる。
竿からガラスを切り離すときがきたのだ。職人が、台の上に花瓶を寝かせると、助手が「やっとこ」で花瓶をつかむ。職人が、ハサミの頭でガラスと密着している竿の先端を2, 3回叩くと、花瓶は難なく離れ、助手の「やっとこ」の中に納まった。助手は、これを400度の徐冷釜に入れる。
除冷釜で形が崩れないように適当な温度を保ったまま、作品によって1日から1週間、長いときは1ケ月も置かれ、徐々に冷ましていくのだ。ガラスの表面に絵付けするときは、この段階でする。
助手が徐冷釜にいれるのを見届けると、職人は棚においてあったコップの水を飲んだ。ひとつの花瓶が徐冷室に入れられるまで、15分とかからなかった。大道芸を見ている楽しさがあった。
「みごとなものですね」
高島は、炉からの熱気で顔を紅潮させて感嘆した。
「ひとつためしてみますか」
ガレはいたずらっぽく誘った。高島はガラスの研磨のときの二の舞になるかなぁと思ったが、好奇心をおさえることができない。こういうとき、彼は実に無邪気に自分の感情に素直だった。
ガレは壁の端にたてかけてあった吹き竿を持ってきて、にやにやして高島に手渡した。
竿は、適度な重量感があった。竿を1800度の炉に近づけるのが、簡単にできない。熱風が襲う。体だけが尻ごみしてしまうので、竿を壷につけるが、ガラスが思うように巻けない。体は熱さから逃げよう逃げようとする。壷から竿を取り出すと焦ったため、いびつにガラスがついてしまい、壷から出すなり落ちそうになった。
今度は慎重に巻く。熱さで息ができない。取り出した竿を回しながら吹くのだが、みていたようにうまくできない。竿はガラスをつけて2倍の重さになっている。勢いよく吹くと、餅のようにふくれあがり、はじけてしぼんでしまった。これはいけないと、もう一度壷に戻そうとしたが、回す手が止まって、どろりと床に落ちてしまった。落ちたガラスは、軟体動物のように床にへばりついている。ガラスは見る間に変色し、液体から固体に変っていった。
「この段階でも3400度ありますから気をつけて」
ガレはそう言って注意をした。
「吹き方にコツがあります。まず竿の中心をもつのです」
ガレは竿をもつ高島の右手の位置をなおさせ
「手早く回転させながら、吐く息を一定にします」と付け加えた。
なるほど手の位置を変えると、竿がずいぶん軽い。
高島は竿を再び窯の中のガラス壷に入れた。今度はゆっくり巻き取った。炎天下の広場に引っ張り出されたように頭の芯が麻痺する。息をつめて、竿を動かすと、重いものがからんでくる手ごたえがあった。熱さに耐えられなくなって竿を引く。竿の先に丸々とした大きさのホウズキがついてくる。静かに吹くと、ホウズキがふくらみ、風船にそだっていく。水中を潜っているような重さがある。もう少し、とひと吹きしたときだった。育ちすぎた果実は枝から落ちた。
ガレと職人たちは、はじけるように笑った。
「だめです」
「むずかしいものでしょう。これは、宙吹きといいましてね、5年はかかるんです。ここにいる二人は10年選手です」
「なぜ、それを最初にいってくれないのです。恥をかかなくてすんだのに・・・」
高島は、体中の窪みから汗がおちるのをかんじ、体がむずかゆくなった。額からも汗が流れた。そのとき職人二人が少しも汗をかいていないことに気付いた。そのことを言うと、ガレは
「長い間に体が汗をかかないように多少、変化している」
と、職人たちを持ち上げた。二人の職人たちは穏やかな顔つきで、初めてみる日本人を観察している。職人達は、長袖の作業着をきていた。その方が、熱をさえぎるからだった。作業着の下に、何キロものガラスを軽々と吹く鍛えられた腕が隠されていた。
「あなたで、何年やってらっしゃるのですか」
高島が、さっき花瓶をつくりあげた職人に聞くと15年という答えが返ってきた。
「ガラス職人に必要な素質はありますか」
高島の質問に、男は軽く微笑して言った。
「左ききじゃないこと」
「どういう意味」
けげんな顔をしている高島にガレが得意になって説明した。1000度以上の溶けたガラスを竿に巻いて作業をするのだから、その中にひとりでも左ききの人がいると、竿がぶつかりあって大火傷やガラスの破片で怪我するというわけだった。しかし、工場内で火傷やガラスの破片で怪我をする者は意外にすくないという。
「150度から200度だと火傷するが、1000度のガラスだと、顔に触れても顔の油ですべり、かえって火傷しないものなのですよ」
さすがにガレは、経営者だけによくしっていた。
「しかしガラスというものは不思議なものですな」
「女に似ていると思いませんか」
ガレはなんでも女性に例えるのが好きらしい。
「温度のある間は、どんなふうにもしなやかになる。が、一度冷めるとびくとも形をかえないがんこさ、惚れているときは相手の言いなりになっていた女も、ひとたび気持ちが冷めるととりつく島もない」
「しかし女の場合、別れて時がたてば、懐かしくなってやさしい気持ちをもっていることはありますよ」
五十がらみの職人が言った。こういう話になると、フランス人は突然、饒舌になるのを高島はおもしろく思った。
「それじゃ、ガラスは女よりあつかいにくい」
ガレが言うと、赤ら顔のもう一人の職人が
「そればかりか祈るような気持ちで細心の注意を払って研磨していても、膨張係数があわないと、ある日、突然内部崩壊する。女のヒステリーより始末が悪い」
と、話にのってくる。“被せガラス”で何層にもガラスを重ねた作品の場合、外部の温度差が激しいと、わずかな膨張係数の誤差で突然ひびがはいることをいった。赤ら顔の男がガレにしみじみといった。
「ガラスは生きているのですよ。このガラスは、鉄とはひっつかないが、石とはひっつくのです。私達は、なだめたり、すかしたりしながらガラスを作っている」
ガレは、職人の言葉にうなずいていて、満足げに聞いていた。
当時のガレ工房がどのようなものであったかは、1931年に工房が閉鎖されてしまったので、写真でしかしのぶことはできない。しかしナンシーには、ガレのライバルになっていったドーム工房が、今も製作を続けている。ドーム工房は19世紀末に建てられた木製の床で当時のまま製作している。
工房は、長さ52m、横18m、高さ14mで、天井には明かり窓がとりつけられている。レンガ建ての工場は、黒くくすぶっている。3つの溶鉱炉で焚かれてきた石炭(現在はガス)が建物を黒く変えてしまった。
ガレの工房で作られた作品には、“型おし”はなく、“宙吹き”で造られた作品が多い。このことは、いかに熟練した職人を確保していたかを証明する。
“宙吹き”で作った作品に、ガレ工房ではさまざまな技法で加飾をほどこしていた。その技法は多岐にわたっていた。
工房では、“宙吹き”で形を作ると、その上に別の色ガラスをかぶせていく。“被せガラス”の方法がとられた。ガラスの素地に別のガラスをかぶせるというのは、理屈的には簡単なものであるが、現実には緻密な化学計算が必要となる。
さまざまな色ガラスは、鉱物の粉によってその色が作りだされる。青色は鉄、ベネチュアグラスが得意とした真紅は金を入れる。
しかしそれぞれの鉱物は、膨張する度合い“膨張係数”が違う。ガラスに別の色ガラスをかぶせる場合、膨張係数が一致していない場合、熱い間は密着していても、温度が下がると色ガラス同士が反発して割れてしまう。製作者は、このかぶせガラスの膨張係数を計算しなければならない。
ガレが19歳のときワイマールで鉱物学を学んだことが、ここで生きてくる。彼は植物好き、文学好きであると同時に、明晰な科学者の一面をもっていた。彼は、鉱物の性質を熟知していたから、ガラスに混入する鉱物量や膨張係数を計算することができた。実際に工房でそれをやったのは、職人たちであったが、鉱物学を学んだ彼は、彼らにさまざまな示唆を与えることができた。職人達は、ガラスの新しい技法の開発に熱心な“親方”を尊敬し、新技法の開拓に仕事への生きがいを見出した。ガレ工房が、腕のいい職人たちをもつことができたのは、ガレのガラスに対する高度な技術があったからだった。
工房の職人達はよく働いた。
ドーム工房では現在、夏の間は朝5時半から仕事が始まる。涼しいうちに作業をするためである。冬は6時半から、労働時間は9時間。
しかし高島がナンシーに行っていた1885年頃は、12時間労働だった。ガラス工場は炉の火を常に千度以上に保っていなければならない。一度冷やすと、その温度にあげるのに4, 5日はかかるので、工場では24時間の当番制がとられていた。
ガレのために日本から花の種を取り寄せる高島
あれだけのサービスをしてもらった後では、今度は自分がお返しをする番だということを心得ていた。高島は、実に律儀な男であった。彼は、何をガレに与えたら喜ばれるかを知っていた。だから話は、高島の方から切り出した。
「こんな絵を描いたのですが・・」
高島は持ってきたスケッチをひろげた。墨絵の蛙だった。蒲のはえている水辺に16匹の蛙が戯れている図である。種本は、最近、東京の兄が送ってくれた浮世絵本からとっていたが、そのことは言わなかった。
ガレの目が、スケッチにすいよせられた。
「蛙がモチーフ。これはユニークだ。今までにないモチーフです」
ガレは絵から目を離さずにつぶやいた。このとき、ガレは蛙の白い腹のふくらみをいかす形状と素材を考えていた。
ガレがあまり見入っているので、高島も黙っていた。
1889年、ガレはパリ万博にこの蛙をモチーフにした陶器を出品している。器の形は日本の茶碗からとっていた(パリ装飾美術館所蔵)
水辺の蛙たち、16匹のいろんな表情を茶碗の周囲に配し、茶碗の内側に、真正面に見据えた殿様蛙をデザインした。
ガレは、この作品によほど自信をもっていたのだろう、展覧会のカタログに次のように書いている。
「グラジオラスの緑色の透き通った地に厚ぼったいエナメルが蛙たちの腹をまん丸くする」
ガレは蛙の腹のふくらみを茶碗のふくらみに生かすことをおもいついたのだった。
一方、高島は蛙の絵がガレを喜ばせたことにすっかり満足する。この図柄が、諷刺画の好きなルネ・ビエネールにも気にいられることに気付き、ビエネールのもとでも描く。今度は二度目だから、手馴れたものである。この蛙の絵の一部は、ビエネールのコレクションの中に現存する。
高島がガレにどれほどの下絵を提供したのか正確な記録はない。
ガレのデッサン帳には、日本画からとった」「猛禽文クリスタル花器」の下絵がある。しかし、それが高島の下絵によるものかどうかを証明するものはない。ただ、明確なことは、高島の帰国一年後に開催された1889年のパリ万博に、ガレは日本画からモチーフをとった大量の作品を出展していることである。
ガレは、今まで墓地の花であった菊を大胆にモチーフに使ったし、蛙やトンボ、蝶といった今までフランス芸術の伝統になかったモチーフを好んで使った。
例えば「松枝文クリスタル花瓶」には、日本画の構図で松の枝が描かれている。枝は、花瓶の上から下へと伸びている。
1896年、工房の協力者であり隣人であり、友人であったヴィクトル・プルーヴェにガレは、松の象徴かつ装飾性の素晴らしさを書き送っている。
「家畜小屋から出た肥料にたよらずに成長し、孤高と厳しさを生き抜いて、松は夏も冬も薫り高く青々と茂る。薄い紅色の炉器――のような色合いと幾何学模様の、鱗片が被う松の伸びた幹は、それを眺める建築家に考える機会を与える。学校の(生徒たち)には、個性と雅(みやび)に満ちたモデルとして、闘技者のような腕の仕草、枝ぶりの習作課題を提供する」
ガレは1年中青々と茂る松の孤高と厳しさについて述べ、松の美しさを強調する。
しかし西洋には、松の孤高の美とする考えはない。図像学においての松は、常緑樹であることから不老長寿を表すことや、船の竜骨に松が使われたことから船舶を表したり、悲嘆、忍耐、陰気さを表す。西欧においての松のイメージは、それほどよい意味をもっていない。西欧絵画や工芸品に松がモチーフとして使われることは少ない。
ガレに松の孤高の美を教えたのは、高島得三である可能性は高い。高島は園芸に通じてその時々に、日本の植物にまつわる話、蝶やトンボの昆虫のイメージをおりにふれて話したと思われる。もともと文学的で、詩人の心をもっていたガレは、それを胸にとめ、作品にいかしていった。
それを証明するものとして、1884年の「装飾芸術中央連合会第8回展」の作品分と、高島との交流(1885年~1888年)のあった後の1889年のパリ万博の作品群とは明らかに異なる。
1884年の出品群には、アラビア、エジプト、日本、中国からモチーフをとった「折衷主義」の作品である。84年に発表された陶器には、伊万里焼の獅子や浮世絵からの鯉などが使われている。そして蝶やトンボもモチーフにしている。
しかしこの蝶やトンボを擬人化したモチーフの発想は、同じナンシー出身の画家グランヴィル(1803~1847)からえたものである。
グランヴィールは、早くナンシーを離れ、パリに住んでしまったが、ガレはこの画家の作品「活動する花たち」や人間の衣装や役を借りて動物を登場させる諷刺、ラ・フォンテーヌの「寓話」の挿絵から多くヒントを得た。1884年までのガレは、グランヴィールからの発想のものやエキゾチズムによるモチーフ、フランス芸術の伝統のモチーフが整理されずに、それぞれ個々に強いエネルギーをもって放出されている。
ところが、高島と交流した後の作品は、ジャポニスム一色に変っていく。モチーフに使われた蝶やトンボは、グランヴィールのそれをどこかに残しながらも、日本的イメージの濃いものに変化していく。「黒のシリーズ」に使われたトンボは、黒の花瓶に彫刻された二匹のトンボである。二匹のトンボは、花瓶の両側に配置され、水面に卵を産み付けようとするトンボが、もう一度水面の安全を確かめている図である。
こうしたトンボのイメージは、卵の産みつけた後、親トンボが死ぬことを暗示している。このトンボのはかないイメージは、日本的といっても過言ではないだろう。
ガレは高島との植物や日本画に関する会話、そして高島その人から“日本”というイメージをつかんでいった。ガレがめざす方向に、運よく高島という日本画のうまい植物にくわしい日本人が現れたのだった。その日本人は、気のいい男で、肩のこらない好人物だった。ジャポニスムといえば浮世絵と陶器と工芸品しかしらなかった彼に、北斎や広重とは違う日本画を教えてくれるのであった。ガレは高島という人間に関心をもったのではなく、高島が身につけている日本の伝統“ジャポン”というものに興味を持ったのだった。ガレにとって、高島そのものが“日本”であった。
ひとりの人間が異国に行くということは、その人間が育った国の伝統、文化が渡ることである。特に19世紀末、ジャポニスムの流行の中で、品物だけが先に行っていたとき、高島という人間が遅れて着いたのだった。人々は競って流行を取り入れようとした。そのひとりがゴンクールであり、ガレであった。高島という人間は、その意味でガレにとって格好の人物であった。
高島の描く日本画が、役人の趣味としての絵だったために、彼らはそこに日本絵画の普遍的定理を簡単に見出すことができた。もし天才の描いた日本画であれば、ガレたちは作品の完璧なオリジナリティをみいだしただけで、手法や技法を見出すのに苦労したであろう。
1889年のパリ万博において、ガレは高島との交流から“日本”を学び、日本的な雰囲気を作品の中に反映させていく。89年のパリ万博の後で、E・デ・ヴォーグがガレについて述べている。
「ひとりの日本人がナンシーで生まれたという運命の戯れに、われわれは感謝しょうではないか」
(“芸術ジャーナル”Journal des Artistes September 1894)
ガレは「ナンシーで生まれた日本人」とまで言われるようになるのだった。しかし高島自身はガレや他のナンシーの芸術家たちに自分がそのような刺激剤になり、影響力をもっていることを強く意識していなかった。彼は、ガレが後にこれほどまでの名をとどろかせるとは予想していない。高島にとってガレは、花狂いのガラス工房の経営者でしかなかった。