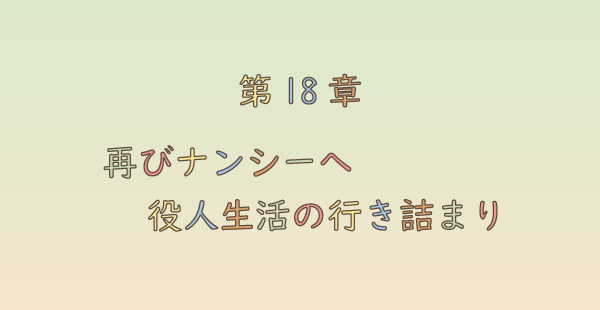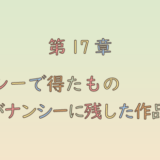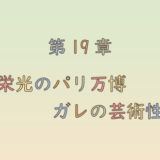53歳 ついに画家になる決心をする高島
「二足のワラジをはく」ことは、本人にとって幸せなことだろうか。高島のように芸術をめざす者にとって、役人として優秀であることはかえってマイナスの要因になったのではないか。なまじっかエリート留学をはたしたばかりに高島は、画家を選択することに躊躇していた。しかし時間は待ってくれない。芸術家に定年はないが、人生には旬というものがある。画を描くには、エネルギーがいる。毎日絵筆を動かし画を描かなければならない。描いているうちに習得する技があるからだ。画も役人稼業も片手間でやれる仕事ではない。
高島はナンシーで画家として立っていく自信を得たのに、ぐずぐずしていた。どちらも捨てられなかった。そのうえ私生活では結婚したばかりで、子供も生まれていた。高島のこうした優柔不断さが画家としての旬を逃してしまった。そればかりか役人としての頂点に立つことも逃してしまう。
森林学はフランスよりドイツの方が進んでいた。政府の目はドイツ寄りになっていたのだ。その背景には普仏戦争でドイツがフランスに勝ったことが起因している。フランス留学組の高島にとって不利だった。高島と同じ時期ドイツに留学していたライバルが、彼の上司になったのだ。
井上馨という時代の権力者の後押しがあり、恵まれた環境に育った高島が一流の画家になれなかったのは、彼の器用貧乏にあったかもしれない。
遂に美津子と結婚
高島が横浜に着いたのは、ナンシーをたってから55日がすぎていた。1888年、明治21年、5月7日、彼はエジンバラでの森林博をいれると4年ぶりに日本の地を踏む。
4年ぶりにみる日本は、埃りぽかった。東京には新しいビルが建設されていた。上野に可否茶館ができ、浅草に馬肉屋が出現し、貸し自転車が流行していた。
日本を出るときには、大都市を中心に短距離しか開通していなかった鉄道が、蔓のように延びていた。1月に山陽電鉄ができ、3月に関西鉄道、そして6月には九州鉄道が設立されようとしていた。新聞は、来年の7月に向けて新橋、神戸間の東海道線の開通工事について書き立てていた。世の中が、大きく音をたてて動いていた。埃りと人いきれが不思議なリズムを作っていた。高島は、パリ東駅に初めて降り立ったときの活気にみちた雰囲気を思い出す。
『日本は元気だ』
新しいレンガ造りの建物の前を、便所の汲み取りの荷馬車が堂々と通っていく姿さえも彼には、無性にたのもしくかんじられた。新しくできたものと昔ながらのものが、一つの器の中に押しこめられ、まばらな縞模様をつくっていた。
しかし高島は町の変化を眺めている暇はなかった。彼は、帰国するとただちに大庭学遷のもとに報告に行った。美津子がまだひとり身であることを確かめるとすぐに求婚した。今度はうまく運んだ。なにしろ彼は、将来を約束された洋行帰りだった。
結婚式は、何かに追い立てられるように急いで行われた。帰国後、わずか54日目に彼は美津子との結婚にこぎつけたのだった。花嫁は19歳、花婿は39歳と齢の離れたカップルだった。高島はなぜ結婚を急いだのか。自分の年齢のこともあるが、ナンシーのマリーの存在があったからではないだろうか。彼はマリーの情熱を恐れていたのではないか。
高島は、美津子との結婚によって、ひそかに計画していたことがあった。画壇への地盤固めをすることだった。画壇に縁者をもたない高島にとって、当時売れっ子の学遷の娘と結婚することは、最大の近道であった。
19歳の美津子が、泰山木の花のような毅然とした美人であることも、彼の気に入っていた。美津子の美貌は、今後,官吏として、画家としての階段をのぼっていく自分の将来を約束してくれるようにも思えた。
二人は根岸に新婚生活を持った。彼は、ようやく自分の足場をもち、人生に積極的に取り組んでいった。ナンシーの思い出に浸っていられないほど、高島の生活は多忙になっていく。
新婚生活を味わう暇もなく、7月、神奈川県の山林巡回を命じられる。年俸900円、彼は農商務省技師補に昇格する。
そして11月、技師補から技師に昇進した。なにもかもが順調に進んでいた。ナンシーは、すでに遠いものになっていた。日々の多忙さが、人をリアリストにする。彼はマリーのことも、絵画のことも忘れていた。
彼がナンシーのことを思い出したのは、年が明けた明治22年、1889年のことだ。イタリアとフランスの「蚕糸業実況取調」のため欧州出張を命じられたのだった。2月27日のことである。出発は3月10日と決まっていた。
出発まで11日しかなかったので、マリーやビエネールに手紙を出すのは、途中の港から投函することにした。たとえ時間があってもマリーに手紙を出す勇気が彼にあったかどうか。
マリーのことを思うと少し憂鬱になったが、またあのヨーロッパの大気に触れられるのだと思うと、泡立つような興奮を覚えた。チェスラン通りのアパルトマンが、夏の入道雲のように彼の中にひろがっていった。
そんな時、高島は妻、美津子の顔色をうかがった。美津子は、欧州視察の内示をうけたときから、目立って不機嫌になっていた。
「ナンシーというところにも、またいらっしゃるのですか」
美津子は、高島の顔を見ないで言った。日程がつまっているので立ち寄れるかどうかわからないと言っても美津子は安心せず、高島がフランスから帰ったとき、父親や周囲の者がどんな風にみていたかを皮肉たっぷりに打ち明けた。
「父は、あなたが3年間フランスにいらした間に悪い病気にかかっているかもしれないので、そのことばかり心配していました。あなたは松林さんと一緒にお風呂にお入りになったことがあったでしょう。あれは、あなたの体を調べるためだったのですよ」
美津子の嫉妬と苛立ちは無理もなかった。新婚生活が1年もたたない間に、夫が7ケ月も外国にいくのであるから、彼女は不安だった。3年半待って望まれて結婚したのに、夫は
自分にかまってくれず、仕事に忙殺されていた。
高島は、そんな美津子の嫉妬すら愛おしかった。
再びナンシーへ
ユッソン家は引っ越していた
高島がナンシーに着いたのは、イタリアのミラノ、トリノ、ローマの蚕糸業地を視察した後の8月になってからだった。
1年半ぶりにみるナンシーは、懐かしさというにはまだ記憶が新しかった。ちょっと長い旅から我が家に帰った安堵感に似ていた。町には、あの装飾過多の建物がまた増えていた。まるで童話に出てくる魔女や変わり者の住む館に似ていた。やたらとくねらせた柱や、柱にからみつく蔦の装飾、こけおどし的な人の視線を集めるバルコニーや窓の飾り、窓にはめこまれたステンドガラス、それらは高島には美しいとはいいがたいものだった。
『やれやれ、ナンシーの街までガレの花瓶みたいになってしまった』
高島は、まだ「アール・ヌーヴォ」という名称を持っていない建物を見ながら、ドミニカン通りのビエネールの店に急いだ。ビエネールに会えば、ユッソン家の事情も聞けるはずだった。
「おお、高島さん」
ビエネールは、信じられない事態に痴呆のようにつったっていた。それからビエネールの質問が矢継ぎ早に高島を襲った。
「ところでユッソン家に行くのかい」
「今から行くところだ」
「ユッソン家はもうナンシーにいない。引越しした」
ビエネールは声を落とした。その時、高島の脳裏を黒い鳥が横切った。今までぼんやりとしていた不安が形になっていこうとしていた。空の片すみにあっ雨雲が、陽をさえぎり、みる間に空をおおい尽くすのに似ていた。
「ユッソン家は急に引っ越ししたんだ。くわしいことはしらない。森林学校のボップ教授なら知っているかもしれない」
ビエネールがそれ以上触れなかったので、高島も聞くタイミングを失った。
ビエネールは、パリ万博にガレがガラス、陶器、家具の大量の作品を出品して注目を浴びていることや、園芸家のルモアンヌが新種の花を作り出したことを話した。が、高島はビエネールの声をただの音として聞いていた。夕食を一緒にというビエネールの誘いに承諾したものの、早くひとりになりたかった。高島は、夜にビエネール宅に行くことを約束してホテルにひとまず帰ることにした。
スタニスラス広場を馬車が車輪をきしませ、何台も行きかった。黄金の四つの門は、夏の陽の中で立ち騒ぎ、噴水のように金の飛沫をあげていた。
4年前に、彼をあれほど感動させたスタニスラス広場の光景も、今は宴会の終わった大広間の金屏風のようにむなしく感じられた。
高島は挨拶を兼ねてボッブ教授宅をたずねた。ユッソン家の話題になると教授はこまった顔をして自分も引っ越し先をしらないのだというのだった。高島はそのことにむしろ救われた思いがしていた。彼はこれ以上突き進むのをやめようと決めた。
高島の渡航日誌「巡回路程表」には、ナンシーでの記録がすっぽり抜けている。3月10日に横浜を出発、4月18日にマルセイユ港に到着し、どのような日程でイタリアの養蚕業の町を視察しかたが詳細に書かれているのに8月9日からのフランスでの日程は空白になっている。しかしナンシーに彼が立ち寄ったことは、ビエネールのもとに残る新聞記事から明らかである。
『多くの友人たちと率直で魅力的なつきあいをしていた親切な日本人、高島は今、ローマにいて近いうちにナンシーにやってくる』
(1889年5月5日付け)
高島はナンシーに再訪したことを書かなかった。彼は用心深い男だった。今も昔も「現地妻」は男の甲斐性として片付けられた。旅先の恋は、男の武勇伝にすぎなかった。日本人の国際結婚第1号は、イギリスに留学した尾崎三良(さぶろう 1842年~?)とされているが、尾崎は3人の子供をもうけながら妻子を残して帰国、日本女性と結婚し、重婚事件をおこしている、明治時代はそんな時代だった。マリーの一件は旅の恥はかきすてのように忘れさられたのだった。高島の描く花に色気がないのは、こんなところにも原因があるのかもしれない。
高島は予定していたナンシーの滞在を大幅に切り上げて、ビエネールやマルタンにお土産の浮世絵本を渡すと、追われるようにリヨンに向かった。
リヨンでは恩師のコワニエ夫妻に逢い、東部園芸博覧会で知り合ったリヨンの園芸家たちと逢った。リヨンの園芸家のリボワール・ペレから記事を頼まれ、日本の園芸について書いた。その記事は「園芸協会中央報告書」に載せられた。
パリ万博で不動の地位を築くガレ
パリでは万国博覧会が開かれていた。日本館は大変な人気だった。
高島はガレの展示会場に真っ先に足を向けた。そこには、高島が描いた蛙が日本風の陶器のモチーフに使われていたり、菊をデザインした水差しのセットや花瓶が飾られていた。ルイ・エストーの下絵やヴィクトル・プルーヴェの下絵をモチーフにしたものもあった。ガレがマジョレルと共同でデザインしたと解説に書かれた家具には、日本画の構図がそのまま用いられ、前景に梅の花、その背景に風景が広がっていた。
高島は、巧みに日本画を取り入れた作品群をみてまわった。どの作品にも「E・Galle」のサインがしてあり、それらの作品は「私がガレだ」「ガレがこれを作ったのだ」と、うるさく主張していた。ガレのどの作品も自分の名を歌いながら登場するオペレッタのように自己主張にあふれていた。
ガレの作品群は、一つの会場を占領するくらいだったが、高島はそこに経営者としてのガレの手腕をみただけで、やはりその作品に感銘をうけることができなかった。それらの作品は手が込んでいて、デザインも材料も凝りに凝っていたが、どれ一つとして高島は自分の部屋に飾りたいとも置きたいとも思わなかった。
『これじゃまるで刺身にホワイトソースをかけたようだ。自分はこの作品に美を見出すことができない。自分の審美眼がおかしいのだろうか。自分の許容量は、あまりにちいさすぎるのではないか』
高島はそんなふうに思いながら装飾過多のガラス作品群をみてまわった。そして黒の作品の前で足をとめた。黒色ガラスの上に「被せガラス」といわれる手法を使ってガラスをかぶせ彫刻をほどこした作品は、花瓶の銅部にスズメガやカミキリムシ、バッタなどの昆虫が浮き彫りにされていた。透明感が美しいガラスをわざわざ黒一色にして、その上に昆虫の生と死の生態が描かれているのだった。それはガラスという素材を無視した不思議な闇の世界を創っていた。墨絵の濃淡によって世界を創り出すように、ガレは黒が色の中の色であることを墨絵から学んでいた。その事に高島はガレの才能を感じた。自分が「席画」で見せた墨絵がこんな風に芸術品に昇華されていることが驚きだった。高島はガレの異国文化を吸収する力に感服したのだった。ガレの才能は日本美術を完全に吸収、租借し自分のものにしてしまう力にあったのか、と高島は気付いた。
高島はマリーのことを考えていた。「私、ナンシーのお菊さん」といったマリーの言葉が、海鳴りのように響いている。ブランシュの哀しい顔が彼を追いかけてきた。
3月に日本を出発するまえにあれほど懐かしく思ったフランスの地から今は一刻も早く離れたかった。ありがたいことに、その日は確実にやってきた。8月のおわりにはフランスを発つことが決まっていた。
そして彼は10月18日、日本に帰ってきた。
マリーの一件は、高島の心の中に深くしまいこまれ、ナンシー滞在中のものをほとんど捨て、その痕跡は消し去られた。
日本画壇に頭角をあらわす高島
高島は、多忙だった。農商務省の役人のかたわら絵を描いて、二足のわらじの生活をしていた。東洋絵画会に入会して、画家との交流も始まった。
明治23年(1890年)日本美術協会に「山村図」と「加州白山山頂雑卉放芳図」を出品し、3等賞銅牌を受け、明治28年にも「淡彩山水」と「連峰紅葉図」を出品、「連峰・・」は3等賞を受賞する。この時の二等賞は、川端玉章、野口小蘋、野村文挙の大家たちである。高島は、専門画家でもないのに、画壇に頭角を表わしていた。彼は画家として立つ決心はできつつあったが、生活は役人の日常をおくっていた。
高島家には長男、一郎が誕生していた。しかし一郎は、留守がちな父親の愛情の少なさを恨むように、明治4年、満一歳の誕生日を迎えずして死亡する。若い美津子は、次の年、長女、チツを生んだ。
全て順調に進んでいるかのように見えた。
しかし官吏としての高島にしだいに翳りがみえだしていた。森林法が制定されることになり、高島は明治27年「森林法調査委員」には一応任命される。
しかしこの時、高島は秋田大林区署に転勤させられていた。秋田にいて、どうして東京の委員会に頻繁に通い顔を出すことができるだろう。
森林法制定をあれほど願い、高島をフランスに留学させた武井守正は、このとき農商務省にはいなかった。武井は貴族院議員になり、明治27年には帝国海上保険株式会社の会長に昇進していたが、高島を支援するのには遠い位置にあった。
世の中はドイツ留学組が圧倒的に力を持っていた。それは、伊藤博文がドイツ憲法にならって帝国憲法を発布してからは、はっきりと世の中はドイツ志向になっていた。
高橋琢也の後を継ぐ次期森林局長は、ドイツで森林学を学んで帰国した志賀泰山とみなされていた。フランス留学組の高島には、高橋局長からお声がかかることなどなかった。高島はおもしろくない。家庭でも高島はおもしろくなかった。妻の美津子が宗教にこりだしたからだ。
美津子は、山林調査で出張しがちな夫の留守の心細さから日蓮宗に求めたのだった。一人っ子でなに不自由なく可愛がられて育った美津子にとって、いつも子供と残されている寂しさは耐えがたいことだった。夫が優しいねぎらいの言葉をかけていれば美津子も宗教にいれあげることはなかっただろう。美津子があまり日蓮宗に熱心なので、しばしば夫婦喧嘩のもとになった。
明治30年4月6日、森林法が制定された。そして8月に予想通り志賀泰山が、森林局長に就任した。高島の役人としての道は閉ざされた。あろうことか、志賀泰山は森林局長になるとすぐに高島を非職にした。ライバルは徹底して抹殺する必要があった。志賀にとって長州出身で、いろんな人脈をもつ高島は恐ろしい存在だった。志賀を恐れさすほど高島の農商務省、工部省においての功績は大きかった。高島は、長年の植物調査につき、明治25年に賞与されているくらいだった。相棒の田中譲と協力して作った日本全土にわたる森林調査は、山林局の財産であり、森林法制定もその調査書の上になりたっていたからである。
明治30年(1897年)飛騨高山で木曽御料林事件がおこる。村落が所有していた森林を役人がまちがって国有林にしたことがきっかけで紛争がおこったのだ。当時、木材は一大財産だったので、村民は収入源を失うことになり、大事件に発展した。その後、明治32年に国有土地森林原野法が公布され一段落するのだが、殺傷事件などがおきたことから、高島はすっかり役人生活に嫌気がさし、辞表をだす。48歳。高島は地位だけそのままで、役職を解かれる。最後の地位は、農商務省の福岡大林署長だった。日本の植物帯調査をして森林法制定の基礎をつくり、フランスの森林学校に留学し、その上長州の有力な人脈をもっていた男にしては、支店長クラスのこの地位はひくい。官吏としては不遇の末路だった。
「明治林業逸史続編」のなかに、林業回顧録座談会が収録されており、その中に次のような一節がある。
「川瀬 高島得三君は森林(局)の留学生ではないのだろう?」
磯山 それは、博覧会の出品の世話に行ったのだ。
本多 そうして絵ばかり稽古してきた
川瀬善次郎(1862~1932)、磯山広居(1866~1952)は、東京帝国大学農科を経て、後年、役人として大成した男たちで、高島よりずっと後輩組である。しかしこの3人の会話には、蔑視と嘲笑がある。高島が、農商務省でどのように同僚から見られていたかを想像することができる。高島は、職場では浮いていた。彼らには、画家と役人の二足のわらじをはいている高島は、やっかみの対象だった。高島が、日本美術会で銅賞をとったのは、官吏としての仕事を怠けているから絵が描けたとみなされた。
しかし当の高島は、一つの道を閉ざされたことで、ようやくふっきれた。画業に専念する決心をする。
10月、高島一家は美津子の父、大庭学遷の里、山口県長府に隠遁する。その時のことを高島は次のように語っている。
「明治30年遂にその職を退いた。その時の目的は、全然閑地に就いて今迄蓄へた多年の抱負を画帛の上に試みようとしたのであって、暫く郷里の長府に隠遁したのである」
(「余の山岳研究」)
一気に中央画壇に入ればよいものを、用心深い彼はここでいっぱく置いてしまう。そして長府で、山口県豊浦中学校で図画を教えるのだ。
彼が中央に戻るのは、それから5年後の明治35年(1902年)、53歳という老境に入ってからだった。ようやく長州の人脈をたどって中央画壇への復帰をはたす。彼のなかには、もはや燃え立つような野心はなかったが、静かな闘志はあった。ナンシーの芸術家をあれほど魅了させたという自負もあった。
53歳で画家デビュー
53歳になって、慎重なこの男はようやく自分の残りを賭けてみる気になったのだった。
その頃の日本画壇は、新しい日本画の理想に燃える横山大観、菱田春草の実験的な「朦朧体日本画」が非難をあびながらも、少しずつ評価されているときであった。
京都では、竹内栖鳳がヨーロッパの美術を見聞して帰国したばかりで、日本画の伝統の中に未来をつかみとっていた。
日本画壇は、老大家の死と大観、春草ら青年画家の進出で、新旧交替の時期にあった。高島は、その中で旧勢力の日本美術協会に入る。そのため、旧勢力の幹部の一員として新旧闘争の矢面にたたされるのである。ナンシーではジャポニスムのブームにのった高島だったが、日本では時代から見放されてしまう。
この時、用心深く思慮深い高島は、どの流派に属するかを考えたはずである。しかし他人と競うことが本来嫌いな温厚な性格の彼は、さっさと闘いの土俵からおりてしまう。生涯師匠も弟子ももたなかった高島は、孤高の道を選んだ。
明治35年3月5日、高島は汽車で上京し、4月1日までの間に、自分を知ってくれている引退した政治家を訪問した。元帥山形有朋、枢密院議長西園寺公望、曾弥荒助大蔵大臣などだった。中でも元上司だった武井守正をしばしば訪れ、武井邸で個人展覧会も開催した。
そして4月25日、家族と共に長府を離れ、東京の麹町区平河町6丁目14番地に居を定めた。
この年の11月、日本美術協会代32回美術展に、ときの総理大臣桂太郎の推薦出品という形で出品された「霧巻畳障図」は、3等銅杯を受賞、53歳の新人は画壇にデビューする。
翌年の同絵画研究会で「山墨山水」で木盃賞状、さらに第5回内国勧業博覧会でも「山水双幅」により褒状を受ける。高島はデビュー後、またたくうちに日本画壇への地歩をかためていく。温厚な人柄が画壇に敵をつくらなかったからだった。
この年には、欧州山岳スケッチとその山岳研究の結晶である「写山要訣」を出版する。そして同じ年、彼はロッキー山脈写生のため渡米までなしとげる。
ロッキー山脈写生には、エピソードが残っている。高島の後ろ盾のひとりである井上馨は高島をもう一度政治の世界にもどしてやろうとして
「今、一番望むものはなにか」
と尋ねた。高島は井上の予想に反して
「アメリカのロッキー山脈を写生したい」と言ったという。
高島の言葉は井上を失望させたが、井上の尽力によってただちに高島の願いはかなえられた。
明治37年には、セントルイス万博の日本政府館で“席画”を描くために渡米する。高島は、行っている間に約6千枚の日本画を描き、見学者を驚かせた。会場にやってきた老婆は、一心に描き続ける高島の健康を気づかって
「きょうはもう帰ってやすみなさい。病気になるから」
と言ったという。
明治40年代になると、高島の画壇への力は不動のものになっていく。パリで知り合った岩下清周が、彼のパトロンとなった。
そして大正5年には、文展審査員にもなる。これには、すでに文展審査員になっていた武井守正の力が働いていた。
高島は66歳にして日本画壇の頂点に達したのである。美津子との間には、8人の子供が生まれていた。
しかし高島の作品は、彼の社会的な地位に反して、その作品は決して好評を博さなかった。ひとつには、日本画の新旧の対立があった。旧派に属する高島だが、旧派の中では浮いた存在だった。旧派の中では、写実を中心にすえた高島の作品は、科学的すぎて
「此の人は描けば描くほど素人画たることを暴露して来るらしい。是は恐らく科学的の写生ばかり依頼して古典の研究が足りぬ故ではあるまいか」
(「美術新報」明治41年3月12日号)
と評された。
進歩的な新派からは
「全く古人のなす所と相反し、而も別に創意的の妙とてはなし」
といわれ、第二回文展出品の「本邦高山植物」は
「高山植物は標本としては結構、画としては少しも面白味がない」
と評され、山岳を描いた作品は
「落機山以来、何時も同模型の山ばかりかくので少々鼻につく」
「高島北海の“山水”屏風一雙の大作だが、例の通り理屈っぽい写生画で少しも筆墨に冴えた處を見ぬ。学者が研究の結果を公するのも、今の画界には好個の刺激であるが、要するに報告であって制作ではない」(「美術新報」明治40年5月12号)
と酷評される。
高島の山水画への評価
日本画壇の最高峰までのぼりつめた高島であったが、翌年、文展審査員をおりる。そして再び長府に帰る。
その背景には、旧派の敗北があった。日本画壇は新派によって牛耳られる。
画壇の春山武松は「第11回文展日本画評」の中で、寺崎広葉の「白馬山八題」を「近来に於ける傑作」と推奨した。その理由に「西洋画描法の融和」をあげ、実際に山岳を踏破し、その本質を捉えた写真の基礎に立ちながら、西洋絵画の「光の問題」も解決していると絶賛した。春山は、寺崎の作品と高島の「朝鮮金剛山四題」を比較し、同じように山岳を扱いながら「雲泥の差」があると言いきった。高島がなによりも自信をもっていた山岳画の分野でも、洋画を念頭においた新しい手法が認められ、高島のように一途に「理想の山水」を追い求めただけの作品は、停滞しているとみなされたのだった。
高島がもし新派のグループに入っていたら、違った評価を受けただろう。ときの批評家から旧派の画家としてレッテルの貼られていた高島は“古い”とみなされたのである。ナンシーでは時代の波に乗った高島だったが、日本では時代に見放されていた。
昭和6年、高島は風邪をこじらせ、82歳でこの世を去る。病床の中で描きかけていた「月見草図」が未完のまま、絶筆となった。この「月見草図」は、水墨に淡く花のところに彩色をほどこしている。
高島は、生涯に一枚の油絵も描かなかった。