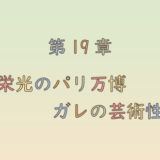高島がフランスから影響を受けたものは?
高島が帰国した19世紀末は、「和魂洋才」が美術界の主流の考えだった。「和魂洋才」とは、日本人の心で西洋の技術をとりいれるという考えであるが、異国で3年間暮らした高島は、西洋の技術だけを器用にとりいれることは本質的に無理だと考えていた。なぜなら、西洋の技術はその国の伝統や風土、宗教に根ざしたものだからである。
こうした高島の考えの根底にあったのは、日本の木の文化のレベルの高さをナンシーで実感したからだと考える。なにも西欧一辺倒にならなくても大丈夫だと彼は思っていた。
もし彼が森林学ではなく、法律や科学、医学のために留学していたなら、高島の西欧観は別のものになっていただろう。ジャポニスムという時代の流行が、高島に強い自信と日本人としての自負をもたらせた。
35歳からの留学という年齢も、外界のものに影響されないだけの体験をつませていた。そこが18歳で留学した黒田清輝と異なる点である。18歳の多感な青年にとって、フランスは刺激的な国であった。青年は貪欲にフランスの文化を吸収し、彼が実際にやりたかったのは、法律ではなく絵画であることに気付かせる。18歳と言う身も心も柔軟な年齢であるからこそしなやかに方向転換できた。
高島がパリではなく、地方都市のナンシーに滞在したことも彼の西欧感に影響を与えた。今日でも、地方の都市はパリに対してある種の強い対抗意識をもっている。特にナンシーは、普仏戦争で国境の町となっただけに、ロレーヌ人としての自負が非常に強く、パリに対しての意識も強い。ナンシー派と呼ばれる芸術家たちにとって、パリ派に一歩遅れをとっていただけに、自分たちの美術、ジャポニスムに対しての思い入れも強かった。パリ派への対抗意識を燃やす芸術家と高島が結びついていたことも、高島の意識に影響を与えた。
留学したほとんどの人達が、西欧かぶれをして帰ってきた中で、高島はより強く日本人であることを自覚し、日本画を描き続けたのだった。これは、不思議な現象である。
精神的には何の影響も受けなかったように見える高島だが、ほんとうに影響は受けなかったのだろうか。
高島は生涯に絵画の師というものをもたなかったし、弟子もとらなかった。彼は派閥というものに無縁であろうとした。その徹底した個人主義は、いかにもフランス的である。彼はナンシーでの3年間に知らないうちにリベラルな考えを身につけていたのである。もともと科学的な目をもっていた高島には、合理的な考え方をするフランス人のやり方が合っていたといえる。
フランスに滞在した黒田清輝も林忠正も、高島と同じようにフランスの個人主義を身につけてしまったがために、帰国してから周囲の者と人間関係でうまくいかなかった。黒田は帰国後、結婚するがうまくいかず離婚してしまう。そして「湖畔」のモデルである照子とは長い同棲生活の後に入籍する。
美術商の林忠正も、パリではゴンクールやガレとあれほどうまくコミュニケーションがとれたのに、日本人とはうまくいかず、日本の美術界で「浮世絵のすばらしさ」を講演して顰蹙をかってしまう。林は、日本人とはうまくいかないことを知り、晩年までパリと日本の両方に住まいをもっていたが、彼がのびのびと呼吸ができたのはパリであった。
高島が、あれほどの業績を残しながら官吏の道をとざされてしまった背景には、彼がフランスで身につけてしまった個人主義的な態度が原因していた。他人の忖度をはかる気配り社会にあって、個人主義の人間は、利己的な人間とみなされてしまう。「ウイ」「ノン」をはっきり言わないと物事が前に進まないフランスでその習性をつけてしまった高島は、他の同僚たちから、物事もズケズケと言う奴という見方をされてしまったのだろう。
3年間のフランス滞在は、高島に個人主義という無形の生活態度を残したのだった。
役人としての高島は、途中で座礁したが、画家としての彼は文展審査員として頂点までのぼりつめた。しかし日本絵画史のなかでは、旧派に属していたこともあって、しだいにわすれられていった。家庭人としての高島は、実に幸福な男であった。彼は美津子との間に8人の子供をもうけ、子供たちのよき父親であった。
高島は、60歳のときに生まれた末っ子の園子をことのほかかわいがった。時々彼は、園子にヒナゲシで花占いをした。
「来る(ビアン)来ない(ジャメ)来る(ビアン)来ない(ジャメ)」
その時だけ高島はフランス語を使っていたという。そしてフランス風に、食事時は「会話がごちそう」といい、いやな話、暗い話題はいっさいしなかった。だから子供たちにとって、食事のときが一番楽しく、にぎやかなひとときだった。
高島の生涯を振り返ったとき、なによりもこの男が幸運だったのは、健康な体に恵まれ82歳まで長生きできたことである。明治人としては異例の長寿である。普通の人が人生を終える53歳から、彼は第二の人生をスタートし、画家として最高の文展審査員までのぼりつめるのである。それは、健康な体力に支えられてこそ実現できたことであった。若い頃から山岳調査で足を鍛えていたことも長寿を支えていた。
高島の名は、現代では全く忘れられている。確かに彼は、偉大な画家ではなかったが、しかし豊かな生活人であったといえる。
高島の恋人マリーについてのその後の調査
高島の恋人、マリーはその後どうしたのだろう。
ユッソン家は高島が帰国して間もなく引っ越ししていた。その理由は分からない。わたしはナンシーの音楽学校で古い生徒名簿を調べた。そのなかにユッソンの苗字があり、エミリー・ユッソンの名前でナンシーのオーケストラの第一ヴァイオリン奏者としての記述があった。しかしエミリー・ユッソンが、あのユッソン家とつながりがあるのかは不明だった。
その後、通訳をしてくれた女性からの情報で、エミリーはいつも母親と一緒で母娘はどこへいくのにも連れ添っていたと聞かされた。地元新聞を読んで電話をくれた人と話ができなかったことが今さらながら悔やまれる。
ここまで打って私のパソコンの手は止まってしまった。
なぜ30年以上も高島に向かうことができなかったのか、原点に戻って考えることにした。
要するに私は高島得三(のちの高島北海)という人物にどうしても感情移入できなかったからではないか。高島のマリーへの態度も女性として納得できないものがあった。男尊女卑の明治時代には、留学時代の浮気は大目にみられたことかもしれない。二足のワラジをはいてぬくぬくと経済的に恵まれた生活をおくり、定年退職する年齢の53歳で、若いころからやりたかった絵画の道を歩き出す。自分が絶対的に自信をもっている山岳と花鳥画にだけに特化する。その“安全な暮らし方”にいら立つのである。
昆虫学者になっていたガレの孫と女優になった高島の娘
ガレに対しては、ガレの冒険心に喝さいをおくりたい。墨絵からヒントを得た黒のシリーズの挑戦、ガラスであることを忘れさせる被せガラスの手法によるカトレヤや昆虫の作品群、どれもガレの芸術家としてのあくなき探求心をかんじさせる。その探求心の強さは、ガレの子孫ジャン・ブルゴーニュにも受け継がれていた。
ガレには4人の娘がいたが、ブルゴーニュ氏は長女のひとり息子。私が会ったときは、83歳で国立動植物園の副館長をすでに退官していたが、世界的な蝶の研究家だと紹介された。ブルゴーニュ氏は「自分が1歳の時、ガレはガンで亡くなったので、ガレのことはほとんど知らない」と申し訳なさそうに言った。ちょっとかすれ声で静かなしゃべり方だった。ガレのアトリエには日本の竹筒や仏像があったと語り、庭には日本のモミジが植わっていたという。「ガレはやせていて身長は167.8センチで、私に似ているといわれる」と少し微笑んだ。
インタビューの内容は、ほとんど彼が母親から聞いていたガレの思い出話だった。最後にブルゴーニュ氏は「私もお願いがある」と言って台湾の昆虫学者に蝶のことを聞きたいのだが、手紙をだしても返事がこない。彼に連絡をとって手紙をくれるように伝えてもらえないか、というものだった。「台湾は日本の植民地だったでしょう。彼は日本語が話せます」と付け加えた。ガレもまた高島に日本の朝顔の種をこんなふうにねだったのかなとほほえましかった。蝶の研究家というのもガレの子孫らしい。私はすぐに承諾した。
日本の国立国会図書館は「日仏交流史」をデジタルアーカイブにして、誰でもパソコンで検索できるようにしている。「芸術」の章を検索すると最初にでてくるのは「高島北海 画家」とでる。次を押すと高島のプロフィールの中に「エミール・ガレを含むナンシーの芸術家との交流・・・」とある。高島のナンシーでの活躍もその後の半生についても詳しく書かれていて驚く。これを「高島は森林技師でしょう」と切り捨てたシャルパンテェ女史に見せたくなる。
高島の評価は、この30年で大きく変わった。高島の実像が詳しく報じられるようになった。これを知ったら河村幸次郎さん(故)はどれほど喜ばれるだろうと思うからだ。河村幸次郎さんは、高島の末っ子の5女園子さんの夫である。生前の高島の絵と人柄をしって尊敬し「北海先生の生き方や絵画の方法を世の人々に知ってほしい」と北海の回顧展に奔走した人である。「北海先生は、政治と株は嫌いでした。金には恬淡でした。とにかく山が好きでした」と高島の自慢話をはじめると止まらない。その横で妻の園子さんは嬉しそうにニコニコしていた。『園子さんは幸せな女性だぁ』と感じたことを思いだす。
河村さんは高島の遺品と作品のすべてを、高島が美術を教えた豊浦中学校のある下関市立美術館に寄贈した。そして高島について取材にきた者には、高島の花鳥図を便箋にした“花箋紙”のレターセットをお土産に与えた。それは河村さんが高島の花鳥図からデザインしたオリジナル便箋だった。河村さんの高島への敬愛と情熱はナンシーにも伝染し、「ナンシー派と北海」の回顧展がナンシーで開かれたのは私の取材からすぐ後だった。私はマリーの存在についてお二人には話さなかった。しかし河村さんは何か察しておられているようだった。
私はジャポニスムがナンシー派のアーチストたちに与えた影響ばかりに視点をあてすぎていたのかもしれない。
今、高島とガレたちは相互に影響しあっていたことに気付く。一人の人間が異国のアーチストたちに出会えば、互いに刺激され感化されるのは自然なことである。その目でみれば高島の描く山岳の構図は、西欧からとっている。なによりも師匠も弟子ももたなかった高島の生き方そのものにフランスの影響を感じる。高島は、ナンシーで自立したブランシュ・ユッソンのような女性と身近に接していたからこそ3女の愛子が女優になることを認めたのだろう。油絵を1枚も描かず、生涯日本画を描き通した高島の頑固なまでの信念に、「和魂洋才」などというどっちつかずの考え方をけちらしてしまうほどの強い意志を感じる。西欧に追いつけ追い越せの西欧の模倣に励んだ明治時代にあって、かたくなに自分を貫きとうし日本画を描き続けた高島の生き方もまたひとつの生き方だ。高島の頑固な個人主義こそが、高島がナンシーで最も影響をうけたものではないだろうか。
しかし私はなにか不服なのである。不服の原因を探っていくと高島が座右の銘のようにいっている言葉に突き当たる。「余は事実が物を言う」つまり事実が重要であると、高島は常々強調している。山岳を歩き調査した彼はフィールドワークこそが大事だと言っている。事実をていねいに調査して得た正確さこそが地質学において最も大切なことである。たしかに地質学において正確さは重要であるが、絵画、芸術において正確さはどの程度もとめられるのだろうか。
高島の富士山ろく草花事件を思い出すと、正確だから美なのかと、疑問がわく。レオナルド・ダヴィンチは死人の解剖から人体の構造を研究したが、人体を熟知したうえで自分の美を描いた。正確さを追求するあまりに、高島には正確を超えた美の追求心が希薄だったのではないかと思ってしまう。だから当時の美術評論家から「この人の絵は描けば描くほどつまらない作品になる」と酷評されたのではないか。人は完璧な正確さより、どこか欠けているところに「美」を見つけ出す。そうでなければ、欠けた茶碗に金継ぎをする「美」は存在しなくなる。人がその人に親近感をいだくのも、その人の欠点を個性として認めるからである。高島が安心安全な人間だったと評価しているのではない。そんな人物ならガレやナンシーのアーチストたち、マリーも高島に好感をもたなかっただろう。
高島はどんな性格の男だったのかの記述はない。しかし女優になった3女の愛子から類推する手がかりがある。
愛子は府立第3高女を卒業しているインテリ女性だったが、古川ロッパに誘われて皇族が経営する「小笠原プロダクション」に入る。同僚の女優、水島あやめが「高島さんは有名な画家のお嬢さんで、外人のような体格のいい、色白の美人でした」と語っている。また別の女優は「高島さんほど一風変わった女優さんはありませんでした。独特なタイプや容貌、大柄で肉づきがよく、頭髪はいつも油っけがなく、何日も手入れをしないクチャクチャした雀の巣のような頭、そのために発散するいやな頭髪の匂い~中略~入社以来おつきあいをしていると、お腹にはなんにもない、まことに善人でキサクな方でした」(「髪と女優」伊那もと著1961年)とある。愛子が自由奔放な女性だったことがうかがえる。彼女がのびのびできたのは、高島夫妻のおおらかな家庭づくりがあったからだろうと推察できる。愛子はその後、外交官と結婚するが、間もなく離婚、太平洋戦争末期の東京大空襲で亡くなっている。
わたしにとっての高島北海
高島は最晩年「高等遊民」と自ら称していた。昭和5年、妻美津子が亡くなると「女房が死んだのでもう生活のための絵は描かぬ」と宣言し、高等遊民としての生活を楽しみ、次の絵のモチーフを嬉しそうに話したという。園子の夫、河村幸次郎さんが「それでは美術館でも作りましょうか」と言ったら「美術館を作るための絵など描いたらロクな絵はできぬ。そんなことは微塵も考えてはならん」と叱られたそうだ。高島は客観的で高等遊民としての美学は忘れなかった。わたしはこの点で初めて高島に共感を覚える。
高島は故郷の萩や長門の島を歩き、故郷の景勝地を国定指定の観光地にするため尽力を尽くしたので、地元では「高島先生」と尊敬されている。高島は良き日本人だった。
ナンシーの取材から35年、「自分にとって高島北海とはどんな存在なのか」をずっと考えてきた。高島の「安全な生き方」を否定したかったからである。不幸な人生であってもいいが、みじめな生き方はすまいと考えてきた私にとって、高島の生き方は対極にあると思っていた。しかし齢をとり、今になってみると、人生に「安全な生き方」なんてあるのだろうか、と思うようになった。「人生は危険がいっぱい」と気付いた。その危険は、波が砂浜を侵食するように緩慢だからすぐには気付かないだけではないかと。高島のように安全で日々無難にすごすためには、どれだけの心配りやエネルギーをかけなければいけないかがわかってきた。だからといって高島のやり方が最善だともおもわない。私の高島に関する自問自答は続いている。