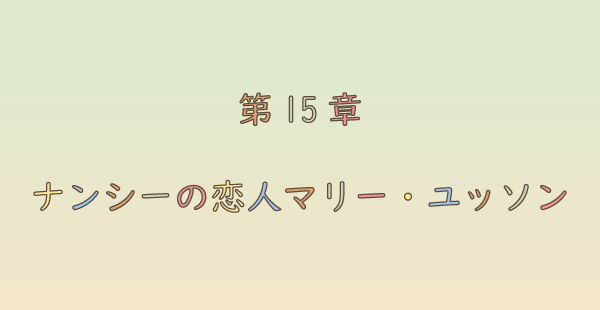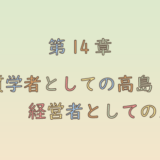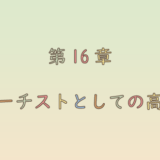高島を愛したナンシーの姉妹
ナンシーでの3年間。独身男性にとってこれは長い時間ではないが、恋が生まれるには充分な時間である。あるとき「(高島)北海は下宿屋の娘に惚れられて、日本に連れて行ってほしいといわれてこまったそうですよ」と、高島の娘婿、河村幸次郎氏は笑いながら話したことがあった。
1987年2回目のナンシー取材のとき、高島のナンシーでの生活をもっとくわしく調べるため、地元の新聞社に3枚の写真をもって飛び込んだ。1枚は高島のナンシー時代の写真、2枚は上流階級の中年女性の正装した写真だった。高島がナンシーでの思い出に写真に写っている本人からもらったものかもしれない。写真に裏書はなかった。
地元紙は、2枚の女性の写真に興味をもち、写真を大きく扱い「日本から100年前に森林学校に留学していた高島得三の調査に来ている。手がかりはこの2枚の貴婦人の写真だ」という記事だった。泊まっていたホテルのフロント係が「あんたの事が記事になっているよ」と教えてくれたので、おおいに期待していた。ところが、この時とんでもないまちがいを犯していた。連絡先の電話をナンシーの友人宅にしていたのだ。取材中に電話があったが、事情をしらない友人の娘は相手の連絡先を聞かずに切ってしまったのだった。年配の女性からだったという。二度と電話はかかってこなかった。
高島と親密な間柄だったとされる家庭教師ブランシュの妹マリー・ユッソン。彼女がピアニストだったことはナンシー市立図書館司書のリオネ女史のもとで判明していたが、ナンシーの音楽学校の名簿に彼女の名前はなかった。
ナンシーでの生活を謳歌する高島
ルネ・ビエネールから再びドミニカン通りのショーウインドウに展示する絵を頼まれたのは、ナンシーの短い秋が終わるころだった。
モチーフはすぐに決まった。ガレにスケッチブックを見せたとき興味を示した花と木にした。一回目のときのような気負いはなく、すんなりと描けた。その分、作品にのびやかさがでていた。
作品の批評は、その週の「ナンシーアルチスト」誌に掲載された。
「陳列窓には、日本画家の手による屏風絵、小さな絵、水彩画が展示されている。そこに描かれている可憐な花、木々の枝、葉の茂りに独特の味わいがかんじられるが、それでいてなお自然の真理に忠実である・・・・(中略) 高島は理想を追求しながら同時に現実主義を貫き通したが、それは彼が日本人であり、同時に森林植物学者であったからこそなし得た技であろう」
(1886年10月17日“ナンシーアルチスト”)
高島は、この批評を素直にうけとった。自分の絵が日本画と植物学者の二つの面からしかみられていないことをさして不満にも感じなかった。
彼は、この国の人々が自分の絵に興味を持つのは、“日本画”であるからだと知っていた。そのことは別段、彼のプライドを傷つけるものではなかった。高島は、ナンシーで日本画を描くことに、一つの意義を見出していた。日本について全く何もしらないフランス人に、日本がいかに文化的伝統をもつ、芸術性豊かな民族であるかを宣伝することは、彼にとって心地よいことであったし、それは日本の国のためにもなることだと思っていた。高島は、民間大使としての自分の役に誇りを感じ満足していた。
ガレをはじめとする人々が、高島を一介の役人すらこのような高尚な芸術的趣味をもっているとみていることが、彼にとって愉快なことだった。この時期、高島は将来画家になる心構えができていた。
森林学という技術畑の学者であった彼は、人間を有機的にみて分類していく才能は持っていたが、人間の本質を分析していき自己の内面と照らし合わせるといった面を持たない種類の男だった。彼の目は、いつも外にむけられていた。そして他人という目に写った自分をみていた。
知的な女性ブランシュ・ユッソンと交わす日仏文化論
高島は毎日が快適だった。
フランス語はマスターできていたし、授業に出るのが楽しいくらいだった。友人もできた。自分の作品によって、周囲の人間たちから一目おかれていることは、長州藩生まれの誇りの高い彼にとって気持ちのよいことだった。特にユッソン家の信頼は絶大なものだった。
ブランシュ・ユッソンは、「私の任務は終わった」といったが、高島は相変わらずブランシュに家庭教師料を払っていた。彼は自分の払う家庭教師料がユッソン家の家庭を助けていることを知っていたので、授業を継続していた。
ブランシュの方も気をつかい、週に1回、女中のバレットを寄こし高島の部屋の掃除をさせた。
今やユッソン家は、高島にとって憩いの場所だった。授業という名目であったが、二人はほとんどおしゃべりをしていた。ナンシーの歴史やフランス人の暮らし方、フランスと日本の文化の違いについて話題はいくらでもあった。高島が日本人の着物について例によって図に描いて説明すると、ブランシュはじっとその絵を見入った。
「なかなか機能的にできている。ひとつのサイズなのが便利」
言われてみるとなるほどと思った。身長にあわせて着物の丈は腰で調節できる。人間の体は肩と体の境界線がないのだから、着物のように直線裁ちでいいわけだ。それに、湿度の高い日本にあわせて、着物のたもとには通気孔がある。折りたたんで収納できるのも便利だった。
ブランシュのちょっとした言葉が、高島に日本文化について考えるきっかけをつくった。
日本では玄関では履物を脱ぐと説明すると
「靴を脱ぐことで、外と内との意識の切り換えをするのね」
と、ブランシュは即座に分析した。高島にはブランシュの明晰さが快かった。彼は知的なものも美しさであることを知った。そして知性とは感受性のもうひとつの代名詞であることを。ブランシュは、美人というには鼻が高すぎ、唇の薄さが年齢より老けさせていた。
しかし彼女がしゃべりだすと、頬に赤味がゆきわたり、山奥の湖のような青い目に光が差し込んで活き活きする。
高島はブランシュと話しているとき、自分がなにか不思議な体験をしているような気がした。日本にいて不可能なことがあるとしたら、ブランシュのような女性と会話の楽しさを共有できないことではないかと思った。
高島にとって、友情的な感情で異性と話ができるのは、気持ちのよいことであったが、時々それが乱れた。冷静で知的なブランシュは、不意にむき出しの女をみせて彼を戸惑わせた。
「高島さんは、私のような女をどうおもわれますか」
こんな質問をされると、高島は返答につまった。女という言葉のところだけが、赤くぬめっているようで、女性に一ヶ月ごとに訪れる生理を感じたりした。
『この人は、自分のどんな答えを期待しているのだろう。自分が考えているより、もっと女っぽい女性なのではないか。それに気付かないので、彼女は苛立っているのではないか』
高島は自分の用心深さを責められているような気がした。
ユッソン家の姉妹から愛された高島
しかし高島がこまった表情をしているのをみると、ブランシュはすぐに自分のいきすぎを是正し
「結婚しない女性は、変人にみられるのですよ。好き好んでこんなふうにしているわけじゃないですのに」
と、少し自嘲のまじえた穏やかな口調に戻った。こんなときマリーなら、きっと高島の答えを引き出すまで引き下がらないだろうと思った。高島は、ブランシュになぜ結婚しなかったのか、これからだってその機会はあるだろうと言おうとしながら、彼はその言葉を口にしなかった。もしそれを言葉にすれば、二人の間が急激に深まるだろうとどこかで恐れていた。
『いずれ日本に帰らなければならないのだ』そのことが、彼をいつも慎重にさせていた。ブランシュは、詩の話題になると急に少女ぽくなった。詩を読むとき、彼女は熱心に祈りをささげる信者のように敬虔で陶酔的な表情になった。とりわけパリで活躍しているシュリ・ピュドム(1839~1907)の詩が好きだった。
ブランシュの説明によると、プュドムは高踏派(パルナシアン)と呼ばれるジャンルの詩人で、内面派詩人として独自の道を歩み、哲学的思索のうちに精神の苦悩や道徳的省察に自分の領域を見出しているということだった。この詩人は1901年、第一回ノーベル賞を受賞している。
「私はさまざまな苦悩にみちた魂のことを考える。
そこには、むかしのいろんな愛が眠っている。
涙はすべて凝固してしまっているが、そこではいつも何かが泣いている」
ブランシュは、プュドムの「鍾乳石」の最後の一節を読み終えた。魂を鍾乳石になぞえた詩だった。「何かが泣いている」のところで、ブランシュの声は震えていた。遠い昔の思い出が、彼女を息苦しくさせているのだと高島は感じた。ブランシュは、「鍾乳石」の詩をA5版のノートより小さい(縦11.5 × 横8.9cm)の紙に美しいペン字でわざわざ書き写していた。
「詩も美しいけれど、ブランシュ、あなたの字に惚れ惚れしますよ」
「高島さん、私の気に入った詩を何点かさしあげますよ」
「それじゃ、詩に挿絵を描きます」
「それはいい考えですわ。私達の記念的な詩画帖になります」
ブランシュが目を輝かせた。
この「フランス詩画帖」は、詩編が13編、高島の水墨画が12点つけられている(下関美術館所蔵)13編の詩のうち、ほとんどがプュドムの詩で、他にアントワーヌ・カンポー、エミール・トゥヴィヨンの詩が2点ずつふくまれている。
高島は「鍾乳石」の詩には、鍾乳石の入り口の絵を添えている。「毀れた花瓶」には、野菊の生けられた花瓶を描いている。ブランシュは、よほどこの詩帖が嬉しかったのだろう、アントワーヌ・カンポーの詩に託して自分のおもいを綴っている。
「高島氏へ
私達の冬の思い出に ブランシュ・ユッソン
冬の便り、烈風オータンが吹きすさぶ10月から11月にかけて、ふたりきりで、部屋の暖炉の片隅に行って、山ほどのさまざまな話題を心おきなく語り合う。私にとってこれは甘味なことはまたとありません」アントナーヌ・カンポー
ナンシー 1886年10月24日
ブランシュは控え目ながらも、高島に自分の気持ちを告白したのだった。
しかしふたりの間には何もおこらなかった。ブランシュは息をつめ高島を待っているような時期があったが、その時期がすぎると二人は、幼い頃からの友人のような懐かしい関係になった。台風のない秋を迎えたようなもの足りなさはあったが、彼はその穏やかさが気に入っていた。だからなじみになっていた娼婦から
「あんた、ユッソン家の二人の姉妹とつきあっているそうじゃないの」
と、からかわれたとき、彼は少なからず驚いた。噂になっているのかと尋ねると、女は彼の反応にびっくりして訂正した。
「この町は小さいから。でも大丈夫よ。“東洋人がユッソン家に出入りしている”ということだけだから」
街の女たちが、この種の噂に敏感なのはわかるが、ナンシーもまた萩と同じように因習の強い土地であることを知った。そしてブランシュとは何事もなかったことを、ブランシュのためによかったと思った。
12月に入ると、ナンシーの町は急に活気付いた。
12月の第一日曜日は、サンニコラの祭りだった。スタニラス広場に野外ステージが作られ、サンニコラの伝統劇が演じられた。
17世紀、飢饉が襲い、もはや子供までも食べなければならない事態になったとき、サンニコラが現れ、子供たちを助けたという伝説だった。この日は、サンニコラの像をかたどったチョコレートや、蜂蜜の入ったパンド・ピスという菓子が子供たちに与えられる。高島もユッソン家に招かれ、ポテロレーヌというジャガイモとベーコン、ソーセージを煮込んだ地元料理の後、パンド・ピスをデザートに食べた。
そして昼食後、ユッソン未亡人の提案でブランシュ・マリーらと野外劇を見にでかけた。マリーが高島のアパールトマンにやってきたのは、その夜だった。
「たった今別れた人に、すぐまた逢うのはヘンな気持ち、楽しいわ」
マリーは、挨拶もしないで高島の部屋にすべりこんだ。高島がコーヒーを入れてやると
「高島さん、姉さんが好きでしょ。姉さんもあなたを愛しているわ」
今までこらえていたことを吐き出すようにマリーは言った。
「姉さんがなぜ結婚しなかったか知っている」
彼女はコーヒカップ越しに上目遣いに高島をみた。
「姉さんは同時に二人の男性を好きになったの。どちらも好きだったから、ひとりだけを選ぶことができなかったの」
マリーは高島の表情をうかがいながらしゃべった。
ブランシュは、小学校の同僚教師の恋人がいたが、しばらくしてナンシー大学の学生とも愛し合う仲になった。ブランシュは二人の恋人を同時にもち、どちらも愛した。が、それはながく続かなかった。同僚教師は、ライバルの存在を知って彼女をなじり、別の女性と結婚した。年下の学生は、ブランシュとの結婚を望んだが、彼女はなぜか結婚しなかった。学生は卒業と同時に町を去り、ブランシュは結婚した元の恋人と少しの間よりが戻ったが、それもすぐに終わった。
「姉さんは、恋に贅沢な人なのよ。その後も姉さんを愛する男性は現れたけれど、あの人は結婚しなかったのよ」
「なぜ」
「姉さんは“恋は恋の虚しさを教える”と言っていたわ。私は姉さんのような生き方をしないわ」」
黙っている高島に、彼女は挑むように言ってから、急に声の調子を変えた。
「クリスマスには高島さんにプレゼントします」
マリーはそれだけ言うと部屋から出て行った。軒先の巣から身をひるがえして飛び去る燕のようだった。マリーがやってくると落ち着かないのに、帰ってしまうとものたりなかった。
ひとりになると、マリーが話したブランシュのことが、油っこいものを食べた後のように胃の中に残った。今まで考えていたブランシュ像が、急に彼のなかで不透明なものになった。彼女の清楚で知的なイメージと、同時にふたりの男性を愛する奔放さが結びつかなかった。
翌日、かねてからポップ教授に頼まれていた教授の「森林のテクノロジー」の本の口絵を持っていった。水彩画で松を描いた。自分でも快心の作だったが、教授の喜びようはおおげさなくらいだった。お礼に夕食をご馳走するという。
「マドモアゼル・ブランシュ・ユッソンも呼ぼう。男ふたりの食事は味気ないからね」
ブランシュと三人で食事をするのは、家庭教師として紹介された日以来二回目だった。
しかし教授は、時々ブランシュと食事をしているらしく、会話からそのことが察せられた。高島は、二人の逢瀬の口実に使われたのだと気付いたが、教授の饒舌なはしゃぎぶりをみると腹もたたなかった。
ブランシュもふだんよりよく笑った。こんなに陽気な彼女をみるのは初めてだった。高島は、昨日のマリーの話を思い出し、ブランシュの笑顔の下に隠されているもうひとつの顔を想像した。むいてもむいても新しい鱗茎のある百合根のように思えた。
同級生カロの意外な告白
部屋にかえると、カロからのメモがドアのあいだにはさまれていた。
学校はこの間から冬休みに入っていた。寮生たちの大半は、クリスマス休暇を故郷ですごすため帰郷しているはずだった。カロも郷里のクロワに帰っているものばかりと思っていた。メモには、明日、一緒に食事がしたいと走り書きがしてあった。
レストランに行くと、いつもは時間にだらしないカロが、先に来ていた。カロはなかなか本題に入らず、自然科学のフリッシュ教授が高島に植物の細密図を依頼したことが、生徒の間で話題になっているという話だった。
「教授が生徒に教材資料を頼むなんて、森林学校44年の歴史始まって以来のことじゃないか。とてもすばらしい」
カロはしきりに持ち上げた。
高島は、何か頼みごとされるなと覚悟を決めてから切り出した。予感は的中した。
「高島さんはユッソン家の人達と親しいでしょう。マリーとも親しいですか」
カロは、半分言い渋っている。そんなところはまだ20歳の青年だ。
「話はするけど・・・」
「彼女には恋人いる?」
「そんなことまでは、知らない」
高島は、マリーが部屋にきたことはいわなかった。カロがマリーに恋しているとは意外だった。そのことを半ばからかっていうとカロは猛然と反論した。
「彼女を思っているのは、僕だけじゃない。マリーの弾くショパンに感動して、彼女の顔をみたこともない一年生までが憧れをいだいています。寄宿舎のベッドに、夜、マリーが弾くピアノの調べが流れてくるのです。たまらなく魅惑的ですよ。勿論、彼女自身も美人だ。学校中のマドンナといっていいかもしれない」
カロは勢いを得てしゃべり続けた。
あの気まぐれな娘がそんなに森林学校の生徒たちを魅了しているとは意外だった。学生たちの何人かは、手紙を書いて振られているという。
「僕は1回、手紙をだしたのです。でも返事はありませんでした。高島さん、あなたに伝言をお願いしたいのです。クリスマスのプレゼントを渡したいから、カフェ・エクセルまで来てほしいと言ってほしいのです。あなたの友人だといえば彼女も安心するでしょう」
カロは必死だった。恋に夢中の男というのは、どこかまぬけな感じがするものだった。農業科目を省いて、16点満点中14点、15点をとっている森林学校の秀才は、今はただの町娘に焦がれている凡庸な若者にすぎなかった。
「そりゃ、言うだけならいってみるが・・・こういうことは他人に頼むのは女の軽蔑を招くんじゃないかなぁ」
高島は、マリーは行かないだろうと思った。だから予め、カロに覚悟をもたせるためだった。
「実は手紙も出してあるんです。カフェ・エクセルで待つからと」
「もし彼女が来ないと、どうするつもりだね」
「彼女には恋人がいるんですか」
「いや、そんなことは知らない。もしものことだよ」
「あきらめます。故郷のクロワで探します」
「彼女のどこがいいんだね。なんだか我がままそうじゃないか」
「彼女のすべてです。我がままなところも含めて。高島さん、ひとを愛するというのはその人の存在すべてを認めることでしょう」
高島は、自分より15歳も年下の若者に恋について教えられていることにおかしくなった。カロが寮に残っていた理由がのみこめた。一瞬、ボップ教授がブランシュを見つめていた目をカロの上に重ねた。
ユッソン家に用事を作って尋ねると、マリーが出てきた。
「よかった。あなたに伝言をたのまれてきたんです」
「伝言」
マリーはありありと落胆の表情をした。森林学校のカロからの伝言を伝えると
「なんだ、そんなことですの」
「彼は私の友人です」
「高島さんの友人だから好きになれとおっしゃるの。あんな赤ら顔の小猿みたいな人を」
マリーは、紙を破るような言い方だった。
「じゃ、あなたの口からそれを言ってやってください。そうしなければ、カロはいつまでも待ち続けるでしょうから」
「よけいな愛は重すぎます」
「ひとに対して傲慢だと、いつか自分もそのような目にあいますよ」
「もうあっています。知っていてしらないふりをするのも傲慢だと思いますわ」
マリーはそういうと、二階へあがっていった。しばらくしてピアノの強い旋律が聞えた。
「あら、高島さん、そんなところでどうなさったの。さぁ入ってくださいな」
ユッソン未亡人は突っ立っている高島をうながした。それから二階のピアノに耳を傾け、
「あの娘、またクロエッツエルソナタを弾いているわ」と二階をみあげた。
高島は、その足で寮のカロを訪ねた。カロは、高島の表情ですべてを理解した。そしてその日の汽車でクロワに帰っていった。
昼間食べた油ものが、まだ胃の中に水銀のように沈んでいた。外気は、寒さを通り越して痛い。
高島は前かがみになればかえって寒さが身にしみるので、なるべく胸をはって大股で歩いた。マリーが言った『知っていて知らないふりをするのも傲慢』といった言葉を反芻していた。自分の予期しない方向に連れ去られていきそうな気がした。
「あと1年ちょっとで日本に帰れる」
彼は自分を元気付けるようにつぶやいた。少しでも風をよけるために壁に沿って歩いた。市場の壁に目をとめたのは「Japone(ジャポネ)」というスペルが目に入ったからだった。
黄色い丸顔に糸ミミズのような目が描いてあった。ジャポネの文字はその似顔絵のしたに書き込まれていた。高島の頭は一瞬空白になり、次に全身がこわばっていった。背筋を一匹の蛇が横切った。
その場から一刻も早く逃げたかったのに、彼は落書きの前から動けなかった。高島はとっさに左右をみて、人が通らないのを確かめてから、巻いていたマフラーを取ると、それで落書きを消した。白墨で描いてあったので、消すのは簡単だった。
高島は、追われるように立ち去った。途中でマフラーは捨てた。噴き出た汗が冷たくした。頭の中で、マリーの弾いていたピアノ曲が割れるように鳴っていた。
子供の落書きにこのようにうちのめされたこと自体がまんならなかった。カロのこともマリーのことも消し飛んでしまった。
ジャポニスムの流行でヨーロッパに渡った大量の文様型押紙
翌日、ヴィクトル・プルーヴェが尋ねてこなかったら、高島はもっとおちこんでいたところだった。
プルーヴェはクリスマス休暇でパリから帰ってきたのだった。パリで買ってきた日本の品物を高島に鑑定してもらうという口実でやってきたのだった。
プルーヴェが持ってきたのは、歌麿と栄泉の美人画と広重の“五十三次”の数点、他に柿渋をひいた織物の文様型押紙だった。型紙はゆうに百枚近くあった(現在、孫のクロード・プルーヴェ氏蔵)
「よくこんな物を手にいれましたね」
「この型押紙は、とても精巧にできています。日本の職人はすごい腕をもっている。ひとつひとつ小刀でこの文様を切り抜いているのですから」
プルーヴェは、萩の図柄の型押紙を宙にすかしてみせた。
「これはどんな物につかうのですか」
プルーヴェの質問に、高島はこの大きさからすると織物の文様型押しに使うのだろうと答えた。今度は高島が、こんな型紙を買って何に使うつもりかと尋ねる番だった。
「陶器にもガラスにも使えると思います。この文様をひとつだけ大きく扱うこともできるし、連続しても使える。まだガレさんには見せていませんが、きっとあの人は”掘り出し物“だと喜ぶと思いますよ。あの人に見せるまえに高島さんに説明を聞いておきたかったのです」
三十になったばかりだというのに、すでに頭がうすくなりかけているプルーヴェは、得々と説明する。話の端々にガレの名前がとびだした。
「あなたも日本のものを集めていらっしゃるとはね。プルーヴェさんの作品には、日本美術の片鱗もないじゃありませんか」
高島は、プルーヴェの人物画や彫刻を見ていたので不思議だった。
「あのう、高島さんを目の前において言うのはなんですが、私は日本美術にいくつかの疑問点を持っているんです。高島さん、あなたは何も見ないで絵を描かれますよね」
「ええ、私の頭の中にすでにありますから」
「確かに高島さんは、花を見ないで描かれる。いや、それは“花らしい花”というべきかもしれません。絵をえがくことは、何も現実のものをそっくり描くことではないことを私も知っています。しかし、高島さんの描かれた花は、なにか花とはちがっているもので、その違いは、外見の違いではなくて、それが生まれてくる中身から違うように私にはおもえるのです。私は日本美術の素晴らしさは充分認めます。しかしカミーユ・マルタンのように手放しで日本画を真似ようとするのには抵抗をかんじます。我々は所詮、フランス人であって日本人ではないのです。民族の歴史や環境もこんなに違う。中身が違うのに単に日本画を真似るのは無意味なことだと思うのです」
プルーヴェは、高島の気分を害しないように気遣いながらいった。
「私も同感です。私はフランスにやってきたのですから、やはり西洋美術を学びたいと思いました。でも、油絵を描くことをとめられましたよ。それを言ったのは、カミーユ・マルタンですが・・」
高島はマルタンのために弁護した。
「誤解しないで下さい。日本美術を私は否定しているのではないのです。日本美術の素晴らしさを知るからこそ、この浮世絵を買ってきたのですから。ただ私は、日本芸術の精神を自分の作品の中にもいかしたいと思っていますが、真似ることはしたくないといっているのです。また、高島さんが日本人だから日本画を描かれるというのは、自然なことだと思います」
高島はプルーヴェが率直に日本美術への疑問を口にしたことで、かえって彼を信頼するようになる。日本美術の外側だけを真似た“日本風”という作品に、高島自身がうんざりしていたからだった。
「高島さん、この型押紙をみてください。この作者は、好きな菊の花だけをそのまま文様にしたのではなく、それを様式化しているのです。この様式美に私はひかれます。この型押紙をみていると、なにか非常にまじめな人がこれを一生懸命作った、という感じが伝わってくるのです」
「真面目さは、日本人の間で尊ばれる要素ですよ」
「これをみていて、日本人は小さな世界の中に感情をこめるのが得意だと気付いたのです。細部にこだわるとき、そこに生き生きとした効果を生み出す。ほら、御覧なさい。歌麿の美人画の着物の柄のこまかさ、美人の持つパイプにも文様が入っている。それが作品の美しさを深めている」
プルーヴェは、型押紙を順に床の上に並べていき、黒のレースのように浮き出た文様に夢みるように溜息をついた。
「高島さんの作品にも、これらの型押紙と同じ省略と大胆さがありますね。花の雄しべや雌しべは細かく描くのに、花弁はひと筆で大胆に描いている。省略と緻密さのバランスがみごとなのだ。二つの間の緊張関係といってもいい。あなたは、マルタンが言うように日本画を深めていかれるべきです」
プルーヴェは腕を組み、型押紙の上に視線を落としたまま言った。高島も、床一面に広げられた型押紙をみつめて大きくうなずいた。
高島はなぜ油絵を描かなかったのか?
後に高島は、ナンシーで西洋絵画を勉強しなかった理由を次のように言っている。
「(ナンシーの芸術家に)油絵を教えろといふと其れは心得ちがいだ。私が教えても私ほど画けない。一方は破壊する。どっちもつかぬものになる。日本画をやれ、我々は大いに歓迎すると云ふです。皆に話さう云うです。終に画に対する観念ではなくて左様いふ所からして書かなかった」
(高島北海の山水画談(ニ))
ナンシー滞在中、高島は自分が日本人であることをいやがうえにもしらされる。
「画も他の事物と同じく其国々に習慣と遺伝がある。私は東洋人である以上は、東洋の遺伝と習慣とで発達した画を益々改良した方がよかろう」
(「東洋画に就いて」美術新報 明治36年10月号)
ひとは、異国に身をおいたとき、それまで意識しなかった自分の国や人種のことをかんがえるようになる。ナンシーの人達も高島を東洋人として別格にみていた。
しかしナンシー人の中には、高島が東洋人であることを意識せず、同じ人間としてのみみる人もいた。マリー・ユッソンだった。
クリスマスにプレゼントをするといっていたマリーは、カローの一件があって高島の部屋にはやってこなかった。
彼女がやってきたのは、新しい年が明けてからだった。
高島が、フリッシュ教授から植物細密画を頼まれ、その参考資料を両手にかかえて帰ってくると、廊下に見覚えのある白のモヘアのストールを頭からかぶったマリーが立っていた。マリーは緊張のために怒ったような顔をしていた。彼女は、自分の感情をもてあまして自分を切り刻んでいるようだった。
「すみません。長く待ちましたか」
高島は、会う約束もしていないのに、彼女が部屋の前で立っていたことであやまった。部屋に入るなり、マリーの不満は爆発した。
「高島さん、どうしてクリスマスにも新年のパーティにも家にいらっしゃらなかったの。カローさんのことがあったから」
「クリスマスは、ビエネールさんの家に招かれていたのです。新年は、あなたもしっているでしょう、クルースさんのところに行って、その帰りに画家のカミーユ・マルタンのところで画家仲間で集まってワイワイやっていたのです」
高島は、マリーの怒りを沈めるためにこまかく説明しながら、彼女の怒りの原因を探ろうとした。
「まるで私を避けていらっしゃるみたい。姉さんとはいつもひそひそ話をして笑ってらっしゃるくせに」
「ブランシュさんは、私の先生ですから」
「そんなにフランス語が上達しているのに、なぜ家庭教師が必要なんですか」
マリーは早口でまくしたてた。
「僕にあなたを避けなければならない理由なんてありません」
相手の不躾さに高島はピシリと言い返した。マリーは黙った。沈黙は海峡の潮のように多くのものを押し流した。
「わたし、あなたが好きです。好きなのにあなたは・・・」
マリーの言葉は涙に流された。涙で彼女の目が膨張したようだった。それからとどめもなく流れ落ちた。
高島は、頭の後ろから殴られたようだった。彼はあわてた。ポケットからハンカチをとりだしたが、もみ紙みたいになっていたので、引き出しから新しいハンカチを出し、マリーの涙をぬぐおうとした。それを待っていたように彼女は、高島にしがみつき、今度は声をだして泣き出した。泣くことが快感でもあるかのように、マリーは泣き続けた。高島は、夕立がすぎるのを待つ旅人のように彼女を抱きしめていた。毛糸のセーターを通してマリーの体温が染み出ていた。吉野ヒノキのようだと彼は思った。雨水があたると水のようになってすべる削った吉野ヒノキの木肌をおもった。マリーの体は弾力にみちていた。高島の体の奥で蠢くものがあった。が、次の瞬間、彼は日本人である自分にたちかえった。
高島は、やさしくマリーの体をはずし、彼女の眼を覗き込み、それから唇を重ねた。白いモクレンの花びらを口に含んだようだった。
「マリー、私もあなたが好きです」
「姉さんとどっちがすきですか」
「好きさのニュアンスは違います。ブランシュさんは、異性と言うよりは先輩のような、姉のような存在です。ブランシュさんを女性として意識しないのです」
高島は、マリーを安心させるためにふだんブランシュに思っている中性的なイメージを何十倍にも膨らませて説明した。
「でも姉さんは、高島さんを男性として愛しています」
「どうしてそんなことがわかるのです」
「姉妹ですから。そして私もあなたを愛しているから。ライバルのことはわかるのです」
「僕は日本人です」
「それがどうしたというのですか」
「帰らなければならない身なのです。わかりますか」
マリーは静かに視線を床に落とした。それからすっきりと高島を見据えて言った。
「私を日本に連れていってください」
「日本へ、あなたが。お母さんやブランシュさんは反対されるでしょう」
「・・・・・」
「みすみすあなたを不幸にすることが分っているのに、僕にはとてもそんなことできません」
「あなただってはるばる言葉や食べ物の違うフランスにやってきたではありませんか」
「僕は、わずか3年間だから、それができたのです」
その言葉をきくと、マリーは壁に顔を伏せて泣いた。高島はマリーを抱きしめ、再び唇を重ねた。モクレンの花びらは、熱のため乾いていた。
マリーが帰って行った後も彼女が残していった香りの中で高島はぼんやりしていた。選択にまちがいがなかったと自分に言い聞かせながら、虚しさとも哀しみともつかぬものが葉擦れのように彼の頭の中でかすかな音を立て続けていた。モクレンの香りは消え、舌の先に金属的な匂いがいつまでも残っていた。
その年、1887年、ピエール・ロティは長崎でめぐりあったお七とのことを「お菊さん」という小説にかいて発表した。折からのジャポニスムで、「お菊さん」は評判となった。