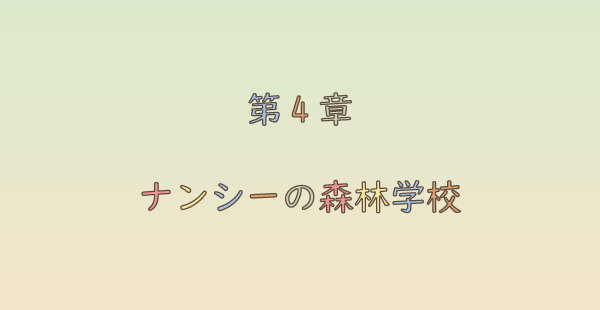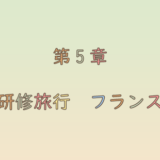超エリートの国立森林学校
国立森林学校は、ジラルド通り14番地にある。スタニスラス広場から歩いて4分足らずの小さな通りに面している。鉄格子の校門に「ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS」の金文字が浮かびあがっている。もしこの金文字を見落としたら、そこが学校とわからず通りすごしてしまうほど校門は小さい。両並びも向かいも普通のアパルトマンで、通りはひっそりとしている。
校門を入ると、レンガ色の屋根の3階建ての館がある。その斜め後ろに中庭がひろがる。
中庭に面して、大時計のある3階建ての校舎と、同じ高さのクリーム色の校舎、その一角に普仏戦争で戦死した生徒名が刻まれている。なぜ戦没碑があるのかは、この学校の設立の背景やカリキュラムをみれば分かる。
ナンシー国立林業専門学校、それが学校の正式名称である。1827年にバルナール・ロレンツによって創設されたフランス最初の森林学校で、今もある。外観は高島の留学当時のままである。
学校が創設された背景には、フランスの森林への危機感があった。
フランスの森林は、フランス革命と帝政期の戦争の混乱で荒廃していた。木材が石炭に交代するのは1850年以後であるから、それまでは工場、家庭用の貴重な燃料であった。政府は,燃料源としての森林保全とその育成のため、1827年に森林法を制定すると共に、森林官を養成するためボージュ山脈に近いナンシーに学校を創設した。
しかし森林に関しては、“森の国”ドイツが先進国だった。ドイツにはすでに1807年に、アシャッフェンブルグとフライブルグに学校ができていた。初代校長のベルナール・ロレンツはドイツの学校で学び、ナンシー森林学校を創設し、森林法を制定する。
高島がドイツを選ばずフランスの学校を選んだことについては、農商務省の人脈が関係している。
なぜフランスの森林学校に留学したのか?
明治4年、フランスからジョルジュ・ブスケ(1846~1937)という一人の法律顧問がやってくる。ブスケは、明治寮、のちの司法省学校で教育をおこなうのが目的だったが、来日の際フランスの森林法に関する資料を持参していた。それをみた農商務省の初代森林局長、桜井勉(1843~1931)は、日本にも森林法を制定しようと考えた。森林は明治政府が推進する殖産興業の中で大きな部分を占めていたからである。
桜井は大隈重信派だった。その大隈が政局を追われると、傘下の彼も失脚する。次に農商務省で力をふるうのは、品川弥太郎である。品川は桜井を追い出すと、自分の息のかかった武井守正(1842~1926)を山林局長にすえる。
播州姫路藩士であった武井は、後に明治銀行や東京火災保険、帝国火災保険、日本商業銀行を創立した人物であるから、会計学には通じていた。が、山林学は全くの素人であった。ただ彼は、森林が明治政府にとって重要な財源であることを感じていた。特に皇室の財源は森林だった。森林を唯一の財源としなければいけないほど、明治政府はさしたる財源をもっていなかった。彼も桜井と同じように森林法の制定を必要と感じ、法案を練り直し、明治15年、森林法案を左大臣有栖川宮識仁親王に提出する。この法案は、フランスの森林法を真似たものだった。
ところが、明治政府は管理費用が捻出できないとして却下する。しかし武井はあきらめなかった。
1884年、武井はイギリスのエジンバラ万国博覧会の事務官長として海外出張のチャンスをつかむと、これを利用してヨーロッパ諸国の進んだ森林制度を視察し、再度、森林法を練り直そうと考える。
さらにしかるべき自分の部下をフランスに残し、フランスの森林学校で森林法を勉強させようと計画する。
武井が白羽の矢をたてたのが、高島得三だった。高島は、全国の主な森林を調査して,森林学を実地に学んでいる。なによりもフランシス・コワニエに習ってフランス語ができる。そのうえ、高島は長州人で外務卿の井上馨からも目をかけられていた。播州姫路藩士であった武井にとって、長州人とのつながりを強固にすることは、権謀術数の渦まくなかで生き残るには必要なことだった。高島は年齢35歳と若くはなかったが、まだ独身で身軽だった。仕事熱心なことは、全国の森林調査の報告書が実証していた。絵師級の腕を持っていることも、武井には好ましかった。武井は、のちに「日本美術協会」の後援者になるくらい絵画に造詣が深かった。武井にとって、部下の高島は相性のあう男だった。
高島のナンシー森林学校留学には、森林法制定という武井の夢がかかっていた。
しかし高島にだけ自分の夢を託していなかった。夢を実現するため、武井はいくつもの網をはっていた。彼は高島がナンシー森林学校から帰国すると、部下の志賀泰山をドイツに留学させる。武井は、ヨーロッパ視察中に森林学ではドイツが先進国であることを知ったからである。
いつの間にかライバルをつくっていた高島
明治17, 18年頃には、政府の目はフランスよりドイツに向けられていた。普仏戦争でドイツがフランスに勝ったことや伊藤博文がドイツから帰国し、ドイツ憲法をもとに大日本帝国憲法の法案を練っていた時であったからである。
当時、明治政府がドイツ志向型であったことは、高島が留学した明治18年の文部省の海外留学生の記録によっても明らかである。オーストリア2名、アメリカ1名、フランス1名の中で、ドイツ留学生は圧倒的に多く16名である。
ちなみに、このフランス留学生は高島ではなく、産婦人科の勉強のためにリヨン大学に留学した梅津次郎である。高島の名前がないのは、彼がパリで留学の手続きをとったからであろう。
武井守正は、これからはドイツの時代だということを知っていた。だから高島、志賀という2羽の鷹を2つの国の野に放ち、どちらが大きな獲物をくわえて帰ってくるかを試したのだった。
志賀泰山がいつの間にか自分のライバルになっていることを知らない高島は、上司の夢を自分が担っていることに自負と誇りを感じていた。しかし高島がドイツではなくフランスの森林学校に学んだことが、彼の役人生活を大きく左右することになる。
国立森林学校の授業料はフランス役人の1年分の給料に相当
高島は野心と希望の帆をいっぱいにはって、森林学校の事務室を探していた。
事務室はレンガ色の屋根の館の1階にあった。用件をいうと、係りの者が校長室に案内してくれた。
「待ってましたよ」
ピュートン教授は、老眼鏡をずらせて高島をみた。この時、フランソワ・アルフレッド・ピュートン校長(1832~1893)は53歳だったが、実際より老けてみえた。高島は「日本森林今報」に「ピュートン校長は61歳・・」と間違ってかいているのも、老けていたからだろう。若い頃は黄金色に輝いていた髭は、今は冬枯れの野原のように少ない。しかしそのブルーの目は、老いた山羊のように柔和な光をたたえていた。
校長は立ち上がって東洋からはるばるやってきた留学生の手を両手で包み込んだ。
高島は、昨年エジンバラで開かれた万国森林博の帰り上司の武井と共に校長に会っていたが、あの時は連日、何人もの人に紹介されていたので記憶が薄かった。
校長の机には、パリの日本大使館の蜂須賀公使からの手紙が置かれていた。
校長は高島に椅子をすすめると改めて質問をした。
「留学の目的は」
高島は4ケ月前に留学書類に書いたのと同じことを繰り返した。
「森林の保全と育成を学び、帰国して森林法の制定に役立たせたいと思います」
「しっかり勉強しなさい。あなたは日本で実際に森林業務に携わっていたのですね、それなら吸収が早い」
校長は、日本でどんな森林業務についていたのかを尋ねた。
高島が、官有調査のため全国を歩きまわって地質の地図や植物帯報告書を作成したというと、校長はおやっと言う風に首をかしげた。
高島はフランス語の発音が悪いので通じなかったのかと不安になる。
しかし校長の方は、しばらく考えてまぁいいやといった微笑をして、それ以上の質問はせず、言葉は大丈夫かと別の質問に切り替えた。
「フランス語はむずかしい」というと、校長は首をふった。
「あなたはこうして今、しゃべっているではありませんか」
校長は高島の顔を覗き込んで微笑した。
そしてもう一度「さぁしっかり勉強しなさい」とつけくわえ、5冊の本を高島に差し出した。ピュートン校長のサインのある「フランス森林法律」「フランス森林法律提要」「フランス森林保護法」「森林学校事務章程」「森林学校教則」だった。
校長は机の上の鈴を鳴らした。
しばらくたってひとりのいかつい男があらわれた。きびきびした動作、豊かな栗毛のカイゼル髭、西洋の甲冑の上からフロッグコートを着ているようである。1メートル80センチの高島より3, 4センチ高い。
校長は、担任のルシアン・ボップ教授(1834~1907)だと紹介した。留学生には教授が一人ずつつくことになっていることも説明した。
51歳のボップ教授の手は、いかつい体格には似合わず柔らかくあたたかかった。
教授は、入学手続きをとるから来て欲しいといった。案内されたのは、会議室だった。
教授は書類を円テーブルに置くと、まず1年分の授業料を事務室に行って支払ってくるようにと言った。すべてはそれからだといわんばかりだった。
高島は、1500フランと書かれた書類をもって事務室に行く。事務員はあらかじめ聞いていたのか、書類と金を出すと、新入生をゴロリと見て、札束を数え始めた。
百フラン札を数えながら、右から左へと移した。それはイライラするほどゆっくりしていた。事務員はまるで札を数えるのを楽しんでいるようだった。せっかちな高島は、それを見ながら貧乏ゆすりをして待った。ボップ教授を待たしているのも気になった。
事務員は、15枚の百フラン札を数え終わると、もう一度最初からやりなおした。それは事務員の1年分の給料ほどの高額だった。
1880年代の最下層の公務員の給料は年間1千フランだった。労働者の年収はさらに低く500フラン程度だった。デュマの「椿姫」に「年10万フランも無駄遣いをしている」とあるのが、どれほど大金であるかが想像できる。
1500フランの授業料は、日本円にすると3百円。この年の東京帝国大学の月謝が1円から1円50銭に値上がりして話題になっている。3百円の授業料は、破格の高額だった。
森林学校は、学力、財力共に選ばれた者のエリート校だった。この学校に入るためには、フランス人の場合、リセ卒業後、バカロレア(全国一斉大学入試試験)に合格し、2年間特別の勉強をつみ、ようやく受験の資格をもつ。一般の大学に行く者は、バカロレアに合格すればフランスのどの大学にも自由に入学できる。
森林学校に入学すると、生徒は2年間寮生活をする。「いかなる生徒も、寮に入ることが義務つけられている。部屋は2人1部屋で、その割付は、担任教授が行う」のが規則だった。
そのかわり卒業すると、森林開拓、森林保護のエリート技師としてフランス全土に派遣される。この場合、在学中の成績によって赴任地が決まる。成績の優秀な者は、都会にも近いいい森林地区の官舎に住むことができるが、成績の悪かった者は、植民地のマダガスカル島やアフリカに配属される。将来がかかっているので、生徒たちは必死で勉強した。高島が留学した頃の生徒入学数は、20人。上級生、下級生あわせてフランス人生徒は40人、留学生が毎年10人程度いるので、全校生徒60人足らずのエリート校である。
フランス人にとって入学はむずかしいが、留学生の場合は国の推薦があれば無試験で入学できた。ドイツの森林学校に定評があるのに、なぜフランスを選ぶのかは、その国とフランスとの友好関係によった。ベルギー人やスイス人はフランスに留学した。
もうひとつフランス留学が好まれたのは、風土的にドイツよりフランスの方が変化に富んでいたことがある。広葉樹と針葉樹の森林をもつフランスの森林学校の方が自国の森林事情に合わせやすいということがあげられる。イメージ的にも、ドイツよりフランスを選ぶ生徒が多かったことも事実だ。
授業に軍事演習がある理由
ナンシー森林学校は学校というより塾といったほうがあたっている。ここでは徹底的に技術教育、実地教育が行われた。1週間が教室での授業、次の1週間が実地研修、次の週にリポートをまとめて提出するという繰り返しの授業である。
高島が授業料を払って戻ってくると、ボップ教授は待っていたかのように次の書類を彼の前に並べた。「書類の記入が終わったら、2階の廊下の突き当たりの部屋にいるから」と教授は出て行った。
履歴書の用紙だった。今度もまたパリで書いたことと同じことを書けばいいのだと思うと、急に楽になり、部屋の様子を観察する余裕がでてきた。
壁には歴代の校長の肖像画がかかっていた。初代校長のベルナール・ロレンツは、正月のにらみ鯛の尾のような立派な髭の男だった。胸につけた勲章は、すずなりの果実のようで重たそうだ。肖像画の下に1824~1830と書かれているのは、在任期間だろう。5代目の現校長ピュートンは、写真である。実際よりいかめしく写っている。
もう一方の壁には、フランス全土の地図が貼られ、正面には金縁の額に銅版画かかげられている。近づいてみると、中世の頃の戦争画だった。
気の遠くなるような細密さで、銃をつかもうとして事切れる兵士や、腹わたを出して死んでいる馬、槍を高々とかかげて果敢につき進む兵士、重なり合って死んでいる兵士が熱狂的な情熱で描かれている。悲惨な戦場が描かれているにもかかわらず、血の匂いのしない作品だった。絵の作者は、記憶の引き出しから引っ張りだして、嬉々として記憶をなぞって砂塵の舞い上がる戦場画を描いていたのだろうか、そこには兵士と馬の死を同じように生物の死としてとらえた非情なほど冷徹な眼があった。無邪気ともいえるほど、その戦場画はあっけらかんとしていた。
しかし高島の視線は、戦場の奥へ奥へと吸い込まれていく。その瞬間、15歳の時にみた腑分けの光景がひろがった。
湿ったよどんだ空気が小部屋にたちこめていた。中央の木の台には、死罪となった囚人の屍体が布もかぶせられず無造作に置かれていた。漢方医の父の命令で、蘭学医の腑分けを見学してくるようにといわれてきたのだった。見学生は12, 3人もいた。見回すと高島が最年少だった。
蘭学医が、屍体にメスをいれた。白灰色の肉の上に、一本の赤い絹糸がひかれた。蘭学医はもう一度、同じところをメスでなぞった。今度は、白蝋からいくつもの赤いビーズ玉がこぼれた。
蘭学医が腹を裂いた。その瞬間、血の匂いが立ち上った。
「よくご覧なさい」
見学者たちは、屍体のそばに吸い寄せられた。高島はみた。
赤い臓物が一部のすき間もなく、実に順序良くぎっしりとつまっていた。それは豊かな果物籠のようだった。ひとつひとつの果実は、よく熟していた。その人間は死んでしまっているのに、それらの臓物はまだ熟することをやめず、ぬめって光ながら息づいていた。
「まだ内蔵は生きている」
そう叫ぼうとした瞬間、高島は気を失った。
高島は、あたりに血の匂いをかいだような気がして、はじかれたように銅版画から離れた。視線は、すでに中庭の噴水に注がれていたが、網膜には血のりがついていた。それはしばらく消えなかった。高島は肩で息をして、呼吸を整えた。
銅版画には、ジャック・カロというサインが入っていた。会議室になぜこのような銅版画が飾ってあるのかわからなかった。あとになってカロは、ナンシーの人々が誇りに思う郷土の画家だとわかった。
彼はようやく自分の仕事を思い出し、事務員がおいていったインク壷にペンをつけた。
職業欄で、農商務省と書き、6等属をどう書くのか迷って、技師と書いた。しかしその時高島は技師補にもなっていなかった。
ボップ教授は、高島が呼びにいくまえに現れた。教授はていねいに書類に目を通すと、明日からの授業の日程表を渡した。最初の一行をみて、高島は思わず書類に目をちかづけた。
起床 6時
学習あるいは乗馬 6時半~7時半
休憩 7時半~8時
授業 8時半~11時
昼食 11時~12時10分
軍隊演習あるいはグラフィックの授業 12時15分~1時半
休憩 1時半~2時
授業あるいは自習 2時~4時半
乗馬あるいは授業 または自習 4時半~6時
夕食、後自由行動 6時~10時
消灯 10時15分
カリキュラムの中でひときわ「軍事演習」の文字が目につく。国立森林学校は、優秀な森林官を養成する学校であると同時に優れた軍人を育成する訓練所であった。陸続きのヨーロッパでは、森は国境の役目をはたしていた。ひとたび戦争がおこれば、国の境界線を知っている森林官の案内が必要となる。その時のために森林官は乗馬ができ、軍事に明るくないといけないのだった。当時の森林営林局長は、予備の陸軍大臣の位をもっていた。日本の森林学にはない考えだった。
寮生と同じ館に教授一家も住む
高島がいつまでもカリキュラムをみているので、教授がいった。
「寝坊をしないように。あなたは日本から選ばれてきたのでしょう、選ばれた者はふつうの人以上に努力しなければいけません」
教授は初めて微笑した。目じりに小じわがよって、いかめしい顔が崩れた。
教授は高島を連れて、校内を案内した。案内しながら学校の歴史を語った。
赤レンガの屋根の建物が二つの校舎と違うのは、この建物が元公爵の館であるからだった。1階は事務室だが、2, 3階はピュートン校長一家の住まいになっていて、歴代校長は生徒と共に暮らすことになっていた。
時計台のある校舎は、1階が生徒のくつろげる娯楽室と会議室になっている。2階は教授室と教室。教授の人数は、助手1人を含めて全員で12人だった。
3階が学生の宿舎になっていた。授業は、フランス人学生と留学生組は別々に行われていた。しかしフランス学生組の授業で興味がある科目は、申し出をすれば授業を受けることができた。
フランス学生の下級生クラスは、地質学の授業をしていた。階段状になった教室で、20人の生徒は、足を組んだり、頬杖をついたり自由な姿勢で授業をうけている。教授は一方的に早いフランス語でまくしたてていた。高島は三分の一も聞き取れなかった。不安が雨雲のようにひろがり、体を重くした。
留学生のクラスでは、樹木につく害虫の講義だった。生徒たちは、フランス学生組よりずっとのびのびしていた。黒い髪の学生はいたが、顔をみると東洋人ではなかった。教授はルーマニアからの留学生だと言った。生徒たちから発せられるチーズと安いコロンの男の体臭が、かすかに高島の鼻を刺激した。
ボッブ教授は、時計台のある校舎をひと通り案内すると、中庭をはさんだ向かい側の校舎を指差して、1階が自然科学室で、そこには森で生息する動、植物の標本があるといった。図書館も1階で、2階は研究室、3階は教授の家族が住んでいると説明した。
「あの3階の端が、私の住居です。こまったことがあったらいつでも来なさい」
ボッブ教授は、白いカーテンのある窓を指差した。
教授の案内はそこで終わった。
「校舎の裏には、植物園があり、その横は動物園です。勉強に疲れたら散歩するのにいい環境です」
と、付け加え、懐中時計をみて、事務員に馬車の用意をさせるからホテルの荷物を取ってくるように言った。
やってきた事務員は、馬車の準備ができるまで寮の内部を案内するからといった。
寮室は二人部屋だったが、最近ルーマニアの学生が市内のアパルトマンに移ったので一人で使っていいと、事務員は得意になって説明した。
風呂なしの寮生活が始まる
寮の部屋は、入り口のところの両側に洗面所があり、その横に細長い洋服ダンスがあった。ドアを開くと八畳ばかりの明るい部屋に、木製のベッドと机、本箱が左右対称に置かれていた。左右の均衡を破るのは、左側にある暖炉だけだった。
机の上にはランプがあった。ランプには小さなアザミの模様がついていた。アザミはナンシー市のシンボルの花だとあとで知った。壁紙には、のうぜんかずらの花柄が使ってあったので、寮室というより少女の部屋の感じだった。35歳の男の部屋にしてはかわいすぎると思ったが、いかにもフランスだと高島は微笑した。
「トイレは?」
「各階のすみにあります」
「風呂は?」
「風呂?寮にはありません」
事務員が断ち切るようにいったので、高島はその後を聞きだせなかった。
「風呂がないのか」
そのことだけで、これからの寮生活がおもいやられた。19世紀末のフランス人には入浴するという習慣がなかった。当時のパリ人の平均入浴数は年2回という記録が残っている。習慣がなかったことと、入浴代が50サンチームと高かったのである。寮生は年何回か町の浴場に行くだけで、ふだんはシャワーをあび体をふくだけだった。
ジパングからの留学生を祝う歓迎パーティ
ホテルから荷物を運んでしまうと、夕食までの時間を部屋にいた。夕食の時、全校生徒に紹介されたときの挨拶を練習しておく必要があった。
夕食は、スタニスラス広場に近い学校の特約レストランですることになっていた。事務員が書いてくれた地図を持って6時少しまわってから寮をでた。スタニスラス広場の黄金の門は、黄昏の中できょう一日の最後の輝きを放っていた。
レストランは、いかにも学生相手の店らしく清潔な店だった。赤と白の格子のテーブルクロスが唯一の飾りになっていた。
壁には卒業生たちの送別パーティの写真が額に飾られていた。
ボップ教授が、同僚の教授とやってきた。すでに生徒たちは気の会った者同士でテーブルにつき、談笑している。ボップ教授は、自然科学のフリーシュ教授を高島に紹介し、3人は同じテーブルについた。
オードブルのアーティショーが大皿に盛られている。高島が、かねがねレストランでみて不思議に思っていたものだ。大きな抹茶色の松かさのような物で、辞書には朝鮮アザミと載っていたが、食べ方がわからないので遠慮していたものだった。
店に次々と生徒たちがやってきた。教授はおおかたの生徒が席についたころを見計らって高島を紹介した。
ジャポンからやってきたというと、生徒のひとりがすっとんきょうな声をあげた。
「ジパング」
その途端、笑い声がわきあがった。生徒のひとりが大声で厨房に向かって叫ぶ。
「ムッシュ、オリエントからきた新入生に乾杯のワインを」
生徒たちの間で今度は拍手がおこった。
レストランの親父が、ジパング、ジパングと歌いながら小脇にかかえたワインをおいていった。ワインのコルクが抜かれると、生徒たちは高島の存在を忘れておしゃべりに夢中になった。
ボップ教授は、アーティショーを皿に取り、皿のはしにソースをそえた。高島は教授のやり方を真似て、開いた松かさの一弁をとって、ソースをつけ、肉厚の固い葉を指でおした。白い果肉が飛び出した。味はサトイモを蒸した「衣かつぎ」のような淡白な味だった。しかし果肉は少ししか入っていないので、めんどうだった。花弁を全部取ってしまうと白い芯が残り、どうやらそれが本来食べるべき部分らしい。レモンのきいたソースの味ばかりが強く、お世辞にもうまいとはいえない。
その日のメインデッシュは、兎の肉料理だった。骨付きの肉をフォークとナイフを使って食べるのは、皿の上の小さな格闘技だった。レストランの親父が、ちらちらとみているのがわかると、高島は耳たぶに火がついた。
学生たちの食事はにぎやかだった。
食事があらかた終り、デザートのケーキがでてきた頃、二人の生徒がたちあがった。
「紳士、淑女のみなさん」
二人がもったいぶって口を揃えていった。
「女はいないよ」
誰かが野次ると、笑い声が熱風のようにあがった。二人が頭をかきながら頭をさげた。
「ジパングからはるばるやってきた我々の仲間のために、ぼくたちは歌います」
二人は「サクランボの実る頃」を歌いだした。
“サクランボの実る頃は、はしゃぎ屋のウグイスも冷やかし好きのツグミも皆浮かれ出す。美しい女たちは、すっかりのぼせあがり・・・”
二人は歌いながら、太っている学生が胸を持ち上げ、女の仕草を真似る。するともう一人が、樹木を計る輪尺で、デブの学生の尻や胸を測ろうとする。デブの方は、色ぽい仕草でそれをはねのけて笑わせる。学生たちは口笛を吹く。女の真似をする学生は調子にのって尻を振ってみせた。
高島は熱いものが不意に湧き出し、それが目もとのあたりであふれるのを必死で抗していた。二人の歌は、しだいに遠くなり、頭が温かい靄につつまれていった。気がつくと二人の歌は終わり、ボップ教授が立つように促していた。
高島は立ち上がって「ありがとう ありがとう」を繰り返した。
学生二人が歌った「サクランボの実る頃」は、パリを皮きりに全国に広がっていたその頃の流行歌だった。歌の作詞をしたジャン・バチスト・クレマンは、パリ・コミューンの幹部で、この歌にはパリ・コミューンの女子衛生隊員だった恋人への思い出に捧げられたものだった。クレマンは、恋の痛手や願望にパリ・コミューンの革命の挫折や理想をたくしていたので、政治的な意味合いをもっていた。それゆえに学生たちに愛唱された。
食事が終わっても、学生たちは席をたたず喋りつづけていた。どの学生ものびやかで屈託がない。21, 22歳の学生たちは、いっぱしの口調で政治や経済を語っていた。彼らは生きることに夢中な若者たちだった。35歳の高島からみると、弟と呼ぶにも若すぎた。明日からこの若者たちに混じって学ぶのかと思うと、自分が新緑のなかに一本だけ混じった古木のように思えた。
しかし彼はまた、若者たちとの年齢差によって競争しなくてもいいレースに参加した気楽さも感じていた。
レストランを出たのは、九時近かった。二時間近く夕食にかけていたことになる。そんなことは、兄の結婚式以来のことである。
4月15日水曜日は、長い一日だった。その一日もようやく終わった。高島は風呂にはいりたいと思いながら、フランス人がするように体をふいてからベッドにもぐりこんだ。
授業についていけない高島
翌朝、廊下を駆けていく足音で眼が醒めた。懐中時計をみると6時半だった。
六時起床、六時半から7時半まで乗馬か自習という時間割を思い出した。
空の一部が白み、夜の底がみえた。街頭に照らされたオレンジ色の輪が周囲をぼんやり浮き上がらせている。
ランプを点けた。シエードに十字架を二つ並べたナンシー市の紋、複十字が浮かびあがった。
高島は、午前中の授業の林業経済学の教科書を取り出した。最初のページの二行目から辞書が必要になり、彼は舌打ちをした。表紙のくたびれた仏和辞典をとった。
仏和辞典は、M・ヌジェンの仏英辞典を訳したもので、明治4年、好樹堂から発行されたものだった。単語はABC順で、日本語は縦組みでわずか440ページしかない。上海のアメリカンプレスビテリアン印刷所から発行されたもので、仏文標題は「NOVVEAU Dictinnaire Fancais-Japonais」。
高島が渡欧する明治17年までには、ヌージェンヌ著の「仏和辞典」の他に、慶応3年に「仏郎西塾語箋」明治4年に「法語階梯挿訳」、明治5年に「洋学指針仏学部」発行されているが、いずれも和とじの辞書である。
明治6年になると「仏和会話編」(陶慮著)、明治7年「仏語入門第一読法」(東京外国語学校発刊)、明治15年「仏語啓蒙」が出ているが、百ページ以内で、辞書というより仏語の手引きといった物であった。440ページもの辞書の体裁をもったものは、当時非常に少なかった。
高島は、辞書を片手に教科書を読んでいったが、辞書に載っていない専門用語が次々とでてきて、そのたびに舌打ちをしなければならなかった。彼は、仏仏辞典をひきながら、遅遅として進まないのにいら立った。懸念していたことが、遂に現実となったという感じだった。
一階の娯楽室兼食堂で、バケットとカフェオーレの簡単な朝食をすませた。生徒たちは昨日の夕食と大違いで、黙々と食べている。授業の教科書をもってきている者もいた。
小柄なギョット教授が入ってきた。イギリスからの留学生4人とベルギー人4人、ルーマニアの6人と高島の15人のクラスだった。
当時、イギリスには森林学校がなかったので、ドイツとフランスに留学生を送っていた。イギリス留学生は、半年間フランス語の特訓をうけてナンシー森林学校に入った。イギリスには、1887年に森林学校が創設されたので、高島が滞在した頃の生徒が、最後の留学生である。
ギョット教授は、留学生のためにゆっくりとしたフランス語で、フランスの森林事情を説明した。イギリス人のために、しばしば英語をはさんで講義したが、英語の分からない高島は、教授が黒板に書いたフランス語の全森林面積は、国土の15~16%の数字だけをノートにうつした。その横に彼は、日本の場合は66%と書き添えた。
高島は、講義の半分しか理解できなかったが、実際に森林業務に7年間たずさわっていたので、実務から得た知識をつなぎあわせて、わからないフランス語を補った。しかしわからない講義を3時間聞くことは苦行にちかかった。
法律を学ぶために留学した黒田清輝もフランス語にてこずる
高島がフランス語の授業に手を焼いている頃、パリでも同じようにフランス語と格闘している日本人がいた。黒田清輝である。
20歳の黒田は、法律を学ぶためにフランスに留学したのだが、法律学校に入学するためにフランス語を学ぶ必要があった。渡仏した前年3月から、彼はパリのアンスティチュウション・ゴファールという私塾に通っていた。黒田は17歳の時から日本でフランス語を学び、18歳のときには外国語学校フランス語科の入学試験にも合格し、かなりできたが、法律学校に入学するのは困難だった。黒田清輝が正式に法律学校に入学するのは、彼が22歳の時、渡仏3年目である。言葉は黒田にとっても高島にとっても厚い壁だった。
フランス語圏からきているベルギー人が質問した。しかし高島は、その質問の意味すらわからない。彼は禅僧のように姿勢を崩さず、机の上に両手をハの字において教授の口元を聾唖者のように読み取っていた。それは、教授を見すえ、今にも襲いかかろうとしているほど威圧的だった。極東からきた自分とあまり年齢の変わらない生徒から、たえず鋭い視線でみつめられることは、教える者と教えられる者の立場を逆転させるほどの緊張を孕んでいた。ギョット教授は、1日で高島の名前をおぼえた。
昼食の後は、フランス人学生組は軍事教練、高島らの留学生組はグラフィックの授業だった。
軍事教練は、中庭で行われたり、ナンシーの郊外で行われることもあった。軍事教練のモンチゴウ教授の号令が、校舎のすみずみまで矢のように飛んだ。それと同時に、玉じゃりの中庭を踏む生徒の軍靴が、波音のように響いた。陽が差し、彼らの鼻梁の美しさを浮き立たせている。中庭の噴水が風に散り、水しぶきが虹を作った。
高島は、神妙な表情で行進する学生たちを見ながら、心を弾ませてグラフィックの教室に急いだ。
グラフィックを辞書でひくと「図表」とある。これは絵を描くことと関係がある授業に違いない。自分の才を発揮する機会ができる。高島はうきうきしていた。
応用数学の知識のない高島が考え出した解決策
チェリー教授が入ってきた。
教授は小脇に白い厚手の用紙をもっていた。その白い用紙をみて、高島の胸は子供の頃に聞いた祭囃子のように高鳴った。
「今回の授業では、森の中の林道の位置の設計について学習します」
教授は、黒板に森の面積から林道を作る間隔を割り出す数式を書いた。
高島はあっけにとられた。
教授の書いた釣り針のように曲がった記号が何を意味するのか見当もつかない。このグラフィックの授業は、地形学に含まれる学問で、応用数学の知識を必要としたが、高島には皆無といっていいほど数学に関する知識がなかった。
そのうちに教授は、用紙を配りボージュの森の一部を例にとり、そこに林道を設計するように指示した。
生徒たちは、用紙に基盤の目を引き始めたが、隣のイギリス人がやっているのをただ眺めていた。
しばらくそうやって見ていたが、冷ややかな狂暴性がうまれ、それが野火のように広がっていった。もうどうでもいいや、という気持ちになった。
彼は用紙にペンでブナを描き始めた。ナンシーにくる途中、車窓からみたブナの林がすぐ浮かんだ。映像は次の映像をよびおこす。最初、灰色のぼんやりした塊であった林が、徐々に1本1本の樹となっていく。次に枝が見えてきた。
記憶をたぐりよせるように彼は、ブナの幹を描いていく。幹から枝へ、枝から梢へ、彼の視線は記憶をゆっくりなぞっていく。時々、ペンにインクをつける。しだいに彼は世界を占領していく。誰も入ってこられない彼だけの世界、そこでは彼は王であり、家来であった。高島は、もはやグラフィックの授業であることも、チェリー教授が黒板に書いて説明していることも耳にはいらない。彼は自分だけの世界で、ブナの枝から枝に飛び移ってさえずる小鳥だった。小鳥は平等に枝から枝に移らなければならない。小鳥は枝に付いた新芽にときどき嘴という絵筆でつついてやった。太陽が差し込んだ。小鳥は光をうけてせわしげにさえずった。
その時、野太い声が窓ガラスをゆるがした。描きあがったブナの林に、鳩の糞のようにインクが落ちた。高島は思わず叫びそうになった。その時、高島の肩越しに声がした。
「うまい。実にすばらしい」
チェリー教授が腕組みして首をふって絵をのぞき込んでいた。
教授は、授業が終わってから話があるから部屋にくるようにといって、作品を持っていってしまった。残りの生徒には、次の授業までに図を完成させてくるように宿題がだされた。そばで聞いていた唇のいやに赤いイギリス人が何か言っていたが、高島にはわからなかった。
教授に落書きをほめられ画家になりたいと告白する高島
6時に授業が終わってチェリー教授の部屋にいくと、教授はクッキーをすすめた。
「あなたは地形学が全くわからないらしい。これはこまったことだ。森林学には、地形学は大変重要だから、勉強しなくてはなりません。しかしあなたの絵は芸術作品だ。」
教授は、地形学についての初歩を学ぶ必要があると言い、一冊の本を貸してくれた。それからクッキーをさらにすすめて、教授の質問が始まった。
高島は、じぶんのおおざっぱな経歴を話し、少年のころから絵を描いていたことも話した。
「そんなに小さいころから絵を描いていたのに、どうして画家にならないのですか」
教授の質問に、日本では画家として生活していくのは大変むずかしいのだと答えた。教授はそれはフランスでも同じことだと頷いた。
「でも、私は画家になりたいと思っているのです」
高島は、今までひそかに自分の中にだけにしまっていたことを初めて他人の前で言葉にした。
「しかし私には、画家になる自信が今ひとつないのです」
「自信があるから芸術家になるのではないと思いますよ。描きたいものがあるから、画家になるのではないですか」
「私は国の費用でナンシーに来ているのです。画家になる前に、やはり森林学を学ばなければなりません」
「それが分かっているのに、教室でこの絵を描いていたのですね」
教授は愉快そうに笑って、どんな風に絵の勉強をしたのかを聞いた。模写と写生だというと、どんな作品を模写するのかと尋ねた。高島は、日本の画家の名前は通じないだろうと説明につまった。
「オクサイですか」
高島は、オクサイというフランス語の単語を頭の中で探した。
「オクサイ、ウキヨエ」
高島は目を見開いた。フランス語ではHは発音しないので、オクサイになる。
「葛飾北斎の浮世絵を知っておられるのですか」
高島は弾んで質問したが、教授は北斎と浮世絵を単語としてしっているだけだった。
「この森林学校によく来る人で、日本のものをコレクションしている人がいます。エミール・ガレという人です。ガレもあなたと同じように絵を描きます。花の絵を」
教授は嬉しそうに目を細め、近いうちにガレが来るから紹介しましょうと約束した。
現在でも森林学校の授業はむずかしいと、昭和50代にこの学校に留学した下山晴平さん(林野庁)は言って高島に共感する。「野外学習の時は目で確かめられるのでホッとしました」と話す。(下山さんは学校の先輩に高島得三がいたことを知らず、入学して初めて知ったという。林野庁では高島は忘れられた存在だった)