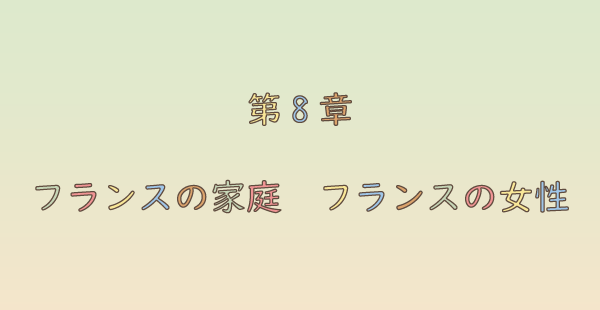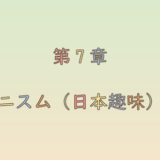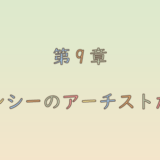家庭教師ユッソンにフランス語と数学を習う
留学生の特権は、滞在の時間を利用してその国の家庭をみる多くのチャンスが得られることだ。その国の人々の暮らしに直接接することで、その国の人の考え方や歴史までも知ることができる。高島得三の場合、ナンシー滞在の3年間、彼がどこに住んでいたのかの記録がなかった。当時は存在したのだろうが、何かの都合で紛失したのか、彼自身が意図的に処分したのかは不明である。森林学校の寮記録に名前がないのは、寮を出ていたことになる。
彼のナンシーでの下宿先の手がかりはナンシー市立図書館でみつかった。高島が寄贈した日本の浮世絵本からブランシュ・ユッソンという家庭教師が判明し、彼女の実家の借家を探りだせたからである。
35歳のフランス女性の優雅さと強靭さに圧倒される高島
高島がボップ教授から、家庭教師がみつかったという知らせをうけたのは、南仏の研修旅行から帰ってすでに10日以上もたっていた。旅行から帰った翌日、高島は担任教授に授業についていけないからフランス語と数学を教えてくれる人を探してほしいと依頼していた。実際、高島は授業の半分のフランス語しか聞き取れなかった。ピュートン校長が教える森林法律学と、ギーョト教授の森林法規、チェリー教授の地形学の授業は、ほとんど教室にでているだけという状態だった。
森林法律学を学ぶために入学したのにもかかわらず、むずかしい用語が出てくる校長の講義は、かいもくわからなかった。地形学は応用数学が基礎になっているので、これも駄目だった。
高島は、講義の後、隣の学生に頼んでノートを見せてもらうことがあったが、ひとまわり以上も年齢が違う若者からノートを借りるのは屈辱だった。結局、ノートを貸してほしいと毎回言い出せず、彼のノートは白紙のページが続いた。授業は、時間のたつのを待つ忍耐という拷問だった。ただ一人の東洋人で、年齢もぐんと年上ということで、クラスの中にとけこめないものもあった。彼はいつも浮いていた。高島はあの拷問から解放されるなら多少の苦労はいとわないだけの謙虚さと覚悟ができていた。
ボップ教授から家庭教師がみつかったと聞きき、まだフランス語の地獄から抜け出してもいないのに、もう半分くらい解決したような晴れやかな気持ちになった。
このフランス語と数学の件について、高島は後にナンシーの芸術愛好家向けに発行されていた「ナンシーアルチスト」誌の編集長、E・オーガンに語っている。オーガンは「高島氏の思い出」の中に書く。
「明治維新以前の日本における数学はごく概括的なものにすぎなかった。江戸で学問に一層の磨きをかけた高島であったが、彼の数学の水準は、ナンシーの学校で力学の授業に無理なくついていける水準から程遠かった。
さらに仏語についての知識は皆無に等しく、当初は言葉の障害は乗り越えがたきものにさえみえた。しかし彼は、こうした苦境に屈するどころか同級生のとったノートを写すのを極力控えられるようフランス語と数学の家庭教師につき始終学問に励んだ」
(「ナンシーアルチスト」誌 1888年3月18号)
ナンシー出身のボップ教授は、地元の人脈に通じていた。教授は、フランス語と数学の両方を教えてくれる人物をさがしあてたのだった。それは、教授の次男が小学校の時に習った教師だった。
「ブランシュ・ユッソンという女性です。マドモアゼルで、あなたと同じ35歳です」
教授はユッソンの経歴を言った。
ブランシュ・ユッソン女史は、小学校のベテラン教師で、自宅は森林学校のすぐ向かい筋のアリアンス通り13番地にある。(現在は森林学校の敷地になっている)父親はすでに亡くなっており、母親と二人の妹、鉄道会社に勤める弟の5人家族である。
「学校とすぐ目と鼻の先ですから、彼女の家に習いに行くのにも便利でしょう。それにブランシュは、フランス語と数学の両方を教えてくれるから、費用も二ついっしょで安くつくと思いますよ」
教授は、掘り出し物をみつけたように得意になってしゃべった。
「ブランシュさんは、数学も教えられるのですか」
ボップ教授は、短くウイとそっけなく言い切った。
「この国には、男の学問である数学を教えられる女性がいるのか」高島は信じられないという顔をしていたので、教授は付け加えた。
「彼女は数学の他に英語も堪能です。あまり優秀すぎて頭がきれるから、いまだに独身ですがね」
教授は独身という言葉をいって、ちょっと微笑した。ブランシュ・ユッソンに会う日は
高島の希望で1日でも早いほうがいいということになって、翌日、夕食を一緒にすることになった。
高島は、家庭教師が女性、しかも自分と同年齢、独身と聞いて意外だった。しかし彼にとって家庭教師がどんな人物であろうといっこうにかまわなかった。ただフランス語の拷問から早くにぬけだしたかった。それほど毎日の授業に出るのがおっくうになっていた。
今も昔も留学生にとって言葉は、大きな障害である。高島より10年早くフランスに留学した中江兆民は、留学に先立って長崎で2年間フランス語を習う。パリに着いた24歳の兆民は、基礎から自分のフランス語をたたきなおすため「まず小学校」に入る。しかし「児童の喧騒にたえずして」やめ、パリからリヨンに移る。ここで恐るべき精神力と徹底した勉強ぶりで、彼がパリに戻った時には「哲学、史学、文学の研鑽」を積んでいた。兆民はわずか2年間のフランス留学で、完全にフランス語をマスターし、ルソーの「民約論」を訳すまでとなる。
高島と同じ年に法律を学ぶために留学した黒田清輝が、本来の目的である法律大学校に入学するのは、パリ滞在の4年目である。しかしその3年間に黒田は、法律より油絵に興味をもってしまう。
高島もまた兆民や黒田と同じように言葉の壁を越えるための一歩を踏み出す。
翌日、ボップ教授といっしょにレストランばかりが並ぶ“食いしん坊通り”の店に入った。
教授を見るなり、黒いドレスの女が椅子からたちあがった。やせて背が高かった。高島は一瞬、冬の木立に止まっているカラスを連想した。それから家庭教師が女性であったことを改めて思いだした。
『35歳というのは、こんなに老けていることなのか』
自分の目の前にいるブランシュ・ユッソンの目尻の皺をみて思った。人生の盛んな時期をすぎてしまった者の穏やかさを高島は、自分と同じ年齢の異性のなかにみた。
しかしブランシュは、外見の虚ろさよりも声も仕草もずっと若々しかった。彼女の白い歯と聡明な瞳は、げっ歯類の動物をおもわせた。
「フランス語はどんな風にして習われたのですか」
ブランシュは、食事をしながら高島の語学歴を聞き、ひそかに語学力を試しているようだった。
高島が、東京で少しフランス語を習い、フランス人の鉱山師のもとで仕事をしながら覚えたことを話し、日本にはまだフランス語の満足のゆく辞典がないことを強調した。
「それでは高島さんがここまでフランス語を話されるまでに、ずいぶん努力をされたのですね」
ナイフとフォークで器用に鴨の肉を切り分けながら彼女は高島をみた。それからとても優雅に鴨の肉を口に入れた。食べ方にもしゃべりかたにも不思議な柔らかさがあった。
「彼女はきちんと躾された家庭のお嬢さんなのだ。教授の推薦した女性だけある」
高島は、初対面のブランシュに好感よりも信頼を感じ始めていた。ボップ教授は、会話が途切れるとブランシュについての新しい話題を提供した。
「ブランシュさんは、パリ生まれなのです。お母さんもパリ生まれでしたね」
教授は、ブランシュの洗練された仕草はパリ仕込だとほめた。
「もうひとつ、高島君に教えておきましょう。ブランシュさんも絵がお好きなんですよ。妹さんのマリーはピアノを弾く音楽家だし、ユッソン家は皆、芸術に造詣が深い」
ボップ教授は、ふだんのいかつさとはうってかわって陽気で饒舌だった。そしてことあるごとにブランシュをもちあげた。ブランシュのためにデザートの菓子のメニューに気をつかったり、コーヒーの砂糖をとってやった。それは、自分の生徒の家庭教師になってもらうことを考慮に入れても、なにかサービス過剰の感じがあった。高島はフランスに来てから女性と一緒に食事をする機会は数えるほどしかなかったので、教授のブランシュへの気の使いように目をみはった。ふたこと目には、教授は「マドモアゼル」と言って彼女の視線を自分に引き付けた。
『フランスの男は、女性にこんなふうに気をつかい、お世辞を言ってもちあげるのか。自分も今後、この女性にこんなふうな気のつかい方をしないといけないのだとしたら、めんどうなだなぁ』
高島は少しうんざりした。
しかしブランシュについて習い始めると、高島が彼女に気をつかうゆとりなど全くなかった。ブランシュの授業についていくのがせいいっぱいだったからである。
ブランシュは、フランス語の動詞の変化と書き取り、作文など次々と宿題も出した。そして毎日、前回教えた内容をテストした。
高島は、学校の授業が終わると、寮に教科書を置き、ブランシュから与えられた教科書を持って、学校の向かい側の通りの彼女の家に直行する。
高島はユッソンの厳しい教え方に耐え抜く
今や学校の授業同様、ブランシュの授業も高島を悩ました。学校の授業は怠けることができたが、1対1のブランシュの授業は毎回テストがあるので怠けるわけにはいかない。彼は毎晩、宿題に出された詩や文学書の一節の暗記に時間を費やした。
「フランス語のリズムを覚えるのです」
と、優秀な家庭教師は繰り返した。
しかし35歳という記憶力の衰えはじめた年齢で、外国の詩を暗誦するのは、自信を喪失するくらい絶望的になった。『言葉の障害は乗り越えがたいものにさえ』思えた。数学においても同じだった。
彼女は小学校の教科書からリセの教科書へと学習の質を高めていった。学校の先生だけにブランシュは教えるのに慣れていた。彼女はじつによくポイントをつかんで、やさしく説明した。そして生徒の弱点をつかみ、弱いところは何回も反復させた。ブランシュは生徒から決して目を離さなかったし、生徒のごまかしを許さなかった。2, 3日前にテストした事柄を、単語を少し変えてもう一度テストするというやり方をした。
高島は時々、ブランシュの冷たく言い放す「ノン」という言葉に思わず立ち上がって帰りたくなった。それは戦いであった。初対面のときに感じた淋しげな雰囲気は、彼女の中になかった。ブランシュは、彼の上に“先生”として君臨していた。
それでも2時間の勉強が終わると、ブランシュの表情は柔らかなものに戻った。
「だいぶ上達しましたよ。がんばりましょう」
と、励ます言葉を忘れなかった。ボップ教授がブランシュを選んだ理由がわかった。
高島がブランシュのもとで勉強し始めた1週間目の日曜日に、ユッソン家の昼食に招待された。
食卓の上座に55歳のユッソン未亡人が位置し、その右側にブランシュ、19歳の次女マリー、三女の14歳のルイーズの3姉妹が並んだ。そして反対側に客の高島と東部鉄道に勤める26歳の長男アンリが座った。それは一枚の家族の肖像画のように整いすぎた風景だった。
『これがフランスの家庭なのか。日本では客といっしょにその家の娘が食事をすることなどないのに』
高島は家族が平等に扱われていることを一種不思議な感激をもって眺めた。
濃い目に口紅をつけているせいか、ブランシュはいつになく華やかな感じをあたえた。ブランシュとマリー、ルイーズの三姉妹は、重ね箱のように同じ顔立ちをしていた。ルイーズから順に老けさせていくと、それがユッソン未亡人になった。その中でも真ん中のマリーは一番ふっくらして顔立ちが整い、白い木蓮のような晴れやかさがあった。高島は長い間忘れていた東京の美津子を思い出した。美津子も今年、16歳になっているはずだった。
料理は鱒がでた。「海のある町に育ったので魚好き」と言ったことをブランシュは覚えていたのだろう。小さな心配りは、食事の随所に感じられた。マヨネーズソースというものにまだなじめない高島のために、サラダがでると女中のバレットが塩と胡椒を彼のそばにおいた。デザートもフランス人の食卓にはかならず出るチーズが登場せず、家で焼いた小さなケーキがでた。
食事の間、鉄道会社に勤めるアンリが代表質問者になった。
アンリは、日本には鉄道があるかとまず質問してきた。
高島が鉄道は敷かれているが、フランスのように全土に敷かれていない、まだ主要な都市の間だけであるというと、アンリは意外な顔をした。
「それでもたいしたものだ。鉄道があるなんて」
と言い、自分は機関士になるのが夢なのだと言った。アンリは、何年間ナンシーにいるのか、帰国するとどこに住むのか、日本でも森林官の給料はいいのかなど、次々と質問を浴びせたてきた。ユッソン家の女性たちは、高島の返答にひとつひとつオーバーなくらい反応を示した。一番彼女たちが大きな反応を見せたのは、高島が「学校の寮を出て、市内のアパルトマンに住みたい」といったときだった。
ルイーズが、はしゃいだ声で目を輝かせた。
「チェスラン通りに私たちの借家があるのよ、そこに住んだら。ねぇ、ママン」
その時は、姉のブランシュは妹の軽はずみな発言を制したが、それから1週間後にルイーズの話は実現した。
寮を出てユッソン家の借家に住み、ひとり住まいの楽しさを満喫
学校側は、高島が留学生であることを理由に、寮を出ることを許可した。このため、森林学校の寮記録には高島の名前はない。
チェスラン通り60番地のアパルトマンの2階、それが高島の異国での小さな城になった。
チェスラン通りは、市場にも3分で行け、学校にも歩いて5分で行ける距離にあった。
高島は引越しするなり、バスタブを買った。それからユッソン未亡人が引越し祝いにくれた鍋でどんどん湯をわかした。
バスタブに脚をいれたとき、むずかゆいような快感が走った。ゆっくり身を沈めた。なるべく肩まで湯が浸るように、体をバスタブにそわせてずらした。杭のように膝頭がでた。
彼はそのままじっと動かなかった。最初湯をはじいていた体に、ゆっくりと湯がしみこんできた。間接のひとつひとつが湯の熱で甘くゆるんでいった。高島は、自分が何カ月間風呂に入らなかったかを計算した。
湯からあがると、彼は食料の買出しにでかけた。日曜日は市場が休みだったが、広場に露店市が立っていた。
広場のプラタナスはすっかり濃い緑に変わっている。風が渡るたびに、葉裏が光った。高島は調理しなくてもいいハムやトマト、果物を買った。ハムの種類の多さに迷った。結局、学校の特約レストランで出されるものに似たものを買った。
肉屋の店先には、豚の足や牛の肉の塊が無造作に吊りさげられ、すだれのように皮をむかれた兎が並んでいた。萩の市場との違いに圧倒された。若い娘が、兎を一匹買っていった。
『あんなあどけない顔をした娘が、平然と兎の足をもぎとって調理するのか。ブランシュやマリーも同じようにするのだろうなぁ』
高島は、14歳の時に腑分けをみて卒倒したことを思いだした。西欧人は、獣を捕らえ、獣を解体してその肉を食べるから、腑分けという発想が出てくるのだろう。狩猟民族の彼らは、きっと血をみることに慣れているのだろう。かつて森を駆けた獣を追っていた雄々しい狩人の血が、優雅にふるまっているユッソン家の女たちにも流れているにちがいない。彼女たちはドレスの下に自分の知らないような強靭な力を持っているのだろう。
高島は、ブランシュと白い木蓮のようなマリーの顔を思い浮かべた。彼女たちがずいぶん遠い存在に思えた。
アパルトマンに帰ると、ドアの前に買い物カゴが置いてあった。カゴの中にサンドイッチとイチゴが入っていた。ブランシュのため息のでるような美しい字で「新しい生活はいかがですか」というメッセージが添えてあった
高島の生活は、アパルトマンに引越ししてからも大きな変化はなかった。学校の授業は、ブランシュの指導でいくぶん分るようになったが、依然として言葉の壁は高くそびえていたし、ブランシュの授業もユッソン家で行われた。食事は昼食と夕食は学校の契約レストランでとった。
寮をでて改良された点は、風呂に入れることだった。風呂にはいるとき、彼は日本人であることをせいいっぱい謳歌した。
時間のあるときは、レストランに行かないで自分の口にあう料理を作った。醤油がないのは決定的だったが、買ってきた魚を塩焼きにするだけで、レストランの何倍もうまい食事ができた。なによりもアパルトマンを借りてからご飯がたべられるようになったことだった。サラダ用に売っている米を買ってきて、鍋で炊いた。日本にはない細長いパサパサした米だったが、白い飯を食べると、胃袋が活発に動き出すのがわかった。
市場で変わった食べ物を探し出し、店の主人に料理法を聞いて作ってみるのも彼の楽しみだった。いつもいく八百屋の女将さんは「ムッショ ジャポン」と呼んで、きゅうりに似たクルジェットをすすめ、煮込み料理の方法を教えてくれた。食べてみると瓜の味がした。山芋に似た黒大根も、皮をむいて煮込んだ料理にした。薬臭いセロリという野菜に慣れるには時間がかかった。
市場に行くと単語の数も増えた。現物があるので覚えやすい。
しかし時々くやしいことにでくわした。外国人だからわからないだろうと、おつりを誤魔かされたり、並んで順番を待っているのに、東洋人というだけで無視された。高島は、馬鹿にされないように、いい服装をするようになった。
高島はフランス語の色の表現に、食べ物の色が多く使われているのも、市場で買い物をするようになって気付いた。栗色(マロン)、カフェオーレ色、シャンパン色、蜂蜜色とフランスの伝統的な色には植物の名前がついていて
『さすが食いしん坊の国だわい』
と感じさせた。
そう考えると日本の色に圧倒的に植物に関する色が多いこともわかった。特に紺は、フランスより日本の方が豊富で、微妙な色が多いように思える。水浅葱、縹色(はなだいろ)、鉄紺、紺、藍と高島は日本の藍色を思い浮かべ、初夏の店先にひるがえる暖簾の藍を懐かしく感じた。
市場で買い物をし、町を歩くたびにさまざまな発見をすることが楽しかった。学校と寮だけの今までの一ヶ月ちょっとの生活では気付かなかった外界のものが、一度に洪水のように彼の中に飛び込んできた。彼は昆虫のように複眼でそれをとらえた。言葉が堪能でなかった分だけ、彼の視線はよく働いた。
しかし学校生活もブランシュの授業の方も、アパルトマンの生活ほど快適ではなかった。ブランシュの授業も高度さを増していった。ブランシュはよく詩を暗誦させた。これは彼女の好みというとよりは、フランスの小学校ではよく行われる授業法のひとつらしい。
「10歳ぐらいでロンサールの詩を暗誦します。“あなたの年齢が花咲いている間に楽しみなさい 楽しみなさい あなたの若さを”なんてね」
「10歳じゃ 詩の意味もわからないじゃないですか」
「わからなくてもいいのです。何回も口ずさんで頭にしみこませてしまうのです。少し
大きくなったら意味は、自然とわかってきますから」
ブランシュは自信をもって言い切った。高島は、日本で漢詩を暗記するようなものかなと考えた。
高島が、シュリ・プリュドーム(1837~1907)の詩を暗誦し始めると、ブランシュは軽く目をとじ、小首をかしげて聴いていた。「こわれた花瓶」の一節をそらんじると、ブランシュの眉間がかすかにくもった。昔の傷をなぞられたように、彼女の閉じた目尻に絹糸の皺がよった。しかしその唇は、何かを待っているようにポチリとあいていた。
高島は、このつつましやかなしっかり者の女性が、恋人との夜にはどのような乱れ方をするのかと考えた。その瞬間、詩の一節が空白になった。
するとブランシュが、一節の冒頭を言ってくれた。高島は思い出して、再びそらんじ始めた。
ブランシュの顔に赤味をさし、35歳の女は童女のように夢みる表情になった。二人の間に、あるやさしい感情がゆきかった。その感情が育っていく予感が彼女をためらわせたが、次の一瞬、ブランシュは驚いたように目を開いて、高島の発音をなおした。
その時、ピアノの乱暴な音が、高島の詩を打ち砕いた。
「ちょっとごめんなさい」
ブランシュは、モスグリーンのドレスをひるがえして部屋を出て行った。
ピアノは激しいリズムの曲に変わっていた。自分の存在を全身で訴えているように、ピアノは静かな家のすみずみまで鳴り響いた。
「私にだって練習があるのよ。この家は姉さんだけの家じゃないわ」
マリーの金属的な声がした。
高島には、もの静かで白い木蓮のような娘が突然癇癪をおこしたこと事態が信じられなかった。木蓮の花は、北の方角をむいて咲く性質があるように、マリーにもなにかはかりしれない暗くて強いものがあるのかもしれないと、高島は思った。
再び静寂が家全体を包んだ。
「すみません。さぁ、始めましょう」
戻ってきたブランシュは、マリーのことは何ひとつ触れずに授業を続けた。
高島はその冷静さと、私的なことを仕事の場に持ち込まない割り切り方、姉妹の恥を外に出すまいとするブランシュの態度にあっけにとられた。なにか『あなたは部外者だから関係ないでしょう』とピシャリと鼻先で戸を閉められた感じがした。さっきのやさしい感情は、すっかり吹っ飛んでしまっていた。
フランスの家庭とフランス女性に戸惑う高島
高島は、肉屋の店先から兎を丸ごと買っていった華奢な娘にも、妹のヒステリーぐらいで動揺しないブランシュにも、ある強靭なエネルギーを感じた。表面のしとやかさとは裏腹に彼女たちは、ことなにかがおこれば男たちと一緒に闘う逞しさを秘めていた。それは、可憐さが女の美徳とされている日本の女性とは全く異なるものだった。ブランシュのように男性顔負けの教養をつみ、一家を支えている女性が、堂々と存在することが、高島には珍しかった。彼は今まで女性を自分たち男性と同じ対等の位置にある人間としてみつめたことがなかった。高島の育った萩という土地は、女は玄関から出入りできず、いつも勝手口を使うという男尊女卑の家長制度が浸透した土地柄であった。
しかし高島は、ブランシュとの出会いによって、いやおうなしに彼女を対等の人間、授業中はそれ以上の存在としてつきあわざるを得なかった。ブランシュは、ユッソン家の婚期をのがした娘ではなく、ブランシュ・ユッソンという自分の位置を持った女性であった。ブランシュは、高島が個として女性をみた最初の人だった。彼にとってブランシュは、初めて出会った女性というひとつの異文化であった。これまで女性の肉体を知っていたし、感情の動きも知っていたが、ブランシュのように一つの自我をもち、教師という自立した経済力をもち、周囲の人々から「ブランシュ・ユッソン」という個人としての地位をもち、人間として社会的に認められている女性を知らなかった。女は結婚するまでは「○○家の娘」であり、結婚後は「○○夫人」であり、子供が成長すれば「○○氏の御母堂」とよばれるのが、多くの女性の生き方だった。高島は、今まで自分が知っている女性とは全く違うタイプの女性にであったのだった。それは“異文化”との出会いといっても過言ではなかった。
ただこの“異文化”は、一見なじみやすくみえて、その実、なかなか手ごわく、竹の地下茎のようにどこまでも根をはっていて複雑だった 。
高島は家庭教師のユッソン家の人達との交流によって、森林学以上の知識を得たはずである。高島の3女高島愛子(1900~1945)は日本映画の黎明時代の女優だが、高島が娘が女優になることをきつく反対しなかったのは、ナンシーで自立したユッソンのような女性を知っていたからだろう。