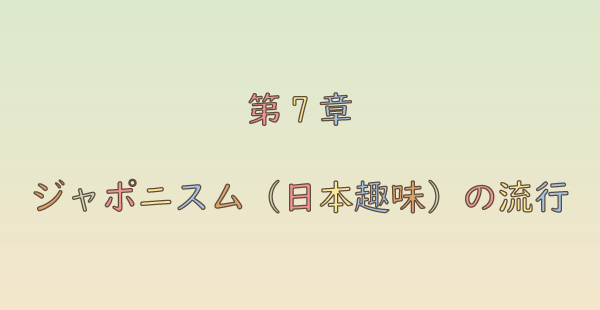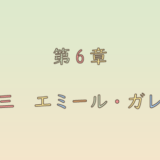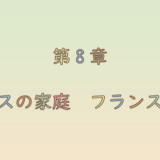ジャポニスム(日本趣味)の流行に火を付けたのは万国博覧会
森林学を勉強に行って、反対に日本についてフランス人たちに教える立場になった高島得三。この奇妙な逆転劇を理解するには、当時のジャポニスム(日本趣味)の大流行をしる必要がある。忘れてはならないのは、ジャポニスムの美を発見し評価をしたのは、フランス人やイギリス人など西欧の知識人の感性だったことだ。日本人は昔からの美の視点を当たり前に受け継いだにすぎない。高島得三もそうだった。彼はジャポニスムが高く評価されていることに、面映かったにちがいない。高島がジャポニスムの流行と同じ時期にフランスいたことが、彼の半生を変えることになる。
売れっ子デザイナー、ウジェンヌ・ルソーの創作の秘密は浮世絵と中国陶器
高島がナンシーの森林学校に入学した1885年4月、ガレはベルリンにいた。ベルリンで、新しい商品のデザインのモチーフを探していた。経営者のガレは、売れ筋の花瓶や香水瓶に要求されるのが、オリジナリティーであることを知っていた。ひと目みただけで「これはエミール・ガレの工房のものだ」とわからせるほどの個性的な商品が必要だった。
そのためにはまずデザインだった。ガレは新しいデザインを求めてベルリンにきたのだった。彼は市内に宿をとって、毎日勤め人のように工芸美術館に通っていた。この美術館には、古代のガラスからベネチュア、ボヘミヤグラスといったヨーロッパの伝統ガラスの他に、中国や日本の陶器を所蔵していた。中国作品のコレクションは300点にものぼっていた。 ガレの目当ては、中国の青磁と乾隆帝ガラスだった。学芸員が特別に見せてくれた部屋で、乾隆ガラスの製法をさぐりながらデザインを模写した。
小柄で華奢な体つきのガレは、39歳という実際の年齢より若かく見せていた。強力な磁石のような集中力は、少年時代からのものだった。ひとつの玩具に熱中しだすと、それをこわしてしまうまでいじりまわしてしまう粘着性があった。
今はその集中力に、芸術家としての自負と野心と経営者としての責任が加わり、彼の集中力を強いものにしていた。しなうような強靭さがみなぎっている。彼は、自分のためだけに用意された世界の闇の奥底の一点の光に向かってまっすぐに突き進んでいた。その光は乾隆ガラスの透かし彫りの手法をまだ探りだせずにいた。
乾隆帝ガラスは、清代に宮廷瑠璃廠でつくられたガラスの俗称である。最盛期が18世紀中頃の乾隆年間であったため、この名前がついている。
製法は、被(き)せガラスといわれるもので、ガラスの素地に異なった色のガラスを部分的、あるいは全体にわたってかぶせかける技法である。
しかし花瓶のガラス本体をどのようにつくるか、浮き彫り文様は何によって、どのように彫刻されるのかがわからなかった。ガレは、乾隆ガラスをひとつずつ手にとって、手の感触で技術をさぐり出していた。
透明な淡緑ガラスに白色のガラスが上に被せられていた。彫刻のように白色ガラスの表面を削りとって、淡緑の地を浮彫にしている。浮彫の花柄文様は、白のレースのように繊細だった。
窓の光にすかしてみると、淡緑ガラスと白色ガラスの間にも、もう一つ別の淡黄ガラスが被せられている。それが浮き彫りに陰影をつけ、深みのあるものにしていた。
乾隆ガラスの花瓶は、4月の弱い陽を吸いこんで、ガレの手の中で森の奥の湖水のような静寂をたたえていた。が、製法は精緻さの中に隠されて見えてこなかった。
パリでは五年前の1880年に、ウジェンヌ・ルソー(1827~1891)が乾隆帝ガラスを真似た花瓶を作り出し、話題になっていた。ルソーの「山水人物文花器」は、白銀色の地ガラスに朱色の花柄が浮彫にされ、エキゾチックな雰囲気をかもしだしていた。
ルソーは、パリ生まれのセーブルの磁器工場の陶器デザイナーである。ガレは、自分より二歩も三歩も先をいくルソーの存在をいつも意識していた。
というのも、ルソーはその頃、陶器デザイナーとして花形だった。パリで開催される工芸展では、いつもルソーの作品は無審査で展示されて特別扱いだった。
ルソーには、モチーフを提供する強力な友人がいた。セーブルで知り合った陶芸家で画家のフェリック・ブラックモン(1833~1914)だった。ルソーはこの男から日本の浮世絵や中国陶器を見せられ、それらの図柄や形を真似て新しい作品を生み出していた。「山水人物文花器」もそうした作品のひとつだった。
「秘密を探り出せましたか」
学芸員が背中から声をかけた。美術館に3日も通う間に、学芸員とも親しくなった。ガレは、バカロレア合格後、2年間ドイツのワイマールに留学していたのでドイツ語が話せた。ドイツ語を話すフランス人に学芸員は親切だった。
学芸員は、象牙でできた小さな彫刻のミニチュアをみせた。
「東洋の国の人達は、私達とはちがった不思議なエネルギーと感覚をもった人種ですな」
学芸員の手にのっているミニチュアの象牙の家には、人が住み、家具が置かれて、部屋はいくつもに仕切られ、その部屋にもまた座っている人間が執拗に彫刻されていた。象牙の家自体、小さな確固たる世界を創っていた。そして見る者の視線を奥へ奥へと誘いこんでいった。視線を誘い込むという点では、乾隆帝ガラスの花瓶も同じだった。花瓶の全面に浮彫された花を追いかけるうちに、視線は迷宮の中で堂々巡りをおこし、不安な無限の空間を体験させられる。始めと終わりがメービウスの帯のようにつながっているのだった。
「こんな彫刻の置物を作る人間は、どんな人種なのでしょうね」
ガレは、学芸委員の手から象牙の家をとってしみじみとつぶやいた。
「これはどうですか」
学芸員は、サーカスの手品師のようにいたずらっぽく楕円形の鉄板を机の上においた。楕円の中央は、細長くくり貫かれ、金の楓が彫金されている。
「日本のものです。剣の柄と刀身との間にはさむ“ツバ”というものらしいです。世界には奇妙な人種がいるものです。剣の見えないところまで細工して・・・パリでは日本のものが人気を呼んでいるというじゃないですか」
学芸員は鍔(ツバ)をひっくり返して見せた。裏側には、楓に鈴虫が一匹とまっていた。
学芸員は、象牙の家と鍔をそれぞれの箱にしまい込むと、ガレに深いため息をつかせたことにすっかり満足して、陳列ケースの鍵を鳴らしながら出ていった。
再び静寂がもどった。
ガレは閉館までたっぷりノートをとった。しかし青磁の壷の文様は、あまりに複雑すぎて形だけを写しとるにも骨が折れた。
ガレは黄昏のベルリンの街を歩きながら写しとることができなかった青磁の壷の文様や日本の刀の鍔(ツバ)の楓文様を頭の中で何度も反芻していた。反芻するたびに、記憶は鮮明さを失っていき、その焦りが形すらもおぼろげにさせていった。そのことが、パリのウジェーンヌ・ルソーの存在を強く意識させた。
ルソーもブラックモンも東洋のもの、とりわけ日本の陶器、浮世絵、工芸品を収集していた。一説には、ブラックモンは日本の文様を丸写しにしているともいわれている。ガレは自分も日本や中国のモチーフになる物を今まで以上に集め、モチーフを提供してくれる人物の必要性を感じていた。特にこれからは、ジャポニスム(日本趣味)だとおもっていた。
ガレがジャポニスムを意識した最大の理由は、ジャポニスムの商品が売れたからだった。100人近い職人をかかえる経営者であるガレにとって、売れる商品はなにより大事だった。
ジャポニスム(日本趣味)は、当時フランスだけでなく、ドイツ、ベルギー、オーストリア、イギリスまで拡がっていた。ジャポニスムの流行は「まるで火薬庫にそえる燃える炎のごとく、すみやかにすべてのアトリエを制していた」(1878年エルンスト・ショノー著「パリの日本」)
ジャポニスムの始まりはナポレオンのエジプト遠征
ジャポニスムのそもそもの始まりは、ナポレオンのエジプト遠征まで遡る。エジプト遠征は、フランスにエジプト風スタイルを普及させた。それが次第にイスラム世界に対する関心へと変わっていった。1830年にアルジェリアがフランスの植民地になったことや、今までトルコの統治下にあったギリシア王国の独立が、アラビア文化にむかわせた。
19世紀の画家ドラクロアは「キヨス島の虐殺」を描き、アングルは異国情緒たっぷりの「オベリスク」を描いた。画家だけでなく、工芸の方面でもジョセフ・ブロセールが回教のモスクのランプを真似、それが人気を呼び、壁紙やタイルの文様にもイスラム風のものが好まれた。
ビザンチウムへの憧れは、やがて中国へと人々の目をむけさせた。19世紀前半、中国風の陶器や家具が大量に輸入されたが、それでも追いつかず中国風のものが真似てつくられた。
中国趣味(シノワズリー)」は、地球のはての国への夢想をかきたてた。ボードレーヌは「旅への誘い」で「ああ かしこ かの国にゆかば、ものみなは秩序と美、豪奢(おごり)、静けさ、はた快楽」と詠みあげた。
当然のこととして、人々は中国の次に日本に目を向けた。特に、日本は鎖国をして、外国との交渉をオランダ、ポルトガル以外は閉じていたので、ヨーロッパ人の想像をかきたてた。
そこにジャポニスムを演出すものが出現した。万国博覧会である。
ペリーが浦賀に来航した翌年、1855年にパリで万国博覧会が開催された。高島はまだ5歳、ガレ9歳のときである。
この万博には、日本は正式に参加していなかったが、日本の色絵磁器が展示された。日本の磁器が、1851年の第一回ロンドン万博で大きな反響を呼んだことがパリにも伝わっていた。
日本の陶器、工芸品は、17世紀オランダからヨーロッパにもたらされ、その精巧さと美しさ、エキゾチズムから王侯貴族の間で珍重されていたが、一般の目にふれることは、あまりなかった。
パリ万博が日本人の知らないところで日本宣伝をはたす。人々はこの万博によって地球、のはてにジャポンという国があることを知り、マルコ・ポーロの「黄金の国 ジパング」の一節を思い出したのだった。
しかし人々は、中国と日本をごっちゃ混ぜにみていた。ただ日本は中国よりさらに遠い国ということで、人々のロマンをかきたてた。鉄道の発達が旅への誘いにひと役買っていた。
1837年にパリとサンジャルマンに鉄道が敷かれ、1870年にはほとんどフランス全土に鉄道網が広がり、それによって人々の移動は頻繁になった。
街も変わった。ナポレオン3世とオスマン男爵は、1852年から70年にかけてパリに大切開手術を施し、現代の近代都市にパリを作りあげた。1852には、デパートが誕生した。人々は変化を進歩であると信じていた。そうした時に、パリで第2回目の万国博がおこなわれた。
パリ万国博覧会と鉄道の普及が人々を旅に誘った
1867年、パリのシャン・ド・マルスで開催された万国博覧会会場には、公園や田舎風の家、宿屋、制服のホステスたちが給仕する民族料理を出すレストランが作られた。ジプシーの音楽が、パリっ子を熱狂させた。
入場者は、4万4千以上にものぼり、1855年の万博の3倍以上が会場におしよせた。日本は、正式にこの万国博から参加する。
将軍の名代として14歳の徳川民部大輔昭武が派遣され、目付けとして山高石見守が御守役として付き添い、この一行に田辺太一や渋沢栄一が加わった。渋沢は、のちに明治、大正を通じて日本の財界の指導者となった人物である。
日本側の出展作品は、工芸品と農林水産物、和紙、書籍、衣服、絹織物、象牙細工、ガラス器、磁器、日本刀、人形などであった。錦絵は5600枚も出展された。
人々は、会場にもうけられた日本の茶店で、ニッポン人の生活を初めて目にした。ひのき造りの茶店には、六畳の土間があり、便所もあって、軒には提灯がつりさげられていた。小さな池もあり、周囲は竹の塀で囲んであった。奥には3人の女性が着物姿で茶を入れたり、コマで遊んだり、キセルで煙草を吸っていた。
人々は縁先に群がって覗き込み、眼鏡を取り出す者もいた。日本会場は大盛況だった。
パリ万博に出品した徳川幕府
ところが一行が帰る時、変えるべき幕府はなくなっていた。1867年の万博の翌年は明治維新である。
渋沢は、一行の帰る旅費を捻出するため、出展された日本の物産を売って船賃を捻出した。5600枚の錦絵も売られ、フランス全土に散っていった。
この万国博によってジャポニスムは、パリを中心に池に投げた小石のように広がった。
万博でみた日本の漆器に魅せられた職人たちは、日本製の模造品を作り出した。マルティン兄弟は、擬似漆や有田風のモチーフで軟質陶器を作った。1869年、美術評論家のエルンスト・シュノーは、ユニオン・セントラルの講演で、ジャポニスムの流行について警告をする。
『フランスの芸術は、単に日本芸術に迎合してその真似をするのではなく、その魅力的な概念を研究して、それをいかに応用し、展開し、完成させ、われわれフランス人が使うのに最適なものにかえられるかを知り、世界の市場の中でわれわれの産業が最大の栄誉と幸福が得られるように努力すべきだ』
しかし一度勢いのついたものは、加速度を増す。
1873年のウィーン万博 1878年のパリ万博で人気を博した日本館
1873年、ウィーンで開催された万博でも日本の展示品が人気を博したことがフランスにも伝わってきた。この時の日本館の演出もなかなか心にくいものだった。とりわけ最終日の演出は凝っていた。
11月2日の最終日の会場には、数百の灯が飾られ、神殿鳥居の内側に菊の花で扇型をつくった。中央に紅菊で円をつくって、日の丸の扇としたのである。いよいよ夕暮れ、万博の幕がおろされる頃になると、その菊を観客に1本ずつ配った。そして日本館の売店に障子をはめこみ、3人の女性の踊りを影絵で写し出し、日本の音楽をかなで続けた。その音楽がふっと止むと、障子が取り払われた。と、金屏風の前に礼服を着た日本側の役員、佐野常民たちがずらりと並んでいた。彼らは、群がる観客に向かってドイツ語で堂々と挨拶をしたのだった。観客は興奮した。そして競って日本人に握手を求めた。
このウィーン万博が作った日本ブームは、やがてオーストリアに「分離派様式(ゼッエッション)」という芸術確信運動の引き金となっていく。「分離派様式」とは、オーストリアのアール・ヌーヴォーと呼ぶべきもので、グスタフ・クリムト、ヨーゼフ・ホフマン、コロマン・モーザー、アルフォンス・ミュシャなどの画家がその担い手である。
ウィーン万博から4年後の1878年、再びパリ万博が開かれる。日本はもちろん参加する。
前回の万博で人気を呼んだ日本の建物は、今回はもう少し大きな規模で作られた。日本製品は45316点も出品される。陶磁器、金や銀、銅の器、漆器、小間物、玩具、雑貨、家具や屏風などの工芸品だった。
予想通り日本の展示品即売会場は連日満員で売り子は、もう品切れですと叫ばなければならなかった。ジャポニスムの熱風は、フランス全土をかけめぐった。そして遂にジャポニスムに反発する者も現れた。
「ジャポニスム!
現代の呼び物であり秩序を乱す猛威である。このジャポニスムは、あらゆるものを侵略し支配し、われわれの芸術、習慣、趣味、そして理性に至るまでのすべてを混乱に落としてしまった」
と、ヴィクトル・ド・ルネは1882年「インターナショナル審査員報告書」の中で批判した。
そして1883年には、ジャポニスム熱への反省がされるようになった。グスタブ・ティルヴェはアムステルダム國際博覧会で、ジャポニスムの影響でフランスの工芸品の伝統美がそこなわれてしまったことを嘆き、反省をうながした。
ヨーロッパの芸術家はジャポニスムの何に魅せられたのか?
しかしジャポニスム熱は冷めなかった。むしろますます過熱していった。
流行にはそれに火をつける仕掛け人と、流行を支える人間がいる。ジャポニスムに最初に火をつけ注目したのは、すぐれた感性と、自らの作品の中に新しい何かを模索していた芸術家たちだった。ジャポニスムを支えたのも彼らだった。
フェリックス・ブラックモンは、そうしたすぐれた感性を持った珍しいものがり屋のひとりである。彼は1856年、日本から送られてきた陶器の包み紙に目をとめた。「北斎漫画」が包み紙として使われていたのだった。新しい造形表現を求めていたセーブル磁器の絵付師は「北斎漫画」の中の雄鶏をそっくり真似てセーブル磁器の皿のモチーフにした。これが好評を博した。
ブラックモンは、同じセーブル磁器の絵付師である友人のウジェーヌ・ルソーと一緒に日本風の花鳥のモチーフでテーブル・ウエアのフルセットを共作した。これが評判となった。1867年のことである。それ以後、二人は熱狂的なジャポニザン(日本愛好家)となる。
ブラックモンが、いかに日本趣味にかぶれていたかを知るには、リモージュのアドリアン・デュブーシュ美術館の地下にいけばわかる。そこには、素仙、探信、法眼といった狩野派の掛け軸の他に鶴と松、竹と雀といった狩野派の掛け軸が、埃をかぶっている。
学芸員は「分らないのでとりあえず、カビがはえないように保管しています。この掛け軸の絵は有名な絵描きですか」と取材者の私に尋ねた。
日本の陶器は、地下の一室の四段の棚にギッシリと保存されていた。伊万里、九谷のほかに志乃、信楽といったものまで集められている。それは、ブラックモンのコレクションであり、タネ本だった。
その頃、画家のモネもまた1862年にル・アーブル港の積荷の中から、日本の色刷り版画を発見していた。
当時の印象派の画家たちは、マネ、モネ、ドガ、セザンヌ、ゴッホたちのほとんどが日本の浮世絵から、自分に必要なものを自分流に作品の中に取り入れていた。
マネは、影をつけない浮世絵の遠近法を、ドガは「北斎漫画」の職人図から着想をえて躍動する「踊り子」の中にいかしていた。セザンヌは、北斎の「富獄三十六景・甲州三島越」の構図にヒントを得て、故郷の「サン・ヴィクトワール山」を描いた。そしてピサロへの手紙に書く。
「北斎はすばらしい印象主義です。モネとロダンと私は夢中になりました。(中略)これらの日本の芸術家たちは、私たちの視覚についての確信を一段と深めてくれました」
(1892年3月27日の手紙)
セザンヌやモネ、ドガ、ロートレックといった画家たちは、日本美術の左右非対称の構図のおもしろさ、形の科学性、色調の豊かさ、特に紺色の微妙さ、余白を残した絵画的効果の独自性、さらにそうした効果を単純な方法によって得ていることに目をみはった。
作家の中にも浮世絵に魅せられた人物がいた。ナンシー出身の貧乏貴族、ゴンクール兄弟である。エドモン・ド・ゴンクール(1822~1896)とジュール・ド・ゴンクール(1830~1870)は、貧乏貴族であったが、生活にこまらないだけの財産を相続していたので、兄弟でヨーロッパ各地を巡った。その後、1850年から小説を合作で書き、共同で日記もつけた。二人は日記を文学のひとつのジャンルとしてえらんだので、作家の内心と生活を語っていながら、私的でなかった。彼らは、日記を現実の観察記録にしようとした。
二人の日記に浮世絵のことらしい「色つき画帳」という言葉が初めて登場するのは、1864年7月である。その後、70年から80年代前半にしばしば「色つき画帳」「日本画帳」の言葉が出てくる。兄弟の言葉を借りると、浮世絵の価値は次のようになる。
「色彩の美を写し、姿態の妙を描き出したことのみにあるのではない。人物の心理を表現することにあるのである。言い換えれば、浮世絵が遊女の華やかな衣服、しどけない容姿、その美しい顔付き、目付きを描いたのは、みな、その内面的な生活すなわち遊女に特有の心情を赤裸々に表現するためだ。
浮世絵は庶民の極楽であった遊郭の生活、歌舞の菩薩であった遊女の心理を表現する芸術写真であることが、浮世絵の存在理由でなければならない。特に浮世絵が貴族絵画の伝統を離れて、民衆美を発見したことに芸術革命の意識を発見するのである」
(“芸術家の家”)
いささか浮世絵を深読みしていて、おもはゆいところもあるが、“胸をしめつけられるような”対象、特に精神病者、変質者、娼婦に興味をもっていた作家だからこそ、浮世絵が民衆美を描いていることに注目したのだろう。いかにも「売笑婦エルザ」を書いた作家らしい。
兄弟を感動させたもうひとつは、日本の美術品の中に見られる象徴を用いて表現するという技法だった。
「私は先日、刀の鍔(つば)を手に入れた。この鍔の円面を見ると、空の一角に銀の半月がでていて、雪白の秋空から紅葉が二枚散りかかる景色である。しかし紅葉の樹は彫っていない。このような図柄の中に、日本金彫の構想が残らず現れている。この二枚の紅葉だけが金工の思いついた道具立てにすぎないし、日本の詩歌の文句もまたこれだけの材料を用いるに止まっている」
(“日記”1876年10月31日)
ゴンクールは、彫金師が二枚の紅葉から、その紅葉の樹を想像させ、さまざまな瞑想をよび醒ませる手法に瞠目したのだった。日本芸術のもつ“余白の美”にひかれたのだった。キャンバスを埋め尽くす西洋絵画には、なにも描かないで見る者に想像させるという発想はない。ゴンクールは、余白もまた空間表現のひとつの方法であることを日本の美術から教えられる。
1881年、ゴンクールは「芸術家の家」を書いて日本美術の素晴らしさを世間に発表する。彼らの周囲には日本美術のわかる友人たちがおおぜいいた。その友人達にはゾラ、ドーデ、ユイスマンスといった作家たちやマネやモネ、アメリカ人のホイッスラー、ブラックモン、ドガ、ファンタン・ラトゥールらの画家達、美術評論家のフィリップ・ビューティー、ナンシー出身の美術評論家ロジェ・マルクス。そのなかにはエミール・ガレも入っている。
ゴンクールの仲間達が、いかに日本愛好家ジャポニザンであったかは、セーブルの磁器工場で毎月1回開かれる「ジング・ラーの会」が証明してくれる。
会員のゴンクール、マネ、モネ、ホイッスラー、ドガ、ファンタン・ラトゥール、ゾラ、ビューティ、ブラックモン等は、ブラックモンによって刷られた北斎や広重の富獄図風の会員カードをもってセーブルに集まり、日本の着物を着て、日本風の料理を食べ、「日本」を楽しんだのだった。
そもそも「ジャポニスム」という言葉を最初につかったのは、この会の会員である美術評論家のフィルップ・ビューティ(1830~1890)だった。ビューティは1872年に「芸術・歴史・民俗学的な新しい研究分野を指す」ものとして“ジャポニスム”という言葉を使った。だから「ジング・ラーの会」も単なる異国趣味を愛する会を超えて、根本的な新しさを追求する会をめざしていた。
ナンシー出身のゴンクール兄弟が信頼した美術商、林忠正
この熱狂的なジャポニザン達によって、日本ブームは一層あおられていった。当然、こうしたジャポニザン達に日本美術品を提供する商人がいた。
1862年頃、極東の美術品を扱ったのは、ドソワ夫人の店「中国の小舟(ジャンク・シノワズリー)である。ルーブル美術館の向かい側の通り、リボリ側220番地の「中国の小舟」に、ブラックモンやビュルティ、詩人のボードレールが立ち寄って買っていった。ゴンクール兄弟もこの店の常連だった。
ゴンクールによれば「でぶでぶに太ったユダヤ女」のドソワ夫人は、日本や中国を旅行して買い付けていた。
パリにはこの頃、J・G・ウーセーの「中国の門」や「中国帝国」「天皇の帝国」などの東洋の美術品を扱う店が出現していた。少し遅れてサミエル・ビングが店を出す。ハンブルグ生まれのドイツ系ユダヤ人サミエル・ビング(1838~1905)は、1870年の普仏戦争の最中にフランスに帰化する。最初は、東洋の陶器を扱っていたが、日本の工芸品や浮世絵が商売になることを知って、1875年には自ら日本に買い付けに行く。
パリのショーシャ通り19番地のビングの店に、ゴンクールやモネ、ロートレック、ホイッスラーがやってきた。1879年にパリに支店を出したエミール・ガレも顔をだすようになる。ガレの支店、プテット・エクリー通りは、このビングの店に歩いて10分程度の距離にある。後にビングは、プロバンス22番地に店をだすが、そうなるとガレの店とは、さらに近くなる。
ビングの店は繁盛する。このビングがプロバンス通り22番地に出した店を1895年に改装し、新たに店の名前を「アール・ヌーヴォ」と命名したことから新しい美術様式が“アール・ヌーヴォ”と呼ばれるようになる。パリに留学していた画家、浅井忠(1856~1907)は、ビングのことを次のように残している。
「ビングという人は、有名な骨董商にしてかつ図案家に候。同氏は日本の古画古器物類を非常に集めて、欧州諸国に其の趣味を紹介したるひとりなる。(中略)実に羨ましき生涯にして面白く金もうけできて、愉快な事と感じ申候。
随分学者にしては分りたる人なれど、金もうけが旨くてユダヤ人故悪くいう人も多く有之候」
ビングを妬む者がいたくらいに店は繁盛していた。ビングの店の顧客であるゴンクールさえ「日記」に悪口を書いているくらい、彼は日本美術で稼ぎまくっていた。
やがてビングにライバルが出現する。1884年、ひとりの日本人がパリに日本美術店を開いたのである。林忠正である。
林忠正(1856~1906)は、越中、高岡の医者、長崎言定の次男として生まれ、14歳の時、富山藩主、林太仲の養子となり、林忠正と名を変える。忠正は明治維新を機に上京し、フランス学塾に入いる。その後、大学南校でさらにフランス語を勉強する。堪能なフランス語を見込まれ、忠正は1878年のパリ万博の通訳として渡仏する。
万博が終わった後も忠正はパリに残り、万博で日本館の出店の窓口となった起立工商会社のパリ支店の社員になる。
1882年には、起立工商会社をやめ、今度は三井物産のパリ支店に入社し、日本美術の専門家として頭角を現す。忠正は出版社「ガゼット・デ・ボザール」の社長ルイ・ゴンスが「日本美術」を書くのに協力し、1883年には竜池会がパリで初めて「日本美術縦覧会」を開くのも手伝う。竜池会とは、フェノロサらが主催する日本の伝統美術を研究することを目的とした会である。
そして翌年の1884年、忠正は念願だった自分の美術店をシテ・ドートヴィル通りに開店する。忠正28歳の時である。
ゴンクールは林忠正の協力でヨーロッパNO.1の日本美術通に
忠正の店には、美術評論家のフィリップ・ビューティやゴンクールがやってくる。ビューティの紹介で、忠正は1878年のパリ万博のときすでにゴンクールに会っていた。ゴンクールたちは、自分たちが魅せられている日本美術の真の辞書をみつけたのだ。流暢にフランス語を話す忠正は、嵐のような激しさと雄雄しい闘争心をもっていたが、表情は日本の陶器のように穏やかで、貴族のゴンクールを敬愛していた。
エドモンド・ゴンクールは、弟が亡くなってから猫のように用心深く猜疑心が強くなっていた。自分の小説よりゾラの作品がよく売れるということだけで、ゾラを嫌い、そればかりかゾラを擁護するマネまで嫌った。彼は「お菊さん」の著者ピエール・ロティがアカデミーの会員に選ばれたことで腐りまくっていた。
しかし親子ほど齢の差がある東洋人の忠正には、心を許していた。この気難しく、誇りの高い老人にとって好ましい人間は、自分の作品を褒めてくれて、敬愛してくれ、なおかつ競争しなくてもいい人間だった。忠正はその条件をすべて満たしていた。その上、日本美術の第一人者たらんとするゴンクールにとって、忠正は生の日本の情報の提供者だった。さらに「日本の商品の値を吊り上げている悪党ビング」にひと泡ふかせられた。
一方、忠正にとってもゴンクールはありがたい存在だった。世間の人々が“ジャポン”などどこにあるのか知らないときに、フランスの著名な作家から日本美術について質問されるのは、大変光栄なことだった。しかもその作家は、貴族だった。異国の者がフランスの上流階級とつきあえるのは、現在でもごくまれなことである。
忠正がゴンクールを尊敬したのは、「中国と日本の美術をはっきり区別」し「日本人さえ気付かなかった日本美術の美」を次々と発見してくれることだった。それも、きらめくような言葉でヨーロッパに日本を喧伝してくれるのだ。
「パリの冬の空、曇った汚い空を悲しむ人は日出ずる国の明朗な青空に光線を求めるがよい。日本は三千八百の島々から成り立っていて、水は国の内外を豊かに流れている。水は日本人の情熱である」
(“芸術家の家”)
このようなゴンクールの日本賛歌は、異国の地でいる忠正の心の支えであった。彼にとってエドモンド・ゴンクールの存在は荒海を照ら灯台であった。見る物、さわるものが、日本より何十年も進んでいるフランスにいて、忠正はゴンクールという最高の日本美術の理解者と出合ったことで、劣等感をもたずにいられた。
ひとは異国に身をおくと、妙に愛国主義者になるものだが、ゴンクールの存在は、忠正の日本人であることのプライドを支えてくれた。
彼は、日本とフランスの文化の橋渡しをしていこうとしている自分に誇りをもつことができた。
だからこそ忠正は、日本から送られてくる粗悪な美術品に不安を感じ、1886年からたびたび日本に帰り、自分の鑑識した商品を選んでフランスに送り込んだ。それは彼が死ぬ1906年まで続けられた。
老作家ゴンクールは、そんな誠実な忠正が気に入っていた。「日記」の中に忠正のことを書いている。
「(前回帰国した)林が送ってよこした牡丹を植えるのを、1日中見てすごす。
(1888年1月9日)
「林が来て、牡丹の名札を訳す。“茜雲” “袖が香り” “薄化粧”」
(1888年5月4日)
「林の家で憂さを忘れ、歌麿のすばらしい画帳“引き潮の思い出”と、とりわけすばらしい鳥文斉の“三十六歌仙」”を買う」
(1888年5月7日)
「家で、林が日本の本の書名を訳し、江戸の芝居について話す」
(1888年5月13日)
ゴンクールは、林忠正の協力によって1891年「歌麿」を書き、1896年に「北斎」を書き上げ、願っていたように日本美術の第一人者となる。ちなみにゴンクール兄弟が結婚もせず集めた日本美術のコレクションが死後、売却され、その売り上げ金が今日のゴンクール賞の基金になっている。
ナンシーのエミール・ガレは、このゴンクールと林忠正の結びつきをかねがね羨ましいと思っていた。
1884年12月、ガレはパリ郊外にあるオートゥイユのゴンクール邸を訪れ、その膨大なコレクションを見た興奮を知人に書き送っている。
「私はこうして、あの“芸術家の家”を歩きまわることができましたし、そこで大変な価値のある聖なる品々を自分の手のなかにとってみることができました。象牙、根付、金蒔絵、小ブロンズ彫像、七宝、玉器、窯変、あるいは貫入炉器、翡翠、岩水晶の品々です」
ゴンクールのコレクションに圧倒されると同時に、ガレは自分にも林忠正のようなジャポニスムのモチーフの提供者があったらと思うのである。
というのも、ガレは今まで“ジャポニスム”の作品で効果をあげていた。1878年のパリ万博に出品したガラスの花瓶は「北斎画漫画」にある「魚濫観世音」からモチーフを撮って高い評価を得ていた。ガレは、鯉の上にのる観世音をとりのぞき、川をのぼる鯉をそのまま真似て、透明ガラスのかびんに黒の単彩で絵付けした。それはあたかも、ガラスの中で鯉が泳いでいるような効果をうみだしていた。
「しばしば模倣されたライオン像の陶器の燭台」も、脚の部分に伊万里の文様を入れることでエキゾチックさを作り出していた。
ガレは、1884年の「第8回パリ装飾美術中央連盟展」に、陶器とガラス器を合わせて300点を一挙に出品し「ナンシーのガレ」の名を一躍世にしらしめる。出品された作品はガレ様式と呼ばれる特色がすでに表されていて、ファイアンス(軟質陶器)にもガラスにもモチーフとして花と昆虫、貝が多く使われた。
しかし彼は、これらのモチーフを使いながらも片方でヨーロッパ様式の伝統を受け継いだ作品を作っていた。ガレ自身は、はっきりとこれからは“ジャポニスム”の作品がうけることを確信していた。しかし彼は、ゴンクールのように中国趣味(シノワズリー)とジャポニスムを明確に区別はできていなかった。だからこそ自分にも林忠正のような人物が必要であることを痛感していた。
高島が森林学校に留学した1885年、パリではジャポニスムが大流行していた。その流行はパリから離れたナンシーでもおこっていた。ナンシーの知識人、アーチスト、ブルジョアが関心をもっていた「日本」に、本物の日本人がやってきたのである。高島はたちまち「時の人」になった。そのことが高島の人生そのものも変えることになる。