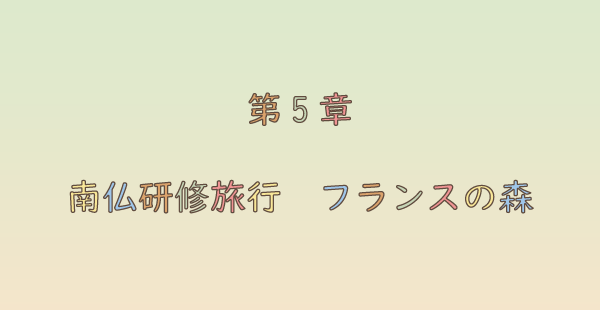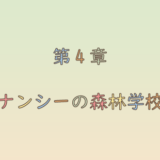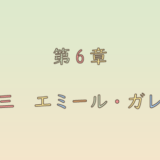森林官の任務は国境を守ること
「数日来ノ良晴 梨季桃桜斉シク花ヲ開キ路傍ノ白楊嫩緑風ニ揺ク 真ニ旅行ノ最良時節ナリ 東頭南ニ向テ奔ル」(第1回仏南巡歴日誌)
1885年4月22日、高島得三は森林学校の南仏研修旅行に参加する。一行は、ピュトン校長とポップ教授、イギリス領インド森林学校のベレー校長とエリオット教授、イギリス留学生9人、高島の計14人だった。
高島は、校長と担任教授から、フランスの森林学を学ぶためには、まず自分の目でフランスの風土を見る必要があるし、今回はそのいい機会だとすすめられたのだった。入学してまだ1週間しかたっていなかったが、すすめられるままに参加した。フランス語の授業に手こずっていた高島は、戸外の実習の方がまだわかりやすいだろうと思ったからだった。
朝、10時ナンシーを出発した汽車は、マルセーユに向かって南下していた。
1週間前、パリをたったときはまだ緑は灰色の殻をかぶっていたのに、今はすべての木々が、灰色の帽子を脱ぎ去って、緑の髪をのばしている。桜や梨、杏の花々が競いあって咲いている。ほがらかな光の世界にみちていた。どこもかしこも春だった。
「スコットランドも今頃春だなぁ」
コンパートメントのイギリス学生のひとりがつぶやいた。それっきり3人のイギリス人も高島も黙って、車窓の田園風景にみとれていた。時々、視線があうと微笑した。高島は地図を広げて汽車の位置を確かめた。
汽車は、フランス中央部にあたるディジョンに近づいた。地図でみると、ディジョンは北緯47度と北の町で、千島と同じ位置にある。しかしリンゴの花が咲いている。高島はノートに「リンゴの開花は、青森の弘前より1ケ月半も早い」と書き込んだ。
ディジョンをすぎると外はしだいに暗くなってきた。鉄道の職員が、客車の屋根づたいにきて、コンパートメントの天井に固定されたランプに外から点火した。そのため車内の換気が悪くなった。
汽車は、闇の中を吼えながら、夜を切り裂いていた。夜汽車の音は、何かやさしい未知の華やかさに満ちていた。
上司武井守正の美貌 容貌は全世界共通?
午前6時、マルセーユに着いた。フランス人の憧れる南(ミディ)だった。
その日は、マルセーユの動物園と植物園を見学した後、マルセーユ港を散歩した。高島にとって1年ぶりのマルセーユだった。
去年、アバ号の甲板から初めてフランスをみた興奮が鮮やかによみがえった。陸が見えてきたと言われ、上司の武井守正と急いで甲板にかけあがった。
最初にブルーと白と赤茶色の色彩の平手打ちにあった。網膜がハレーションをおこした。目が慣れると、マルセーユの町の高台に立つ寺院が白のアクセントを作っていた。マルセーユの町は、海と空の間にはさまれ、青のなかにたなびく白っぽい布のようにのびていた。
「高島君、これがフランスだよ」
武井は前方をみたまま言った。歌舞伎役者のような端正な横顔は、感動のため少年のように紅潮していた。43歳の武井は、陸の一点をみつめ、深いため息をついた。
「やっと着いたね」
「着きましたね」
高島をみた武井の目はうるんでいた。かつて米を買い占めていた御用商人に天誅を加えた姫路藩のこの豪気な人でも、こんなとき泣くのかと高島は思った。そう思った途端、彼の目は涙のためマルセーユの町がふくらんだ。全身がしびれるようになり、ほうけたように甲板につったっていた。
高島は、去年の5月22日にマルセーユに着いてからのこの1年のあわただしさを振り返った。
エジンバラでの森林万国博、ドイツ、オーストリア、イタリアの林業視察を強行スケジュールで巡回したときのことが、波のように次々と彼の脳裏にかぶさってきた。
スイスでは降雪のため視察ができず立ち往生になった。夜、レストランで店のウエイトレスから武井は声をかけられた。
「南イタリアから来ると、このスイスの寒さはこたえるでしょう」
高島がウエイトレスの言葉を通訳すると、武井は怪訝な顔をした。高島が代わって自分たちは日本人だというと、ウエイトレスは
「日本人?日本てどこにあるの?」と聞てきた。フランス語が話せる高島が、結局ウエイトレスと会話することになった。武井は少し淋しそうに言った。
「言葉ができないと盲人と同然だね」
しかし高島は、この時、別のことを考えていた。美貌、美しさといったものも、万国共通ではないかと。目鼻立ちがはっきりし、太い眉と切れ長の目の武井は、どこに行っても女たちの視線を引いた。この国の女たちは、露骨に異性への関心を表したので、そのことがよくわかった。
武井守正自身、欧州山林視察で自分が人々の関心を引いたことを嬉しく思っていたのか「男爵武井守正翁伝」に記している。
『君が欧州僻地の或る山林を巡視したおり、土地の人々は日本人だとは思ひもよらず、髪も瞳も黒いのを見て、伊太利亜南部の人と信じていた。然るに日本の山林局長だと分ったので大いに驚き、これこそ誠の珍客であると非常に優待するようになった。欧州では山林局長になるのは、既に禿頭または白髪の老人であるが、日本の山林局長は若いと、人々は驚いた』
高島は、どこへ行っても人々の視線を集めていた美貌の上司を思い、今頃はオランダからアメリカに向かう船のなかで、語学のできないことを悔しがっているだろうと想像した。
午後のマルセーユ港は、一枚の青いガラス板となった海に、何十隻もの客船と貨物船を配していた。ヨーロッパ随一の港は、高島をいつまでも引き付けた。久しぶりの潮の匂いは、彼を爽快な気分にさせた。潮風に吹かれて歩いていると、イギリス人の学生が食事に行かないかと誘いにきた。
南仏名物の米サラダ、フランスでは米は野菜だった
食事は豪勢だった。高島もイギリス人も海から遠いナンシーでは食べることのできない魚を、この日ばかりはしこたま食べた。海老はレモンをかけるだけでうまかった。ニンニクとオリーブ油と白ワインで蒸したムール貝もうまかった。ボップ教授が推薦した南仏の名物料理“ブイヤベース”は、なんのことはない魚貝のごった煮だった。鮮やかな黄色の煮汁は、サフランという香辛料を入れたためだという。
しかし魚は大味で、もうひとついただけない。萩の海でとれた魚でこの料理を作れば味も数倍よくなるのだがと残念だった。ここでも野菜を生のままでたべる“サラダ”がでた。イギリス人たちは、“ニース風サラダ”という牛の飼い葉のような青菜を
「これは、いける」といって食べているのをみると、高島はフゥと鼻から息を吐き出した。
「これじゃまるで青虫だ」
野菜を生のままで食べることを高島は、ヨーロッパにきてからしった。食事のときほど、文化の違い、人種の違いを感じことはなかった。その文化の違いを決定的にする事件がおきた。
隣のテーブルのイギリス学生が
「教授、これが美食の国のサラダですか」
と、皿に盛った米をみせた。米のなかにピーマンやトウモロコシが入っていて、見た目にはなかなかきれい。
「この国じゃ、米は野菜なんだ。所かわれば品変わるとはこのことだ」と高島は感じた。生徒がみせた米のサラダをみて
「カマルグ・サラダですか?うまいじゃありませんか」と、ボップ教授がニヤリとしてやりかえした。するとその大盛りの米サラダが、教授や高島のいるテーブルにまわってきた。
教授は、南仏にカマルグ地方という湿地帯があって、そこで米を栽培していると言った。高島が、フランスにも稲作があるのかと聞くと、イタリアでも米を作っていると、教授はこともなげに答えて、高島に米サラダをすすめた。
高島は、一口食べて、思わずムッと顎をひいた。生煮えで米に芯があった。まるでロウをかんでいるようだった。後は呑み込むよりほかなかった。
「これは、調理が不完全です。米が煮えていない」
高島が首をふっていうと、ボッブ教授は
「固いから米なんですよ」
と、意外な顔をする。
同じテーブルにいたイギリス学生も「煮えてない」と言ったので、隣のテーブルの学生たちが拍手をして笑った。
すると教授はむきになって
「うまいよ。このうまさが君たちにわからないとはね」
と言って食べる。それを学生たちははやしたてた。高島は、文化の違いが人間の味覚まで変えてしまうのかと目を見張った。ドーバー海峡をはさんですぐ隣のフランスとイギリスでもこんなに味覚が違うことに驚いた。
“米(リー)”という言葉はひとつだが、日本人にとっての「米」とフランス人にとっての米は、なんという違いだろう。日本人にとって主食の米は、フランスでは野菜だった。
言葉は同じでも、住む場所、風土、環境、その国の文化背景、あるいは身分によってもそのものの中身は変わってくる。海だってそうだ。「海」という言葉は同じでもマルセーユと萩の海は全然違う。マルセーユは乾燥した土地なので、潮風にあたってもべとつかない。
しかし海といえば、マルセーユの人はマルセーユのこの海しか思わないだろうし、萩の人にとっても、海は萩の海なのだ。でも世界には、さまざまな海があり、いろいろな米がある。言葉はひとつでも、事実は無数である。真実はひとつではない。
高島は、この時はっきりと自分が異国の地にいることを実感した。
マルセーユの1日は、カマルグ・サラダで幕を閉じた。
森を管理し耕すことが文化(カルチャー)
翌日、一行はマルセーユを発って、オーリャール駅まで汽車に乗った。駅におりると、見覚えのある制服が目に入った。緑の軍帽型の帽子と緑の上着、青灰色のズボン、それがフランスの森林官の制服だった。制服をきたふたりの森林官は、ひとりがレハ林区長、もう一人が森林看守で伍長の位のある男だった。
森林官「Forestier」は、国有林の監視人、林務官のことで、日本の営林所長クラスにあたる。この森林官たちは、公式な場には緑の制服をきて出席することになっていた。戦争時でも、軍服を着ないで、この緑の制服をきる。その上、森林官は、軍隊の中で特別優遇されていた。
というのは、こと戦争がおこれば林区長が先頭に立って森を案内する。ヨーロッパでは、森が国境になっていたからだ。
フランスには、41区の森林区があるが、林区長になると自動的に大佐の位が与えられる。だからこそ、将来の林区長を養成する森林学校では、軍事教練が学科に取り入れられているばかりか、全授業の七分の一が軍事教練にあてられていた。
森がいかに軍事上のポイントになっていたかを示す百年戦争の例がある。
1356年、戦利品をかかえてロワール河を南下するイギリス軍を、フランス軍がひそかに追っていた。ところが森の中なので、互いにどう動いているのかわからず、追いかけていたフランス軍は、イギリス軍を追い越してしまい、あろうことかフランス軍の最後尾とイギリス軍の先頭が衝突してしまう。追手をかけるはずのフランス軍は、反対にイギリス軍から追いかけられる形となり、国王ジャンはイギリスに捕われてしまう。これがポワチエの戦いである。
森の地理にくわしい林務官は、それだけで優秀な陸軍の軍人だった。ボップ教授は、林区長と同じ大佐の位で、フランスで唯一の森林学校の校長、ピュトン校長は軍隊の大将の位をもっていた。それは農林大臣と同じクラスを意味していた。
一行は、レハ林区長の案内で、荷物を村の教会に預け、720メートルのサントボーム山に登る。
「サントボームト称シ、ローマ時代ノ神女断崖ノ窟穴中ニ住シ所ナリトテ、古来著名ノ霊場ナリ。諸国ヨリ神蹤巡拝ノ徒常ニ絶エズ。仏国代々ノ帝王モ登山アリ。山ハ、紀州高野山ニ類セリ」
(仏南森林巡歴日誌)
霊山とあって、山の木には1800年あまり斧が入れられてなかった。カシ、ブナ、ニレ、菩提樹の巨木がうっそうと茂り、木漏れ陽が地上に縞模様を作っている。まるで山全体が迷宮のように深い。
レハ林区長が、1本のカシを指差し、樹齢500年あると言った。生徒のひとりが、巻き尺でそのカシを計った。
高島は、幹のはるか上空に豊かな枝葉を斜上に張るカシを見上げた。レハ村長は「樫(シエーヌ)」と言ったが、日本の樫ではなく、葉や幹の色から日本のミズナラとわかった。
「日本でなら、樹齢500年もある霊山の木なら、しめ縄でもかけるところだなぁ」
そう思いながら、高島はカシの幹に触れ、この国には樹木を信仰の対象とする考えのないことに気付いた。そのためか、霊山といわれるサントボーム山を登っていても、“木霊”(こだま)も感じない。
しばらくはカシの林が続いた。カシは、ヨーロッパの森で、ブナと並んで最も一般的な樹である。英語ではオークといわれるカシは、“森林の王”と呼ばれ、高さ20メートルから25メートル、種類によっては30メートルにも達する。ヨーロッパの樹木のうちで“最長命”で、歴史は森の樫に聞けという諺があるくらいだ。家や家具、かつてはバイキングの海賊船に使われたのも、このカシである。
レハ林区長は、途中、何回か立ち止って説明をした。そして後は、蟻のように一列になって黙々と登り続けた。
森に呑み込まれそうな村、森は闘うべき敵だった
突然、視界が明るくなった。
眼下に緑の樹海が広がる。森の中にところどころハゲたように村落がある。村は緑の海に浮かぶ島だった。ナメクジが這ったように森の中に細い道が続く。緑の海は、どこまでも続いていて、その境界線は空の中にとけていた。森はアルプスまで続いているという。光景は、日本の山頂からみる風景とまるで違っていた。
幾重にも重なる山はない。朝日は緑の地平線から突然あがるのだろう。森は山、人は平地といった配分がそこにはなかった。村は、周囲の緑に囲まれ、キュッと小さく固まって息づいている。「村が今にも緑の波にのみこまれそうだ」と高島はおもった。
高島がかんじたように、ヨーロッパの森は、人間の生活の前に立ちはだかる緑の壁だった。人々は、森の木を切り、緑の壁を切り崩して村を作り、畑を作った。
しかし切り開いた森は、放置しておくとまたもとの原始の姿に戻ってしまう。「眠れる森の美女」では、魔女の呪いをうけた姫が眠りにつくと、森はたちまち城をおおい尽くし、「マクベス」では、バナームの森がダンシネインの城に向かって動く。ヨーロッパ人にとって、森は闘うべき敵である。
仏語のSauvageは森の意味で、野蛮とは“森のような”ということである。つまり、人間の手が入っていない所である。人間が森に手をいれ、木を切って、土地を耕す(カルチャー)、それが文化(カルチャー)である。フランス語のCultureは「耕作」と「文化」の二つの意味をもつ。
ヨーロッパの森には、一度開墾されたあと再び森になってしまった二次的森林というのが多い。森は生きていて、大斧で幹を切り、切り開いても少し放っておくとたちまち木々の大波が押し寄せ、空き地は森の海に沈んでしまう。
日本の自然も、山崩れ、河川の氾濫、地震など人々を恐れさせている。しかしそれは、本来おだやかな自然が、時たまその場で体を動かしたため、そのとばっちりで人々が迷惑をこうむるということにすぎない。日本の自然には、静的なものがあるが、ヨーロッパの自然には、人間に襲いかかってくるような動的な、野獣的な荒々しさをもっている。だからヨーロッパ人は可能な限り自然に手を加える。
高島は、サントボーム山の頂上から森を俯瞰して、日本の風土とのあまりの違いに愕然とした。
『このような全く異なる国の森林学が、はたして日本の森林に適応できるのだろうか』
彼はかすかな不安を感じた。
レハ林区長の説明は続いていた。日照時間の長いサントボーム山の樹木は、どれも木の比重が高く、良質であることを林区長は具体的に比重値をあげて説明している。高島は南なまりの歌うようなフランス語をぼんやり聞いていた。
高島たちは、その夜、村の教会に宿泊した。ジャガイモと豆だけの質素な食事だった。翌朝、雨の音で目が醒めた。
イギリス学生の体力と気力に圧倒される高島
しかし授業は、スケジュール通りおこなわれた。イギリス生のひとりが十分ばかり遅刻したが、午前6時、一行は雨の中をついて出発、8キロ先のオーバーニュ停車場にむかった。
南(ミディ)の雨は太い。高島の傘の周りに水のすだれができた。昨日豊かだった森は、一変して不気味な場所に変貌していた。
レハ林区長は、闇を走る汽車のように逞しく先頭にたって森を突き進んだ。
一行はツーロンに出て、オリーブ栽培を見学し、その日はツーロンに泊まった。
翌日もまだ雨は止まなかった。
そしてその朝も、昨日と同じ学生が遅刻した。授業は計画通り実施された。20キロの行軍の後、オリーブ園に着き、マドン林区官なる人物が、オリーブ栽培の土壌について長々と説明した。ピュートン校長は、傘をさしたまま直立不動の姿勢で聞いている。ボップ教授にいたっては、傘をさした弁慶のようにいかめしい顔つきである。質問する者もいた。そのため雨の中の講義がのびた。
高島は、林区長の話は半分も理解できなかった。次々と話の中から飛び出す数字を翻訳するも骨が折れた。フランスは60進法なのでややこしい。高島は、林区長がしゃべる数字を口の中で復唱し、数字に書きなおした。
雨は小止みなく降り続いた。
午前10時、モンリューノという古い教会で昼食をとり、再び森に入り、マドン林区官の講義を聞いた。午後になると雨はいよいよ激しくなったが、ピュートン校長は授業の中止を言わなかった。ツーロンのホテルに帰ったのは、午後6時をまわっていた。
「この日、路程往復12里」
と、彼はノートに記した。
ホテルは二人部屋だった。
高島は、体をふいて一刻も早くベッドにもぐりたかった。ところが、相棒の学生がノートをだして、今日の授業の整理を始めた。彼は寝るわけにはいかず、並んでノートを開いた。ドアがノックされ、隣の部屋の学生がノートを持って聞きにきた。
高島は、彼らの体力と集中力に圧倒された。彼らが自分より15歳も若いというのは、何の理由にもならなかった。何かが根本的に違うと思った。よく鍛えられ、調教された馬のように強靭だった。
「こんな奴らと闘うことになったら、自分は負ける。日本は負ける」
高島は、深い敗北感に似たものを感じた。しかし相棒のおかげで、たっぷり2時間その日の授業内容をノートに再現することもできた。
ノートの整理ができると、相棒の学生は服を脱ぎ、脱ぐごとにハンガーに吊るした。学生は下着だけになると、ベッドのそばに行って、最後の下着までもスルリと脱ぎ捨てたのだった。その瞬間、高島はベッドの中で身をこわばらせた。彼はきたるべき事態にそなえての言葉をさがした。相手を傷つけずに拒むフランス語はすぐに思い浮かばない。
「眠ったふりをしよう」
咄嗟に考えがひらめいた。昼間の相棒の親切が、今から考えるといろんな意味をもっていたことに思いあたった。高島は35歳という年齢に似合わず動転していた。
しかし隣の青年はいっこうに自分のベッドに近づいてこない。ランプは消され、窓からわずかな明かりで、隣のベッドが人の形を作っているのが確かめられた。やがて青年の寝息がかすかに聞こえた。
高島は、毛布から亀のように首をだした。思いきり大きな深呼吸をした。体中の血がうごき始めると、彼は相棒の目をさまさせないように毛布で口をおおい、笑った。
「イギリス人は裸で寝るのか」
旅行も5日目を過ぎると、それなりに旅の日程に体が慣れた。仲間の性癖もわかった。高島がひそかに“遅刻君”と名付けた学生は、皆が注意しないことをいいことにいつも集合の時間に5, 6分遅れてきた。高島は不思議だった。どうして“遅刻君”に仲間は注意を与えないのかと。
しかしイギリス人たちは、遅れるにはそれなりの理由があるのだと思っているのか、「ごめんなさい」と走ってくる同僚を非難の目で見ることもしない。「イギリス人は紳士の国だというが、集合時間にいつも遅れてきて何が紳士なものか」、待つことも待たされることも嫌いな高島は、待っている間、例の貧乏ゆすりをした。
賭博の国モナコの存在に驚く高島
4月30日、フレジュからサンラファエルを経て汽車でニースに出た。コンパートメントのひとりが買った新聞に、パリでヴィクトール・ユーゴーの国葬が行われたことが載っていた。
高島は、コンパートメントの3人のイギリス人が
「モナコに着いたらひと儲けしょう」
と言い合っているのが、よくわからなかった。モナコが賭博の国であることをしったのは、実にモナコに着いてからだった。
『モナコハ仏国ノ伊太利亜トノ間ハマル小独立国ニテ人口4万人に過ギズ。政府ノ財政ヲ維持スルモノハ賭博ノ税ニシテ、四方ノ旅客コノ地ニ集マル。公然賭博ヲナシ』
高島は、この世の中に賭博の税だけで生計をたてている国があることを聞いて、自分の耳を疑った。しかしそれは事実だった。国民は、観光と国営カジノの収益があるので税金をおさめる必要がないというのだった。その上、国営カジノの建物が清潔にあふれ優雅で、少しも下卑たところがないのに驚いた。日本の威信をかけ、贅を尽くして建てられた鹿鳴館など、この賭博場に比べると安っぽい張りぼてに見えてしまう。賭博場は、蒼空に向かって歓楽を朗らかに謳歌していた。『賭博という悪しきものもまた人生の一部として認め、人間の負の要素もまた西欧では承認しているのだ。森の教会で、ジャガイモと豆だけを食べる神につかえる人間がいる、その一方で享楽の殿堂がある。なんと許容量が広いのだろう。西欧の国々は、大人の国なのだ』
高島は、ふるえるような感動で、国営カジノの建物を見上げた。その館は、誠実な正義より美しい嘘の方が、よほど真実を含んでいるのだといわんばかりに、彼の眼前に燦然とそびえていた。
モナコでの見学が終わると、研修旅行もいよいよ終盤に近づいた。終わりが近づくにつれ高島は焦りにも似た不安を感じ始めていた。
「国が違うということは、すべてが違うことだ。森も木も違う。人の接し方まで違う。こんなに何もかも違う国で、はたして自分は日本に何を持って帰ることができるのだろうか。たとえ持って帰っても、それを日本という風土に根付かせることができるのだろうか」
彼は、フランス語と格闘しながら、何度も漠然とした不安に襲われた。その不安から高島が感じ取ったものは、とにかくフランス語をもっと勉強しなければいけないということだった。すべてはそれからという気がした。
5月5日をもって実習は終わった。
翌6日、午前7時アレースの街をたってマルセーユに着き、また長い汽車の旅が始まった。来るときのような好奇心も興奮もなく、コンパートメントは檻のように退屈だった。例の“遅刻君”と同じ席だったことも高島の気持ちを沈ませた。彼は他の2人のイギリス人と話したが、“遅刻君”とは会話をさけた。
高島はあまりの所在なさに、ノートをちぎって折鶴を折った。イギリス人の3人は目を輝かせ、折鶴を順に手にのせてまわした。そのうちに“遅刻君”が折鶴をおそるおそる解いた。そして今度は実に慎重に折鶴の再現にとりかかった。他の二人はそれを見守った。
“遅刻君”は、折りたたんだ紙の跡をなぞろうとして、何度も手をとめたる。そして彼はひとつの法則を発見する。三角形を作っていくという法則を。白い紙は、“遅刻君”の膝の上で何度も向きを変えた。
やがて、手垢でよごれた折鶴が生まれた。高島は“遅刻君”の集中力、根気に圧倒された。
“遅刻君”は、折鶴をいとおしそうに手にのせて高島に見せた。
「こんなに美しい紙の鶴を作り出すあなたの国は、とても美しい国なんでしょうね」
その言葉は、乾いた土地に注いだ水のように高島の心にしみこんでいった。と同時に、自分は他人に対しての寛容度が低いのではないかという思いにとらわれた。仲間の遅刻を口にしない寛容さは、どこかで賭博の国モナコの存在に通じるものがあった。その寛容さのなかには、人間のさまざまな生き方を肯定する眼差しがあり、人間の多様性を包みこむ力があった。人間を一定の枠にはめこまないゆとりは、今まで見てきた森に代表される厳しい環境の中からどのように生まれたのだろうか。高島は、文化という言葉をぼんやりと頭の中でころがしていた。明治政府になって、国をあげての西欧化が叫ばれ、自分もその西欧化を推進するひとりとして留学したのだけれど、そのことが真に必要なのだろうか。すべてを西欧一色に染めてしまうことが、日本の文化を築くことになるのだろうか。高島は、“遅刻君”にならって一心に折鶴を折っているイギリス人たちを眺めながら、考えにならない思いにとらわれていた。
汽車はナンシーに近づいていた。