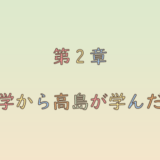藩医の次男として恵まれた環境で育った高島北海
父の絵画趣味の影響を受ける
高島得三は嘉永3年(1850年)9月26日、長門国阿武郡萩江向村の藩医の次男としてうまれた。現在の山口県萩市江向町である。1988年、私が萩を取材した時には生家の跡に「高島北海生誕の地」の石碑があったが、今はない。
高島の父、良台は毛利家本藩の奥付きの藩医だった。奥付きというのは、藩主の奥方や姫様の担当医師をいう。良台は人望が厚く、川向こうの皮をなめしている貧しい村に病人がでると、気軽に出かけていき治療したという。
高島は、父良台と母曽能との間に次男として生まれた。4つ年上には兄、張輔がいる。明治維新の志士たちの多くが貧農の家庭の出身者であるのにたいして、高島はめぐまれた環境で育った。そのことは彼の性格を見ていくうえで大きな意味をもつ。萩の郷土史家で医者でもあった田中助一さん(故)は、高島の生家の写真をみせながら「北海先生は、藩医の息子であるから本草学にもくわしく」と、高島を恩師のように尊敬されていた。
父良台は、酔茗の雅号を持っていたくらい絵画が趣味で、参勤交代の折に江戸土産として書画をかってきて幼い兄弟を喜ばせた。息子たちは土産の椿椿山を模写した。高島は、筆さばきをみただけで画家名をあて、父親を驚かせたという。兄弟の合作「菌蓮根図」や、高島が8歳ごろに描いた「雀図」が残っている。「雀図」の構図はよくできているが、雀の細部に無駄な線がなさすぎるため、これは写生したのではなく模写だろうと思われる。あたりを警戒してきょときょとしている雀は動いているので、簡潔な線で表しにくくよけいな線を描きこんでしまうものだから。しかし8歳の息子の絵を大事に残しておくほど両親から可愛がられて育ったことは確かだ。温かで知的な家庭で彼は何不自由なく育った。彼自身も穏やかな性格の子供だっただろう。後年、彼が憤慨し激情にかられるということがなかったのも、こうした少年時代につくられた性格だった。
明倫館の先輩 乃木希典の負けても清々しい姿に憧れる 医者への道を断念した理由
高島は15歳で、萩藩の藩校、明倫館に入校する。同級のひとつ年上には乃木希典がいた。乃木とはそれから3年間一緒に机を並べて勉強する。
当時の藩校は、文学と兵学2寮に分かれていたが、高島も乃木も文学寮に籍をおいていた。二人は明倫館で学びながら、校則で決められていた12時から午後6時までの外出自由時間を、学校から5町ほど離れた一刀流指南栗栖又助のもとで剣術の修業をした。
ある冬の日、剣術の稽古が終わって皆が帰ろうとしたとき、乃木が自分の下駄の片方を探しているのを二級年下の生徒が「何をぐずぐずしているんだ」と押しのけた。その拍子によろけた乃木は
「君は目上の僕に向かって」
と、相手の袖をつかんだ。つかまれた生徒は、道場に通いだして間もない年下の生徒だったが、剣の筋の良い青年だった。自信もあったので、やせて剣術の腕も劣っている乃木を鼻から小ばかにしていた。
「ちょっと中庭にきなさい」
と乃木の言葉に
「ああ、行きましょう、どこへなりとも」
と下級生は喧嘩をかってでた。高島は聡明な乃木がどう決着をつけるのかと見ていた。
乃木は中庭にでるなり相手の胸ぐらをつかんだが、一瞬速く相手は乃木を抱き上げて投げ飛ばした。乃木は空中に投げ飛ばされた犬のように背を丸めて地面に落下した。叩きつけられた乃木は、二つに体を折ってなかなか立ち上がれなかった。下級生は薄い笑いを浮かべて悠然と立ち去った。そばにいた生徒が、乃木を助けおこそうとしたが、彼は邪険にその手を振り放って立ち上がろうとした。が、たちあがれなくて、両手で右足を押さえていた。
「骨折したのですか」「僕の肩につかまって」
そばにいた生徒たちが次々と声をかけた。誰かが乃木の下駄を持ってきて彼の前に並べた。乃木は左足で踏ん張ってかろうじてたちあがった。彼の額には脂汗がにじんでいた。乃木は下駄を手にもって、素足でびっこをひきながら帰っていった。ひとことも口をきかなかった。高島は「乃木さんにはかなわないな」
とおもった。そのことがあって乃木をいっそう注目するようになった。乃木は明倫館の授業中、姿勢を崩さないこと、夜食が出たときはなぜか「家の者に外では食べぬようにいわれていますから」といって箸をつけなかった。
高島は、後年、明倫館の文集のなかに「乃木さんへの思い出」と題してしるしている。高島は、乃木希典の不器用なまでの清廉さに憧れをもっていた。だから乃木が明治天皇の崩御で自決したのを知ったとき「やったのう、ひやぁ、乃木はやりおったのうお・・」といった。(5女の園さんの「父・北海のこと」のインタビューから)
高島は18歳のとき、母曽能を病気でうしなう。父良台は、翌年はやばやと再婚したため、実家の存在は軽くなり、高島は明倫館を卒業すると乃木と同じように軍人の道を志す。父良台は兄弟のどちらかが医師を継いでくれることをのぞんでいたので、高島は14歳のとき、父親にいわれて死体解剖を見学した。しかし解剖の血の匂いをかいだ瞬間気を失ってたおれてしまった。このことがあって、医学の道は早くに絶たれた。あとは、軍人か政治の道である。さいわい高島の住む萩は、時代の渦を作り出している中心地だった。
世は薩長の時代 軍人を志し大阪陸軍所へ 受験に失敗 上京しフランス語を習う
維新の志士たちは、高島の知っている人たちだった。木戸孝充、高杉晋作、村田蔵六から改名した大村益次郎、井上馨・・・日に何度となくこの人達の名前を聞くうちに、自分も何かをしなければと気持ちにかきたてられた。野望と希望と不安が、たえず高島ら若者をかりたてていた時代だった。そんな長州藩萩では、画を描くというのは男の仕事ではなかった。だから高島は、画家になる気持ちは全くもっていなかった。画をえがくのは教養のひとつであり、それは余暇の一環と考えていた。余暇だから楽しいのだと彼は思っていた。
彼は兄張輔が羨ましくもあった。父の跡もつがず、自分にふさわしい学問の道を選び、明倫館の教師になっていた。静かでおだやかな世界、それは兄張輔にふさわしい世界だった。
高島の迷いに関係なく、明治2年(1869年)になるとさらに状況が変化した。
大村益次郎がフランス式の兵制にのっとって初めて徴兵制度を採用しようとした。その手始めに自藩の長州から兵を募ることになった。ところが大村益次郎は、その翌年の9月京都で刺客に襲われ、11月、それがもとで大阪の病院で死亡した。兵制改革によって明治2年の冬から翌年にかけて脱隊兵の暴動がおこった。この暴動鎮圧のため、高島ら明倫館の藩校生徒が駆り出された。その時の体験で高島の気持ちはかたまった。高島は乃木と同じように自分も軍人になろうと決心する。
当時、大阪陸軍所は「元常備軍」と新しい志願兵とで構成された長州藩出身の出向組でなりたっていた。その出向組の中に高島は所属していた。海軍はイギリス式、陸軍はフランス式だったので、高島はフランス式操兵練習をうけ、初めてフランス語なるものに接した。
このフランス語への道が、高島の運命をかえることになるのだが、それはもう少し後のことになる。
高島は萩から目の治療のために大阪にやってきた兄張輔を浪速花見物に案内する。大阪の郊外の箕面の滝を見物し、久しぶりに滝のスケッチをする。兄は24歳、弟は20歳、わずか1年ぶりの再会なのに、まるで長いこと会ってなかったようにふたりははしゃいでいた。
兄弟は双子のように何をするにも一緒で仲むつまじかった。父親の再婚を機に、兄弟の絆は深まり、それは高島の生涯をつうじて変らなかった。
明治4年、同郷の乃木が陸軍少佐になったのを聞くと、高島は焦った。ところが現実は、全く違った方角から彼に方向転換を迫ってきた。
大阪の兵学修業を終えた高島は、軍人志望者がすすむ幼年学校を受験したが、落第してしまう。試験の成績ではなく年少者から優先して採用されたためだった。
軍人の道をあきらめた22歳の高島は、明治4年、上京して「築地居留の欧人」についてフランス語を学ぶ。これからの日本は、外国語が必要になると感じていたからだ。その背景にはひそかに洋行への野心があった。吉田松蔭が命がけで外国に行こうとしたことを自分はなしとげたかったのだ。同郷の先輩、井上馨、山尾庸三、伊藤博文、品川弥太郎ら、明治の指導的立場にある人達はすべて洋行帰りだった。洋行帰りには、軍人の勲章以上の価値がある。高島は自分の野心に興奮していた。
萩出身の井上馨の推薦で工部省へ 生野銀山に赴任 フランス人コワニエと出会う
その野心に一歩近づいた。明治5年8月、23歳の高島に工部省鉱山寮への指令がでた。工部省管轄の生野銀山で、お雇い外国人のフランス人コワニエのもとで、地質学とフランス語を学んでくるようにという指令だった。
工部省は明治3年に創設されたばかりだった。その中心人物が、幕末、藩主黙認のもとにイギリスに渡った井上馨、井上勝、伊藤博文、山尾庸三らだった。イギリスの産業を視察した彼らは、イギリスと日本の共通性をみて、早くからイギリスのような工業立国の理念をもっていた。明治維新で要職につくや、彼らは工業化の問題にとりくんだ。その最初の仕事が工部省の創設だった。以後、工部省は長州閥の拠点となる。
高島はその第一弾というわけだった。当時、大蔵大臣だった井上馨の力が働いていた。
萩出身の井上馨は「今清盛」といわれるほど隆盛をきわめていた。高島が終生この井上馨の後押しでチャンスをものにしていくことになる。井上は背が高く物腰がやさしい素直な高島を、絶対的な自分の配下にすることで、ライバルたちから身を護ることにしたのだ。
明治時代は、薩長の時代である。萩で生まれた高島は、人生の最初から時代の大きな波に乗っていた。