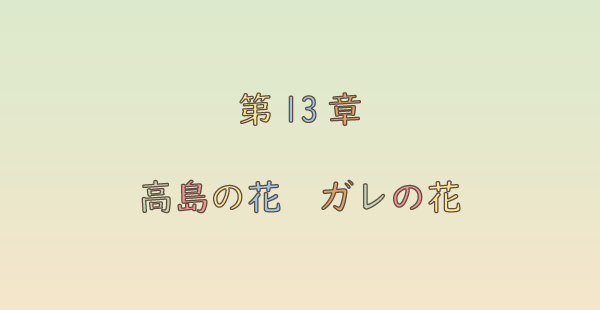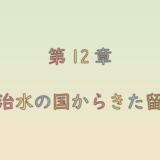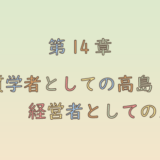日本初の植物辞典「植物名藳(めいい)」をガレに貸す
1886年の初夏、ようやく異国での生活の輪郭ができてくる。
高島が、かねてからエミール・ガレから頼まれていた「日本植物名藳(めいい)」をもってガレンヌ通りのガレ邸をおとずれたのも、この頃だった。
ガレは、ナンシー・アルチスト誌の編集室で高島の日本画をみてから、高島の作品をみたがっていた。彼は会うたびに日本の花の話題をし、ルイ・エストーを通じても高島の作品や日本の植物に関する本を持っているなら見せてほしいと言っていた。
高島が、エストーの編集室で日本の植物図鑑について触れたのをガレは聞いていたからだった。この「植物名藳(めいい)」とは、東京大学助教授の松村任三の編纂による植物の学名と和名を書いた一覧である。日本には5000種の高等植物が自生しているが、その学名と日本名を一対にした総覧で、日本で初めての植物辞典だった。1884年2月に丸善から発行されたばかりの201ページからなる植物辞典を、高島はエジンバラの森林博覧会に参加するため出来立てほやほやの本を持参したのだった。
高島は「植物名藳」のほかにも全国の森林をまわって植物帯調査をしたとき、部下の田中壌と丸山宣光の3人によって作成した樹木図の本を持参している。
3人は明治11年3月21日、伊豆国の官林調査を皮切りに全国21余県を6年の歳月をかけてまわり、日本の植物帯を作成した。3人とも絵心があり、田中壌は日本洋画の鼻祖といわれる高橋由一の天絵社の幹事であった経歴を持っていた。また丸山宣光の方は、樹木図作成のため、高島・田中の所属にまわされた男で、本職の画家級の腕をもっていた。高島は、この植物名藳(めいい)のことを「ナンシー・アルチスト」誌のオーガンにも語っており、オーガンは「高島氏の思い出」の中に書き残している。
「高島氏は、森林図の作成作業と平行して“日本における樹木の植物の種類の分布についての報告”と題して豪華版の定期刊行本を出版した。これは、高島得三著、東京、省庁直轄印刷所出版とされていた。 ~中略~ この全集は450枚の白黒、また色彩入りの石版画で挿絵されることになっていて、現在までに150枚がすでに出版されている。高島の仕事を熱心に手伝ったのは、大変な腕利きで石版画の技術に熟練した丸山という画家であった。
丸山は、この重要な作品の構成、印刷を自ら手掛けた。印刷部数は各200部に限られ、政府管轄の学校に独占的に配布されただけである。各々のデッサンには、各植物の一般的な特徴が記述された文面が加えられている」
(ナンシー・アルチスト誌 1888年5月18日号)
翌日、学校から帰るとアパルトマンに1枚の名詞がはさんであった。
「エミール・ガレは高島氏のご訪問時に不在であったことをお詫びいたします。彼は狩りから帰って植物名藳(めいい)をみつけ、大層よろこんでいます。それをもう数日お借りできれば幸せです。高島氏が、ラ・ガレンヌにお越しになれば、いつでもE・ガレは歓迎します。彼は菊の国についてたくさん質問することがあります」
名刺の裏にまでガレの文面はぎっしりと書き込まれていた。
園芸協会の例会に招待された高島
ガレと会ったのは園芸協会の月2回の例会だった。会員たちはこの日の話題を日ごろからため込んでいた。
「どういうわけか着実に実を結ぶ植物の花は美しくないですな。西瓜とかナスとか。この牡丹のように種子なんかみたことがない花が、鮮やかな花を咲かせる」
園芸家のクルースは、七分咲きの牡丹の花弁に触れて、いとおしそうにいった。
高島とガレ、プルーヴェ、マジョレルの4人は、雪洞のように明るい白い牡丹の周りに集まって、花をのぞいた。
「種子ではふえにくい牡丹やバラも、人間の眼や、違う種族の生き物をひきつけ、接木だの挿し木だのと手を借りて生き延びているわけですから、結局同じことじゃないですか」
大工のようにがっちりした小柄なプルーヴェは腕を組んで花を見ながらいった。
「一見、徒労のように見える鮮やかな花もそうやって子孫をふやしているのですな。植物の知恵でしょう」
クルースはプルーヴェの指摘にうなずいた。
「それじゃ、水仙のような花はどうなりますか。球根でふえるのに、なぜわざわざ花を咲かせるのでしょう」
高島が質問すると、それは簡単なことだと言わんばかりにガレが答えた。
「水仙やチューリップは、花の咲き終わった後に種を作っています。この種は、球根に万が一のときを考えて種を作っているのです。二段構えで子孫に受け継いでいこうとする用心深い花ですよ。園芸家が新種を作るのは、この種を掛け合わせるのです。球根からは同じ種類しか咲かないが、例えば黄色のチューリップの横に白いチューリップを植えておく。するとそのチューリップの種は、黄と白の縞模様の種を作るのもある。花というのは、私たちが考えている以上にしたたかで強靭です」
「そうです。女性のように強い」プルーヴェがまぜかえした。
「それに世話がやける」と、クルースが言った。
「いや、世話のやけない花もあるでしょう。カーネーションなど、2年に1回植え替えればいい」とガレは言った。
「おや、花の中に何かいますな。てんとう虫かな」
さっきまで黙っていたマジョレルが、牡丹の白い花弁に指を入れた。てんとう虫は、折り重なる花弁の中で、香りと蜜に酔ったように動かない。
「幸せな奴だ、この虫は。私もこんな風にして一生を終えたい」
ガレが言ったので、クルースが
「おやおや発展一途のあなたがそんな風におっしゃるとはね」
と、半分揶揄するように返した。ガレが7月にパリのプチィット・エキュリにある支店をリッシュ通りに移すことを知っていて言ったのだった。ガレが、1886年の春からパリ支店の移転のため、パリとナンシーの間を忙しく往復していることは、園芸仲間に知れ渡っていた。
園芸趣味は金持ちの象徴、ガレもそのひとり
しかし花のことになるとこまめに園芸協会に顔を出し、園芸家の庭に新種の花が咲いたというと恋人に会いに行くようにいそいそと出かける。今回もフェリックス・クルース(1840~1925)の庭に新種のアフリカ産のベゴニアが咲いたというので、園芸仲間が集まったのだった。
高島はクルースを森林学校のフリッシュ教授に図書館で紹介されて知っていた。しかしクルースの家に招待されるのは初めてだった。クルースの家は豪邸だった。ヨーロッパの王侯貴族が自分の権力を誇示するために壮大な庭園を造ったように、園芸は金持ちの贅沢の象徴だった。
クルースの専門は、牡丹、アスター、水仙、ベゴニアだったが、特にベゴニアの交配による新種作りで知られていた。牡丹やベゴニアは酸性の土壌のほうが適している。国土の55%が石灰質のアルカリ土壌のフランスでは何か土に工夫がいるはずだった。4人は牡丹の畑を見ながら、ベゴニアの温室に向かった。
高島は淡いピンクや鮮やかな朱鷺色の牡丹の種類の多さに視線を忙しく走らせた。薄紫色や深紅色の牡丹が、繻子のような光沢の花弁を開かせ、濃密な香りを漂わせていた。それは、手の込んだソースをかけたフランス料理のように豪奢だった。ただ花は、日本のものに比べるとやや小ぶりで、茎が細いので不安定な感じを与えた。そのことを言うと
「そうなのです。大輪の花をさかせるには茎を太くする改良が必要です。ルモワンヌ氏もそれを研究している」
クルースは歩きながらいった。そして思い出したように尋ねた。
「高島さん、日本にも黄色い牡丹、ありますか」
みたことがないというと、
「それじゃ、一度ルモワンヌ氏の所に行ってみることをすすめます。あの人は、黄色の牡丹を作ったのです。ルモワンヌ氏の牡丹園は、こんな比じゃありませんよ」
クルースは付け加えた。高島は、森林学校の図書室でみた額の広い年配の男の顔を思いだした。
中国原産の牡丹がヨーロッパにもたらされたのは18世紀に入ってからである。ルモワンヌは、牡丹を交配させ、レモン色の牡丹を作り上げた。それは現在も「レスペランス(金帝)やクロマテラ(金鶏)」の名で残っており、P・コーツ著「花の文化史」にも牡丹の章にルモワンヌの名が載っている。
牡丹畑が終わると、水仙畑が続いていたが、すでに水仙は葉だけになって、風が吹くと緑の波を作っていた。その後にガラスの温室が建っていた。それがべゴニア館だった。
5月の終わりの温室は、むせかえるような香りで、息をつめた。花の香りと肥料、太陽のこもった熱が混ざり合っていた。階段式になっていて、鉢植えのベゴニアが、まるで行進する娘たちのように整然と並んでいた。赤と白、ピンクのベゴニアが、色の縞模様を作り、よくみると花の大きさも葉の色も微妙に違っている。
アイアンクロスという種類のベゴニアには、葉の緑に十字が入っていた。一重、八重のベゴニアが、少女の頬のようにやわらかな花弁をつけていた。低木のベゴニアもあって、その種類の多さが高島を驚かせた。世界には400種類あるが、そのうちの300近くあると、持ち主は誇らしげに言った。
4人は、鉢植えのベゴニアを手にとったり、花に顔を近づけたりしていた。
「これが、南アフリカ産のものと交配させた花です」
クルースが手にとった鉢は、白い蝶が重なり合って止まっているような白の花弁のベゴニアだった。
「この美しさには、威厳がありますね」
「人間もまた、この花のように優性遺伝させられないものでしょうかね。子供というのは、どうして親のいやな性格だけを受け継ぐのでしょう」
「全くです。花は改良によってどんどん美しくなっていく。人間は駄目です」
男たちは、白の大輪のベゴニアをめぐって勝手なことを言い合って、その花の美しさをめでた。女たちが宝石を眺めるときのように、光にすかしてみたり、真上からのぞいてみたり、ベゴニアは香りの少ない花なのに、鼻を近づけたりした。なにか美しい少女を何人もの男がなぶっているような淫らささえ感じさせた。ガレは、マジョレルから手渡されたベゴニアの鉢を手にとって、その白い花弁を凝視し、網膜に焼き付けていた。高島には、ずいぶん長い時間に思われたが、実際は1分ぐらいのものだった。
『まるで視姦しているような眼だ』
高島はふとガレの閨房を覗きみたような厭な気がしたが、その時、ガレのガラスの花瓶は、もしかして芸術的に高い価値を持っているのかもしれないと思った。人は相手の存在感に圧倒されて、相手の価値を見つける場合がある。このときの高島がそうだった。
高島には、エミール・ガレという男がよくわからなかった。花に対しての狂おしいまでの情熱、薩摩ガラスなどの美しさとはほど遠いガラスの花瓶を作り、周囲から高い評価を得ていること、経営者としての抜け目のなさ、そういったディテールがすべてわかっているのに、ガレその人はみえてこないのだった。きれいに揃ったトランプのカードに中にジョーカーが混じってしまったために、一つの秩序が組めないのに似ていた。しかし存在感はあった。迫力はあった。わからないけれど無視できないものがあった。ただ明確にわからない人間は、心から安心してつきあえない。高島は、最初に出会ったときの握手の感触を思いだした。
『この男とは、どこまでいってもすれちがってしまうのではないか』
高島は、鼻梁の整ったガレの横顔をみた。ガレはベゴニアに寄せられた昆虫だった。クルースもプルーヴェもマジョレルも、園芸好きの人間というのは、花に集まる蝶や虫に似ていた。花を求めて触覚ならぬ視線をはりめぐらせている。収集によせるマニアックさは、それに関心のない者には実に少年じみて、稚拙にみえる。クルース家に招待されているとブランシュに言ったとき、
「男の方の収集癖というのは、私たち女性にはわからないものの一つですわ。なぜあれほど躍起になって世界中のベゴニアを集めようとするのか、それがどんな役に立つというのでしょう」
ブランシュはレッスンの後でコーヒーを飲みながら悪戯ぽく笑った。
「しかし女性だって、宝石をコレクションするでしょう」
「もし宝石に高い価値がないと知ったら女性たちはただきれいなだけのガラス玉を子供の玩具にでもやってしまうのじゃないかしら」
高島は、ブランシュの言葉を思い出して、確かに収集という習慣は、男のものかもしれないと考えた。
ガレは蜜を求めて飛ぶ虫のように温室を歩き回り、クルースに質問している。温度は、水の量は、肥料はと執拗に尋ねているガレをみると、この男は自分が考えているほど複雑な人間ではないのかもしれないと思えてきた。
東京の「朝顔市」に驚くガレたち
一同はベゴニアを見てまわると、クルース家の食堂に案内された。
食事中にも高島は、日本の花について質問を受けた。ベゴニアは日本にも「秋海裳しゅうかいどう」と呼ばれているが、クルース家の温室にあるほど種類もたくさんではないし、花も地味だというと、全員はひどく満足した。
高島は、そうやって彼らを持ち上げておいてから、日本の牡丹の花の大きさについて話した。話題は、花の大きさから日本人がいかに大輪の花を咲かせるのに熱心かという話に発展した。
「ナンシーの野原にもさいているでしょう、こんな花が」
と、言って高島は持っていたメモ帖に鉛筆で朝顔の花を描いた。単語が分らなかったからだ。
「ああ、リスロン(昼顔)」
と、隣の席のプルーヴェが言った。
「日本ではリスロン祭というのがあるのです」
と言い、東京、入谷の朝顔市の話をすると、ガレの眼が輝いた。
「そんなに大きな花がさかせられるのですか。日本のリスロンの種は大きいのでしょうか」
ガレは身を乗り出して聞く。
「ナンシーのリスロンの2, 3倍はあるでしょう」
高島の言葉に、全員はおあずけを食った犬のように口をあけた。
「ぜひ、日本から取り寄せてもらえませんでしょうか。もちろん費用はだします」
ガレはなかなか強引だった。高島はガレ工房を訪れたときにも頼まれたので、今度は逃れられず、承諾した。ガレは急に陽気になった。その単純さに高島も嬉しくなって、その場の座興に生け花を披露した。
高島は庭に咲いていた雪柳とアスターを切ってきて、クルース夫人に頼んで台所から花器の代わりになる大鉢を借りた。針金と小石で剣山を作り、雪柳の下に白とピンクのアスターを添えた。
「日本人はなんとエレガントなのでしょう。こんなふうに花をアレンジできるなんて」
今まで花瓶に盛るように活けていた人達にとって、少ない花でつくりあげた造形美は眼を見張らせた。
「この花の生け方は、日本画と似ている。とてもうまく空間を利用している」
ガレはいち早く生け花の特徴をつかんで指摘した。皆もうなずいた。絵画のほかに彫刻も手掛けるプルーヴェは
「三角錐の変形を作るのが基本かな」
と、彫刻家らしく眼で生け花の定理をみつけようとした。
人々は生け花の周りに集まって、花器に活けられた小さな創られた自然にみとれた。
「花の生け方ひとつにも、日本人は自然ということを考えるのですね」
ガレは、日本人の自然に対する傾斜の深さに、自分と通じるものをかんじているらしかった。
「高島さん、この次は私にも日本の“生け花”を教えてください」
クルース夫人が目を輝かせた。
意外に大きな反響に、高島は面映いおもいをしながらも気分はまんざらでもない。この生け花ですっかりクルース夫人に気に入られた高島は、クルース家にいくたびに生け花を教えることになった。
「日本の生け花は、花は少しですむし、日持ちがするので経済的です。冬はお花が高いですもの」
と、夫人は感謝した。造形美とは全く関係のないところで、生け花が評価されて高島は苦笑した。後年、高島は自分の画室にも自ら花をいけた。特別に習ったわけではなかったが、画家だけに生け花の腕は素人の域を抜いていたという。(高島の5女 園子さん談)
高島はナンシー滞在中、クルース家をしばしば訪れ、クルース家に集まるナンシー芸術家と交流を深めた。
「クルース家は、エミール・ガレ、フレール・マジョレル、ブッシェール、グルベール、プルーヴェなどナンシーの芸術家を愛想よくもてなした。特に珍しい花、ランを必要としていたエミール・ガレを、フェリックス・クルースは快くいつでももてなした。
画家のグッサンクルーもまた、クルースと親しくし、この家でインスピレーションを得ていた。森林学を学ぶために3年間滞在した日本人学生、高島は、クルース家で家族同様のもてなしを受け、この家にやってくるフランスの若い芸術家と交流した」
(「園芸家クルース」CROUSSE HORTICUTEUR 1888 ナンシー植物園所蔵)
現在、クルース家はない。彼が持っていたベゴニアの広大な温室を記念して、クルースのあった家の前は“ベゴニア通り”と名付けられ、その名を残している。
ナンシーの森でラン探し
この日、クルース家でラン探しに行くことが決められた。ランには目のないガレが言いだしたのだった。
「来週の日曜日です。皆さんいいですか」
ガレがこの家の主のようにいったので、マジョレルは
「ガレさんの方こそ大丈夫でしょうな、パリの支店には行かなくていいのですか」
と覗き込んだ。ガレは痛いところをつかれて、情けなそうな顔をしたので、一同は笑った。
「やれやれ花に捧げる我らの命ですか」
クルースが言うと、ガレは
「女に捧げるよりましでしょう」と反論した。
「女も花も時間と金が必要です」
「珍しいランを見つけるのは、美人をみつけるよりむずかしい。僕たちは幻を求めているところがある」
ガレは突然能弁になる。
「それにランは自分の庭に根付いてくれません。美人よりランは気難しい」
クルースが加勢する。男たちは花に魅せられることでいかに虚しい努力をしていて、それが愚かであるかを口にしながら、自分たちの愚かさを競っていた。中年のむくつけき男たちが、たかだか1本の花に躍起になるのは少々こっけいですらあった。そのことを高島がはっきりと感じ取ったのは、クルースやガレと共に“エ”の森(FORET DE HAYE)に行った時だった。
“エ”の森は、ナンシー北西部に拡がっていた。新緑の季節がすぎ、緑が少し重たくなりかけの6月の初めだった。園芸協会の会員たちは、森のそばまで馬車や馬で行った。どの男も狩りにいくような格好をし、猟犬のように興奮していたが、誰も口数が少ない。しゃべらない分だけ昂揚感が伝わってくる。手に植物採取の小型のスコップや袋を持っている。
森に入ると、彼らは猟犬が獲物の匂いをかぎまわるように視線を走らせる。彼らは落し物をさがしまわっている人のようで、その姿はこっけいだった。
高島はクルースの後ろからついていった。ランは陽のあたらない湿地に咲いていると教えられた。“エ”の森のランの開花期は5月中旬から6月にかけてだった。森のところどころに鹿や猪、兎のための餌が置いてあった。秋の狩猟のために餌付けしているのだ。
クルースの少し前をガレが行く。犯人を追い詰めていく警察犬のように彼は用心深く丹念にどんな小さな花も見落としまいとする。
下草の少ない森には、ドイツ鈴蘭がまだ咲いていた。ショージョーバカマに似た花が咲いていたので、高島は前を行くクルースを呼び止めた。するとガレも獲物をみつけた犬のように飛んできた。クルースがていねいにピンクの花を掘るのをガレはしゃがみこんで見守っている。子供同士で悪さをしているようである。
そして歩き出した高島のもとに風のようによってきて
「この次は、私にも教えてください」
と、ささやくとさっと離れた。高島は、後ろに手をまわしてガラス工房を見て回っていたガレの姿を思い出し『まるで別人格だ』と思った。男は誰でも大きな少年であるけれどガレの場合はそれが極端だった。少年の部分と経営者の部分が、まるで花と葉のように分かれている。しかし花は葉の進化した部分であることを思うと、彼の子供じみた熱狂の方が根本にあるのかもしれなかった。
『この男はなにかが過剰すぎる』
高島はそう思いながら、背を丸め、いじましく花を探しまわるガレをみつめた。高島は何かに淫するということに価値を認めないタイプの人間だった。医者の息子であり、鉱山学、植物学を学んだ彼には、常に対称を冷静にみつめるという習慣がそなわっていた。彼の場合、感情が優先するということを避けていた。医者の家に育った高島は、どんなときも患者に対して冷静である訓練を幼い頃から身につけていた。彼は好悪をあからさまに表現することをはしたないと思っている江戸時代の儒教の教えを受けて育った。だから大の男が、花ごときものに躍起となることをどこかで気恥ずかしいと思うこころがあった。花は女がいじるものという概念があった。
ただクルースやルモワンヌの場合は別だった。二人はガレと違って新種の花を作ることを職業にしている園芸のプロだから、それが許されると高島は思っていた。
高島がそう思うのも無理ないところがあった。ガレは花といえば節操なく、なんでもかんでも好きという漁色家めいたところがあった。芸術家にとっては、過剰なものだけが創造のエネルギーとなる。ガレは、マニアックなまでに花への情熱を、工房の作品の中でしっかりと花開かせていたのだった。
“エ”の森で採取したランを、ガレは性格にスケッチし、作品の中に使う。ラン好きの者には作品に使われたランが、ロレーヌのどの地方のランなのか、その名前まで指摘できるのだという。
「ナンシー派の中のラン」というグラビアの本を夫婦で著した園芸家のペルティエ夫妻は、一枚の薄紫の花をつけた地味なランの図をみせ
『このランは、森の中で少し花茎が曲がって咲くのです。ガレは、このランを机の脚のモチーフにしていますが、花茎の曲がり具合をそのままデザインの中にいかしているのです』
と説明する。花茎のくびれと机の脚の曲がり具合がなるほど一緒である。そして薄紫のランが、ロレーヌ地方ではめったに見られない珍種であると付け加える。
ペルティエ夫妻は、ガレやポール・ニコラ、家具デザインのウージェンヌ・バランが毎月1回、ラン探しに出かけていたことや、ラン探しにどれほど夢中だったかをバランの娘から聞いている。
「ふだんの日でもガレは森を歩くと、ランはないかと落ち着きなくキョロキョロしていたと、バランの娘は言っていました」
と、ペルティエ氏はいう。そういうペルティエ氏も本業は医者で、ラン好きがこうじて「ナンシー派の中のラン」を著したのだった。
ガレがどれほどラン好きであったかは、ポール・ニコラと共著で1900年のパリ万博の中の園芸国際会議に「ロレーヌのラン」という研究書を発表していることでもわかる。ロレーヌ地方のランの種類や形について述べたもので、ランの細密画が載せられている。細密画は、ランの正面、サイド、後方からの3つの角度から拡大してとらえられ、B4版の中に17図が丹念に描かれている。
ガレはロレーヌのランばかりか熱帯のランもこよなく愛した。熱帯のランは、18世紀イギリスが南方から持ち帰った物が貴族の間で愛好されて広がった。
ガレの時代には、園芸家たちは競って「高温に弱い」「花もちが悪い」熱帯ランの弱点
をカバーする新種の改良に励んだ。そしてその花は金持ちの間で珍重された。冬は零下10度に下がるナンシーの過酷な風土に暮らすガレたちナンシーの園芸家にとって花への思
いは日本人と異なる。ヨーロッパ人にとって花はブルジョワのものだった。王侯貴族が権力の象徴として庭園を造ったように。ナンシーの園芸家にとって自然豊かな国からきた高島はまさに黄金のジパングの人だった。ガレは、自然への畏敬の念をもった日本人の考えに賛同し、新しい世界観をみつけたのだった。
傑作「カトレア」にガレは何を描こうとしたのか
ガレは、1880年代の作品のモチーフにランを使うことは少ないが、1900年に入ると急に増える。1900年のパリ万博出品の作品はロレーヌのランばかりか、カトレアをモチーフにしたものがきわだって多い。80年代に興味をもったモチーフを1900年になってようやく結実させることができたのだった。
モネの“睡蓮”が晩年になればなるほど形を失ない、狂おしい花になっていったように、ガレのランも晩年の作品ほど圧倒的な迫力をもって見る者に迫ってくる。
1900年にパリ万博に出展された「カトレア」は、ガレの晩年の傑作であるが、そのピンクのカトレアは完全に腐って咲いている。真正面からとらえられたカトレアは、葵色の花瓶に蛸のようにからみついている。北斎の海女にからみつく蛸を連想させる。花弁はねっとりと腐り、変色する一歩手前である。これがガラスでできているとはとても思えない。ゴムいり粘土のようにカトレアは腐っているのに弾力性がある。ピンクのカトレアに取り巻かれて、花瓶は赤紫色の悲しみの中に沈んでいる。花瓶の入り口がわずかに色が薄く、そのところでようやく素材がガラスでできていることがわかる。花は病んでいる。病むことによって花瓶のカトレアは異様な熱をおび、見る者の視線をとらえて離さない。ガレと交流があった世紀末の作家、ユイスマンスの小説「さかしま」の主人公がランをみて悪夢に襲われる一説を連想させる。
『不意に彼は覚るところがあった。この女は“花”だと彼は思った。悪夢の中までしつこく彼についてまわる推理癖は、昼間のあいだと同じく、やはり病原菌の繁殖に源をはっしているのがわかった。
やがて彼は、女の乳房と口に物凄い炎症があらわれ、胴体の皮膚に黒ずんだ褐色や胴色の汚点が見え出した ~中略~ そのとき、彼の血走った目には、女のむきだしの股の下から猛々しい“ニドウラリウム”の咲き出るのが見えた。“ニドウラリウム”は血を滴らせながら、剣の刃のごとき葉身の内側にぽっかり黒い孔をあけた』
(ユイスマンス著「さかしま」)
ガレもまた「さかしま」の主人公と同じようにランの中におぞましい女体をみていた。この「さかしま」のモデルが、当時のパリ社交界の花形であり、ガレのパトロンでもあったモンテスキュー伯爵であることは、偶然の一致ではない。
ガレと彼の支援者モンテスキュー伯爵の関係
モンテスキュー伯爵とガレは短い交際期間の間に百通以上の手紙をやりとりしていた。モンテスキュー伯爵が男色家であることはよくしられている。しかしモンテスキュー伯爵とガレとの間に友情以上のものがあったことを証明することはむずかしい。
ただモンテスキュー伯爵が熱烈なガレのファンであり、ワーグナーの音楽を愛するガレに、コジマを紹介したのもマルセル・プルーストを紹介したのもモンテスキュー伯爵である。この伯爵自身がガレと同じように花好きだった。伯爵の庭には「魅力的なハタさん」という日本人の庭師がいたくらいである。ジャポニザン(日本趣味)であったモンテスキュー伯爵が日本の日傘をかざした写真が残されている。
ガレとモンテスキュー伯爵との間には、いくつかの共通点があった。伯爵をモデルにした「さかしま」の主人公が、珍種の花を収集し、花に熱い情熱を注ぎながらも、夢の中でランの花におびえるように、ガレもまたランが象徴する女性におびえを持っていた。
『カトレアは女性なのです。花瓶はガレ自身で、女性にまき付かれた自分を表していると思います。ガレは女性に対して憧れと同時にひと一倍恐れをもっていたのではないでしょうか』
「ナンシー派の中のラン」の著者、ペルティエ夫人は、ガレと花の関係をそのように分析する。
ガレにホモセクシャルな性癖があったかどうかを実証することはできないが、ただナンシー植物園長のブーランジェ教授は
「ガレはナルシストだったと思います。彼は手紙をだした人々の名前を丹念に記録しており、自分に関心をもってくれる人間に対して普通の人々以上に敏感な人だった」
と言う。
ガレや友人のモンテスキュー伯爵、ホモセクシャルな作家マルセル・プルーストらは、女性に対する憧れが過度であり、母親への傾斜が強すぎる男たちであった。ガレが一人っ子であったことも影響しているのかもしれない。
ランに女性をみたガレは、バラには何をみたのだろうか。バラもまたガレが熱愛した花のひとつである。
『バラ園のバラは愛らしい。バラは生け垣や(女性の)胸や指先にあってほしい。鉢の中で葉を摘まれると、この上なく魅力的である。
しかしバラが布地の端切れのように扱われるのをみると苦痛である』
(ガレ著「芸術ノート」)
ガレは園芸論文に、バラの扱い方、バラの新種について長々と書いている。そしてバラを「樽詰めのニシン並みにぎゅうぎゅう詰めに飾りたがる大衆にまかせてはいけない」と言い、「死んだ蝶々のように箱に入れられたしみのついたバラの花を前に抗議する」と憤慨する。ガレの「芸術ノート」の文体は、やたら修飾語が多く、華美である。文は人なりというなら、この文章からガレは意外に内面は気難しい耽美派ではなかったかとおもわせる。
しかしガレのバラの花瓶は、彼の文章よりずっと明解で、彼の文章以上に文学的である。
ガレのバラは、女王のように誇らしく咲いてはいない。三分咲きのつぼみは、ぐったりと首をたれている。「薔薇文香水瓶」のバラも「フランスのバラ」も同じように病んでいる。つぼみのまましおれたバラもある。
ガレは、孫のジャン・ブルゴーニュ氏が指摘するように「花の中に文学的な意味を託した」芸術家だった。
ガレ自身は「バラ」に関する小文の中でヴィクトル・ユーゴの詩に仮託してバラを語っている。
「バラの問題に対して、詩人はいつも同じ答えを出す。ユーゴは、直ちにこう書いた。
“女の肉!理想の粘土!おお驚異!
そして より精妙に
一輪のバラが私に告げる 聖なるものと
私は答える 愛と!”ゆえに新種の(バラの)形態をあたたかく歓迎しょう」
(ガレ著「芸術ノート」)
ガレにとって、バラはカトレアと同様に女性の肉体への強い興味と恐れ、不安を表すものだった。つぼみのまま枯れてしまったバラに、彼は甘味な死を詩的に盛り込んだ。ラファエル前派のジャン・エバレット・ミレーが、入水した「オッフェリア」を克明に描きあげ、死もまた生の強烈な証であることを描いたように。
園芸家ガレは、あらゆる花を陶器、ガラス、家具のモチーフに使うデザイナーであった。その中で、カトレアとバラと共に忘れてはならないのが、ウイキョウである。
ウイキョウはセリ科の多年草で、草全体に芳香があり、高さ1メートルから2メートルにまで伸びる。夏に黄色い小花がパラソル状に咲く。芳香材であり、これから香油もとれる。
ナンシーにこの花が渡ったのは、1810年から90年頃にかけてで、アルメニアやコーカサス地方からもたらされた。ガレにとってウイキョウは、ランやバラとは違う造形的な美しさをもっていた。夜空に打ち上げられた花火のように放射状に広がる小花は軽快で明るく、デリケートだった。デリケート、これがガレの好みにあっていた。
ガレ工房にもお化けウイキョウといわれる背の高いウイキョウが植えられ、ガレはこの花を家具やランプ、花瓶のモチーフに使った。レースを広げたようなウイキョウの花は、ランプの傘に使われたとき、その美しさを最大限に発揮した。明かりが灯ると、ウイキョウがレースの日傘を広げるのだった。ガレは造形的に複雑な花が好きだった。
彼は自然がつくった花のデザインをデフォルメして使うことを全くしなかった。彼は偉大な自然が作り上げた造形美に手を加えることができなかった。園芸家としての彼がそれを許さなかった。ガレの徹底した写実主義は、植物だけではなく、昆虫にも及んだ。
ガレと家具デザイナー、マジョレルの共同作品で、ガレの家具部門の最高傑作といわれるベッド「暁と黄昏」は、蛾をモチーフに使っている。
ベッドのヘッドボードには、一匹の蛾が大きく羽を広げ、その下に暁の田園風景が寄せ木(マーケットリー)でほどこされている。そしてベッドの後板は、2匹の蛾が向かいあって二匹の腹にはヒスイに似た石がはめこまれている。豪華なベッドである。
ベッドボードにデザインされた蛾は、実際に朝方に活動する蛾であり、後板の蛾は夕方にしか飛ばない蛾である。ガレはベッドに朝と夜を象徴する2種類の蛾を使ったのである。この傾向は、花瓶に使われたトンボやハチについても同じことが言える。昆虫学者なら即座にその名前がいえる。
アールヌーヴォーの作家たちは園芸愛好家だった
アールヌーヴォは花の様式といわれるほど花をモチーフにしている。ナンシーでフランスのアールヌーヴォが大輪の花を咲かすことができたのは、作家たちが園芸家であったことが大きい。画家プルーヴェ、ウージェンヌ・バラン、ポール・ニコラも全員ナンシーの園芸協会の会員であった。彼らのそばにいて、園芸熱を刺激したのが、遠く日本からきた高島だった。この男は、ふたことめには
「日本では、こんな花があるのですよ」
と、鉛筆でいとも簡単に花の絵を描く男だった。しかも高島が描いた牡丹は、フランスきっての園芸家ルモワンヌが金をかけ、苦労して育てた牡丹の花よりも大きいのだった。彼らはうなってしまう。くやしくもある。しかし日本人が嘘をついているとは思えない。なぜなら彼の描く牡丹や菊、あやめも実に正確であることが、園芸家の彼らにはよくわかっているからだ。4月には桜を見にピクニックに行く日本人、5月にはあやめを見に行き夏には朝顔市がたち、秋には菊の祭りがあると話す高島に、彼らは素直に共感する。極東の国に、自分たちと同じ花好きの民族がいることに好感と安らぎさえ覚える。
高島が森林学校の留学生でなく、漢方医の息子でなかったら、園芸家のガレたちはこれほどまでに高島をていねいにもてなすことはなかっただろう。彼らにとって、高島は人種こそ違うが仲間だった。そのうえ日本の昼顔の種まで取り寄せてくれる親切な友だった。
「ガレ氏の迷宮(のような庭)に、自分の国の植物を再現させられるのは高島氏しかいない」
(ナンシー園芸中央協会報告書 “BULLETIN DE LA SOCIETE CENTRALE D’HORTCULTURE DE NANCY”)
その報告書は、また次のような記事も載せている。
『園芸界の旗手、ガレ氏は珍しい植物の種類をもっている』
“ガレ氏のlabyrinthe(迷宮)”といわれるほど花に執着したガレ。ガレの迷宮のような庭園の花々は、彼の作品の中で永遠の生命を得て咲き誇った。
花への異常なまでの情熱が盛り込まれたガレの花
高島も53歳で画家になってから、花をモチーフにした作品を数多く残す。花によって結ばれた二人であるが、高島とガレが描いた花は大きく異なる。
『植物の詩的な部分にガレは興味を持っていた』ガレはランやバラ、菊に自分の思いを託した。ガレの花は正確に精密に描かれたが、その大胆な構図や色彩、背景となる花瓶の形、色によって独特のものうい雰囲気に彩られている。
しばしば「ガレの花瓶は再現不可能だ」といわれるが、ガラス作家の竹内洪氏にいわせるとガレの作品は時間はかかるが再現できるという。では何が再現不可能かといえば「作品のもつ一種独特のあの雰囲気ですよ。モチーフの使い方、構図のとり方はガレの世界です。ドームの作品より、ガレの作品が芸術的で高く評価されるのは、ガレのもつ芸術家としての強烈な個性が作品のある種いいがたい雰囲気を創り出しているからです」と指摘する。
ガレは正確にランを写しとることによって写実をこえて自分の中に迷宮の花に仕上げててしまった。花瓶の上のカトレアは、ガレによって生命を与えられた花だった。高島の描いた花は、ガレほど個性的ではない。しかし彼もまたガレと同じように実に正確に花を描いた。
高島の「富士の裾野」の花騒動
昭和5年、高島は「富士の裾野」と題した作品を文展に出品する。
ところがこの作品は、富士山麓にない高山植物が描かれていると、ある植物学者から指摘され、一大論争を巻き起こす。
しかしその学者と実地検証をした結果、問題の花は実在し、絵の真実が証明された。この学者が牧野富太郎であるか三好学両であるか判明しない。くだんのこの作品は、高島の代表作のひとつといわれているが、現在どこにあるか不明であり、花論争のエピソードだけが残っている。
花を描いた高島の「夏草花図」は、芭蕉とアジサイ、タチアオイ、キスゲをモチーフにしている。金地の二枚折屏風に描かれた夏の花々は、日本画の伝統をふみ、気品がある。芭蕉の葉の淡い墨使い、アオイの花のピンクと紅のぼかしになった光沢のある花弁、キスゲの葉の伸び伸びした線、それは熟練の絵師の作品である。
夏の花々は、厚ぼったくもなく清潔である。照りつける太陽のもとで咲いている花々は草いきれもなく、涼しげである。しかし美人だけれど表情の乏しい女に似ている。
ガレの花には、どれも花のあえぎが伝わってくる。それは、ガレが花をどこかで女性の化身としてみていたからである。これに対して高島の花々は、上品で、毅然とし、日本画の様式に支えられている。高島の花は、花は美しいものであるという大前提の上で描かれている。彼にとって花は生々しいものを感じさせるものではなく、美しいものであらねばならなかった。彼は美しい花を描くことによって、自分の心も清らかになることを欲した。彼にとって日本画の様式美は定理のようなものだった。「心破るべからず」といった芭蕉の句の美意識を高島は信じていた人間であった。どんなつらいことがあっても、他人からどのように酷評されて、怒りが心に渦巻いているときも、形、人道は破ってはいけないと彼は思っていた。見方によっては、一種の形式主義だが、彼は形式美というものの美しさを認め、受けついできた江戸時代からの絵師の末裔であった。
日本画の伝統美がナンシーの芸術家を驚嘆させたことを知っていた高島は、自分の才能によってガレやプルーヴェ、カミーユ・マルタン等から賞賛をあびたとうぬぼれてはいない。彼らにとって墨絵の様式美、日本美術の伝統が、彼らを共鳴させたことを充分知り尽くしていた。高島は、ナンシーで日本画の様式美に対して絶対的な信頼を持ったのだった。だからその様式美をはみだすことは考えなかった。そのため高島は、正確さが真実であるかどうかについて疑問をもたないで通りすごしてしまった。彼は普遍的な、だれにでも分る言葉や色、形ではなく、自分だけの言葉や色、形で外界のものをとらえようとするとき、大事なことは自分にとって何が真実であるかを見極め、それを表すことだということに注意をはらうことはなかった。
しかしガレは自分の言葉で、なにを自分のものにするかということのみを考えていた芸術家だった。