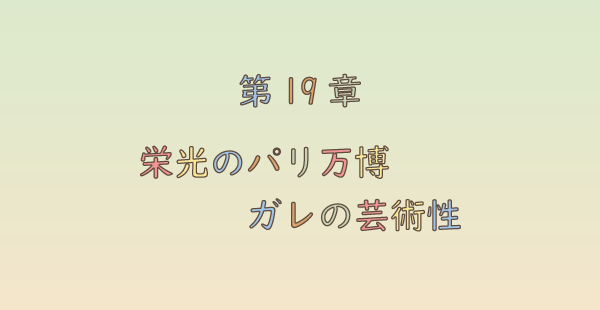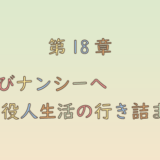異文化交流は双方の感受性が決め手
高島北海にスポットがあたる時、かならずといっていいほど「アールヌーヴォーのガレと親交があった」日本人として扱われる。ガレあってこその高島というわけだ。ナンシーのシャルパンテェ女史は「ガレは高島に出会わなくても、日本美術から美を吸収し、アールヌーヴォーの旗手になっていた」と言い切る。
しかしガレに日本の美のとらえ方の確信を与えたのは、ナンシーにやってきた高島であったと考える。外国人との出会いが、一方の人間だけに影響を与えるということはありえないからだ。ガレにとって高島は、日本的なデザインのガラス工芸品をつくるうえで得難い存在だった。二人の出会いは創作上でも経営的にもラッキーな出会いだったと考える。
ガレの芸術性は、日本文化を租借し、ガラスをこえた工芸の世界を創り上げたことである。パリ万博に出品された花器「カトレア」は、花器の正面には咲き誇るカトレアを配し、裏には黒ずんでしおれたカトレアを配して「生」と「死」を強烈に表現している。この花器にはどこにもジャポニスムや高島の日本画の片鱗はない。ガラスを彫刻したガレ独自の文学的な世界がつむぎだされている。一度見たら、この恐ろしい腐ったカトレアを忘れることができない。そこにガレの芸術性の高さがある。
成功したガレ工房の電気スタンド作品の数々
そのとき、家路を急いでいた人々は、歓声をあげ、いっせいに空を見上げた。
エッフェル塔に明かりが点いたのだった。濃紺の空を背景に、明かりの塔は夢の中のクリスマスツリーのように輝やいていた。
1889年、パリ万博を記念してエッフェルの設計によって建てられたエッフェル塔は、知識人たちの反対にあいながらも、パリ万博の大きな呼びものになった。エッフェル塔を中心にした一万の白熱灯と1500のアーク灯によるイルミネーションが、人々を驚嘆させた。新しい電気の時代の到来を告げていた。夜を昼間の太陽に変える電気は、人々の生活、産業、芸術家の作品までも変えていった。素晴らしい未来を予感させていた。
ガレは塔を仰ぎ見て、自分のカンがまちがっていなかったことを感じ取った。ガレ工房では、電気時代にそなえて、一般にも普及されだした電気スタンドの製作を始めていた。
ガレは、エッフェル塔を見上げながら、ひとりでうなずく。彼の頭の中には、万博会場のざわめきと展示してあったガレの作品をみた観客の好奇な視線が、イルミネーションのように彼の頭の中でまたたいていた。展示場にやってきた人々に熱心に説明したので、喉がいがらっぽい。万博は5月6日に始まったばかりで、これから11月6日まで続くのだった。彼は疲れていたが、全身に力がみなぎっているのを感じながら、リシェ街にある支店に向かった。
1889年のパリ万博に、ガレはガラス工芸品300点、陶器200点、家具17点を出品する。出品作品は、ガラス部門では大賞を、陶器部門では金メダル、家具部門では銀メダルを受賞する。このときの活躍で、レジオン・ド・ヌール勲章四等を受章し、エミール・ガレの名は、国際的に広まった。
この万博に出品されたガレの作品群には、日本美術からの影響が色濃く反映している。そのひとつは、ガラス、陶器に表れたモチーフである。ガレは、高島に教えられた菊の素晴らしさを、作品の中に堂々と取り入れた。今まで葬式の花でしかなかった菊を、彼は水差しや花瓶の中に大胆に取り入れたのだった。そして今までイソップの童話の中ぐらいしか登場しなかった蛙やバッタ、蝶をモチーフにして人々を驚かせた。かつてフランス美術の中で、松の枝や松ぼっくりがモチーフになったことなどなかったので、人々はどんなものも芸術家の目でとらえれば立派な作品の素材になることを知ったのだった。
彼が二番目に学んだものは、日本美術の構図の奇抜さだった。ルネサンス以降、人間の目の高さが、画面の中心になってきていた。それは、西洋文化が人間中心の文化であったからである。
しかし日本美術の浮世絵や高島が“席画”で描いてみせた日本画の構図によって、俯瞰の構図を知った。俯瞰の構図でしかも中心をずらす構図を。この構図は、科学的な遠近法からガレを解放し、彼が描こうとする対象に自由に取り組んでよいことを教えたのだった。
さらに、日本美術の非対称の構図は、全く新しい構図であった。ガレは、特にこれを家具のデザインに使った。ここでも日本画の単純と省略性が重んじられた。省略性は、“空間恐怖”を“空間愛”に変えた。装飾は細心に、しかも控え目にした方が、かえって効果のあがることを彼は知った。
しかしガレは、直線的な日本の家具をそのまま真似ることはしなかった。彼は、フランス伝統にあるロココの様式とうまく溶け合せたのだった。火炎のモチーフや先細りの脚、C型のモチーフは、ロココ、ネオロココの様式である。ガレは、いつもフランス伝統の中にジャポニスムをどう取り入れるかを考えていた。
ガレが高島から得た最大の収穫は、自然をみる目への確信である。もともと植物好きで、自然を系統だてて観察する目をもっていたガレは、日本の植物学者で、日本美術の伝統をもつ画家、高島に出会うことによって、自分の自然観が正しいことを確信する。西洋美術では花瓶に活けられた花を描くことはあっても、地面に咲いている花をモチーフにすることは少ない。しかし日本美術には、自然に茂っている植物をありのまま図柄にすることがおこなわれていた。園芸家であるガレは、我が意を得たおもいで、日本美術をみたのだった。
1889年のパリ万博の成功は、ガレをさらに躍進させる原動力となる。1889年万博から次の1900年のパリ万博までの11年間は、ガレ工房が最も隆盛をきわめた時期である。
300人の職人をかかえたガレ工房の全盛期
高島がいた頃には、100人たらずの職人たちも1900年の最盛期には300人にふくれあがる。ガレは、職人のふえた工房を運営するため、Gall’eの名で大量の工房作品を世に送り出す。
しかし、パトロンであるパリの社交界の花形モンテスキュー伯爵からの依頼や、マルセル・プルーストなどのお得意様の依頼には、自らデザインをほどこした。
ガレの作品には4つのタイプがある。ひとつは、1889年以前の透明なガラス地にエナメル装飾をほどこしたものである。
次のタイプは、1889年か90年代の金属とガラスを合体させたもの。ガラスの花瓶に金属の台座をつけたものや、ガラスのジョッキに金属の把手をつけたもので、このガラスと金属を合わせるのは、ナンシー派の大きな特徴である。
第三は、89年から90年の不透明なガラス地に、花や虫などの繊細なデザインをほどこした作品群で、その形態、装飾、色彩は多岐にわたっている。
最後のタイプは、1899年以後の実験的作品である。ガラスで作られた「手」や「ひとよたけのランプ」などがこれにあたる。
これらの4つのタイプとは別に、工房で商品として売れ筋の作品が大量に作られた。
89年の万博で、ジャポニスムの作品によってナンシーのガレの名をとどろかせた彼は1900年のパリ万博で、いよいよガレの集大成ともいえる作品をおくりだす。
1900年のパリ万博に、ガレは69点の家具と73点のガラス器を出展し、ガラス、家具とも大賞をとり、このときの活躍でレジオン・ド・ヌール勲章三等を受章する。工房で働くルイ・エストーもガラス部門で金賞と銀賞を獲る。
ガレは、ガラスという素材の中に多くの可能性をみいだしていた。すでにガレの作る作品は「ものいう花瓶」と評されていた。一日の光の具合によって、窓辺においたガレの花瓶は、さまざまな色を織りなし、それは饒舌に見る者に語りかけてくる文学性をもっていた。ガレの装飾過多ともいえる文学性こそが、ドームと異なる点である。それは彼の著書の文体にもあらわれている。
1900年のパリ万博の成功は、ガレだけの名誉ではなかった。ガレの成功は、フランスのガラス史における輝かしいモニュメントだった。
それまでフランスのガラスは、チェコやベネチュアに比べて一段下にあった。ガレの成功、次に生まれるアール・デコのラリックの出現は、フランスのガラスを世界に知らしめることになる。そしてエミール・ガレは、“アール・ヌーヴォー”の旗手となった。
“アール・ヌーヴォー”は1895年12月25日に、サミエル・ビングが出した美術店の名前である。ビングは、ベルギーの画家、バン・デ・ベルデに自分の家の4室を植物の蔓をおもわせる装飾をほどこし、店にはガレやラリックの作品をはじめ、ルイス・C・ティファニーの一連のステンド・グラスやブラッドレーのポスター、イギリス人では、ビアズリー、ブラングウィン、マッキントッシュ、そしてフランス人ではボナール、ピサロ、スーラー、シニャック、ロートレックなどの作品を並べた。
ヨーロッパを席巻したアール・ヌーヴォー
当時の美術評論家、アルセーヌ・アレクサンドルは「フィガロ」紙上で
「どこもかしこも、いやらしいイギリス人か、モルヒネ中毒のユダヤ女か、えげつないベルギー人か、あるいはこれらすべてを寄せ集めた匂いでむんむんしている」
と酷評する。
しかしビングの「アール・ヌーヴォー」の店は評判となり、1900年の万博には、アール・ヌーヴォウの花がいっせいに開花する。ビングは、万博会場に「アール・ヌーヴォー・ビング」館まで出す。
アール・ヌーヴォーは世紀末の流行となり、建物や室内装飾、家具、アクセサリー、書物の装丁にまで及ぶ。アール・ヌーヴォーの装飾的特徴は、先端が鞭のようにしなって力強い動感を示す左右非対称の波打つ線である。
「線のずるずる延びたるグリグリ式と我等は唱え居候・・・・少々厭味は有之候得共、何しろ新式を以って人を驚かし当世に歓迎された居申候」
「線はずるずる延びたるグルグル式」といわれたアール・ヌーヴォーだが、ナンシーの芸術家の多くが園芸家であったことによる。ナンシー派のガレやドーム達は、フランス人である前に自分たちが「ナンシー人」であることの証しとして、作品にナンシーの紋章、復十字架を作品に入れた。この復十字架は、戦後、レジスタンス運動の旗印に使われる。
こうしたアール・ヌーヴォウは、またたくうちにフランス全土にひろがる。そしてこの“新しい芸術”運動は、フランスだけでなくイギリス、ドイツ、ベルギー、オーストリアで伝染する。国によって多少の違いがあり、名称も異なる。
ドイツでは「ユーゲントシュテール」の名で、オーストリアでは「分離派様式(ゼソエッション)」の名で呼ばれた。イギリスでは「グラスゴー派」と呼ばれ建築家、家具デザイナーたちが活躍した。アール・ヌーヴォーが発端となった「アーツ・アンド・クラッツ運動」は、フランスのアール・ヌーヴォウとは違ったもっと力強く簡潔な作品を生み出していく。スペインでは、ガウディが建築の分野で新しい試みに挑戦していた。
アール・ヌーヴォーのもともとの精神は、理性に代わる感性文化の肯定であった。
しかし感性という美だけを重視した芸術は、すぐに行きつくところまでたどり着き、先細りしていく。
1904年にはすでに下降線をたどり始める。ビングとその息子マルセルは破産した。ビングが再び商売を始めた時は、もっと手堅い分野である東洋の美術品をあつかった。
ガレの死で求心力を失ったガレ工房
アール・ヌーヴォー衰退は、くしくもナンシーのガレの死と重なる。
1900年の万博であれほど輝かし業績をおさめ、1901年にはナンシー派協会(芸術産業地方同盟)を設立し、その会長となったガレだが、1904年、白血病で倒れ、9月23日、58歳でこの世を去る。栄光のパリ万博からわずか4年後であった。
ガレの死後、妻のアンリエットが工場の経営を継ぎ、ヴィクトル・プルーヴェが美術部門の責任者となる。しかし大黒柱を失ったガレ工房は、アール・ヌーヴォーの衰退とともに忘れられた存在となる。そして1914年の第一次世界大戦で工場は閉鎖される。大戦後、工場は娘婿ペルドリーゼの手で再開されるが、長くは続かなかった。現在、ガレンヌ通りの工房跡には、労働者階級のアパルトマンがたっている。
ガレと対抗していたドーム工房は、戦争で一時閉鎖されたこともあったが、時代をみる目と着実な経営で、時代が要求する作品を作り出し、現在も健在である。
しかしドーム工房の大衆の購買層だけを狙った作品は、ガレが自らデザインした作品に比べると、芸術性においての価値では、大きな差がついている。技術的にもガレほどの複雑さや洗練味に欠ける。
ガレが活躍したアール・ヌーヴォーは、急速に発展したものは、急激に滅びるの法則通り間もなくアール・デコにとってかわられ、やがて歴史の中に埋没してしまう。長い間、アール・ヌーヴォーは、世紀末のあだ花として美術史では低い評価しか受けてこなかったが、1世紀を経た現在、再び美術史の中で、20世紀に通じる道を切り開いたものとしてみなおされてきている。
地球は回り、文化もめぐる。パリとナンシーを中心におこったアール・ヌーヴォーは、フランスで忘れられた頃、日本に上陸する。
アール・ヌーヴォーのポスターや挿絵は大正初期、竹久夢二や杉浦非水、橋口五葉、北野恒富の美人画の中にいかされる。流動曲線を取り入れた夢二の作品、ミッシャのポスターを髣髴させる橋口五葉の「髪梳る女」など、アール・ヌーヴォーは1910年代後半から20年代にかけてあらわれる。が、日本のアール・ヌーヴォーは既存の造形美術の世界に影響を与えるまでには至らなかった。高島がアール・ヌーヴーの芸術家たちに関わっていたことなど全く知られることはなかった。
歴史と言う偉大な小説家は、時にはおもしろい物語をつくってくれる。エミール・ガレと高島得三の出会いがそれである。
ガレと高島がであったのは、ジャポニスムという時代の中の3年間である。ガレが高島に出会った1885年は、ガレがひとつの山を越えて1889年のパリ万博という次の目標に向かって大きくはばたこうとしていたときである。ガレは、ジャポニスムの生きた手引きとして高島の“席画”から貪欲に吸収していった。そして自らの作品の中に取り入れ、アール・ヌーヴォーという大輪の花を咲かせた。次の1900年のパリ万博では、ジャポニスムを完全に租借し、ガレはガレになっていった。
一方、高島はガレやナンシー派の芸術家との交流によって、日本人である自分を発見する。高島は、日本人である自分に迷いをもたず、帰国後、真っ直ぐ日本画の道を進んだ。
二人はジャポニスムという時代の舞台で、全く別々の踊りを踊った役者だった。ガレは高島から自分に必要な芸だけを盗み、自分流にアレンジした。高島は、相手の踊りをみて、自分の踊りを見直す手がかりをつかむ。
ジャポニスムという一時代を画した流れの中で、歴史は実に軽やかに、朗らかに二人の人間を結びつけ、異文化に触れる衝撃と楽しさ、滋養の深さを見せてくれる。異文化との出会いとは、外国人からうける知的な刺激のことである。異文化の中に、人はいくつかの共通点を見出し、共感しあう。ガレと高島の出会いは、そうした異文化の幸せな出会いの典型であった。