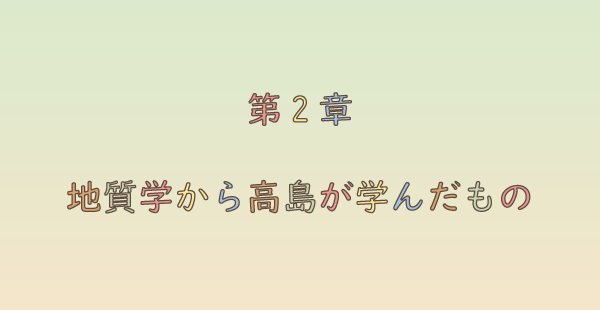生野銀山時代の高島(のちの北海)
山の魅力と地質学が絵画に目覚めさせた
生野銀山は、姫路から山つたいに50キロ入った夏でも涼しい中国山地にある。石見銀山と並び称される江戸時代からの銀山である。
山峡の村には、白い二棟の洋館風の家が目をひく。窓には、白いよろい戸があり、バルコニーのある木造洋館には、1号館、2号館と番号がつけられ、峠から見ると西洋館は緑の葉に止まったモンシロチヨウのように美しい。それが、フランスからきている二人の技師の住居だった。1号館が、生野銀山の所長であるフランソワ・コワニエ夫妻の住居。2号館が地質学者ムーセ夫妻の館だった。
村を貫く川のほとりに5,60坪ずつの長屋風の3号館、4号館、5号館があり、ここにはフランスから来ている工夫や鋳物溶鉄師、機械工が住んでいた。彼らは全員が独身で、家族と赴任しているのは所長のコワニエとムーセだけだったが、フランス人は総勢14人、溶鉱所が3棟あり、溶鉱所から白い煙が力強くたちのぼり、そこは明治政府が誇る西洋の最先端の工場だった。
明治5年8月8日、うだるような暑さのなか馬車に揺られてきた高島は、その光景に汗がさっと引いた。緑の風がここちよい。これから始まる出来事に胸が高まると同時に気持ちが引き締まった。
高島は、赴任の前からコワニエの評判はきいていた。明治元年にコワニエが生野に赴任し、銀山の収益を1590円に伸ばし、明治3年にはその46倍の7万3千140円と飛躍的にのばしていた。
仏人技師コワニエの力で銀山の利益が152倍に増える
生野銀山は江戸時代初期が最盛期で、江戸末期には銀を大量に含む「灰吹銀(はいふくぎん)」の算出は減少していた。最盛期には、820貫産出た銀は、安政の頃には214貫しかとれなくなっていた。
コワニエは、銀の埋蔵量の「灰吹銀」の産出に限界があっても、大量の鉱石を発掘することによって、すず、銅、鉛などの副産物がとれることに着眼した。銀鉱石には銀の他にすずや銅、少量の金などが含まれているが、従来の生野銀山では精製の方法をしらなかったため、銀だけを採掘して捨てていたのだった。コワニエの知識と技術は、大きな効果を生んだわけだった。
「コワニエ様がこられたとき、村の者は皆、土下座をしてお迎えしたものだよ。赤い髭をはやしておられて、初めてみたときは、そりゃこわかったです。今は慣れましたけど」
高島を迎えた鉱山寮の賄いの老婆は、そういって目を輝かした。夫と長男を坑内の事故で失い、鉱山寮で働かせてもらっているのだといった。生野は年寄りと後家の村と呼ばれていた。坑内事故で毎年、男たちが何人も死んでいたからだ。
「コワニエという人は、どんな人ですか」
「私は直接お話したことはないさかいにわからんけど、気難しい方だと聞いています。奥様は気さくな人ですがね」
老婆はそういってから、よけいなことをお役人に言ってしまったと口を押さえた。
荷物を置くと、鉱山事務所に顔をだした。事務所は、江戸時代の生野代官所が使われており、コワニエが正門として築造した石門には、菊の御紋がはめこまれ、門だけが西洋風であたりの風景とちぐはぐだった。事務所の裏はすぐ山で、八月の緑が重たげに茂って緑の壁を作っていた。
事務所を訪ねると、奥の部屋にとうされた。赤毛の男はペンを走らせていた。老婆が言ったように「レンガ色の髭が鼻下から顎の裏に密生している。男は高島をみると、すぐにペンを置いた。「二重瞼の目は」ひどく無感動で濁っていた。38歳のコワニエだった。
「工部省からきました高島得三です」とフランス語で挨拶した。
「フランス語ができるのですね」
「東京で習いましたが、十分ではありません」
「少しでも話せれば上々です」
この時はじめてコワニエの眼に光が戻った。高島は、この男は疲れているのだと感じた。コワニエは高島と握手をすると、急に咳き込んだ。彼にはぜんそくの持病があった。持病は異国でも彼を苦しめていた。
コワニエは、フランス西部のロレーヌ州の鉱山の町、サンエチエンヌに生まれ、国立サンエチエンヌ鉱山学校を卒業している。この学校はナンシーの森林学校と同格で、一般大学よりひとランク上の大学である。
コワニエは、フランス本国でも優秀な鉱山学者で、植民地だったアルジェリアの鉱山で腕をふるい、1862年にはマダガスカル島の科学探検隊に参加していた。アメリカ、カルフォルニアの金鉱脈探査にも数年間赴任し、メキシコにも行っている。彼はヨーロッパでも超一流の鉱山師であり鉱山学者だった。
コワニエが日本とかかわりをもつようになったのは、フランスの貴族モンブラン伯を介して薩摩藩の五代才助(友厚)に紹介されたのが、そもそもの始まりだった。
五代は1865年、幕府の禁を犯して松本弘安、森有礼、田中静州(盛明)ら15人とイギリスに渡り、さらにフランスにも立ち寄った。その時、モンブラン伯に会って薩摩とフランスとの貿易会社設立を提案する。五代は藩の資源開発について述べ、優秀な鉱山師を紹介してほしいと依頼、モンブラン伯が推薦したのがコワニエだった。
慶長3年9月、コワニエは妻と共に坑夫ひとりを連れ、モンブラン伯と共に日本にやってきた。しかし間もなく幕府は崩壊、明治維新を迎え、コワニエは明治政府からお雇い外国人として、年俸9千円で迎えられる。それは、横須賀造船長フランソワ・ヴェルニーニの洋銀1万枚につぐ高級であった。現在の金額では3億円以上である。しかし明治政府は高い買い物はしていない。
コワニエは生野銀山に赴任するや、くまなく銀山を調査し、生野を模範鉱山にしようと考える。彼は、精製のために蒸気力の導入よりも水力の利用を考え、鉱山動力として水車を設備し、精製の動力源を得る。そして赴任3年目にして今までの46倍の収益をあげ、帰国するまで年々収益を伸ばし続け、明治10年の帰国時には152倍の収益、24万1千902円まで伸ばす。コワニエは収益をのばすかたわら生野鉱山学校を創設し、実地に教えながら鉱山師を育成した。高島が赴任した明治5年に、この学校は経費不足などから15人の卒業生を出して閉校となったが、生徒たちは鉱山資源の開発に貢献する。高島は、閉校になった直後に生野に赴任したのだった。
コワニエやムーセ、フードア等は、フランス語をかじってきた高島を重宝した。彼らは、実際の仕事を通じて、高島にも鉱山学、地質学を教えた。幼い頃から植物を模写し、自然観察の眼を養っていた高島はのみこみも早かった。彼らにも、教えがいがあるというものだった。
一流技師から調査の手ほどきを受ける
コワニエが北陸や東北の鉱山調査にでかけるとき、高島は通訳として一行に加わって、実地に地形や地質調査の方法、岩石鉱物の鑑定を習得していった。堆積岩や火成岩、変成岩の違い、山の斜面から湧き出ている水が酸性水かどうかをしっかり見極めないと、隧道(トンネル)を掘るとき事故につながることを教えた。酸性水は岩石に含まれる黄鉄鉱が酸化したもので、岩石の地盤がゆるんでいることの表れであるからだ。高島にとって、コワニエやムーセが地表をみて説明する言葉は一語一語新鮮だった。実際に地層構造を前にして言ってもらうと、質問もしやすい。師匠も熱心な生徒たちにていねいに教えた。高島は優秀な弟子になった。調査に同行するたびに知識が増えた。日本には背骨のように山脈が連なっていること、日本列島を二分する大地溝帯があると師匠はいった。フォッサマグナのことだが、高島には何度聞いても分らなかった。彼らはラテン語で「大きな裂け目」というばかりだった。しかしこの鉱山調査が高島のものの見方、考え方をつくり、彼の絵画の基礎となった。
「余(高島)生来地学の癖なる未経の地を過る毎に必ず山川起伏の源を極む」
(山陽山陰地質記事)
自分の癖で山水画を描くとき、必ずそこの地形がどんなであるかを見極めるという。それはレオナルド・ダヴィンチが人体解剖を見て、人の筋肉を研究したのと似ている。高島は鉱山調査に随行したことで、地質学を含めた山岳そのものに惹かれた。山にはその山がもつ様ざまな歴史があり、どの山も人間の顔がひとりひとり異なるように違った形体をもっていた。天候や季節によって山の表情は万華鏡のように変った。それをみつけるのは楽しいことだった。山の美しさ、不思議さ、偉大さ、不気味さは高島の心にしみた。
しかし高島は、この随行で自分の一生のテーマである「山岳」に出会っていることにまだ気付いていない。彼は、フランス人の地質学の知識を吸収するだけでせいいっぱいだった。毎日の生活は、はちきれんばかりに充実していた。
コワニエ夫妻に可愛がられた高島
彼のフランス語も上達した。
明治6年から生野から飾磨津までの12里15丁を貫通させる「生野銀山道」の工事がレオン・シスロイを技長にして始まった。高島は通訳として活躍する。「生野銀山史」に高島得三の名前が唯一登場するのは、この工事の通訳としてである。
工事は明治9年に完成するが、その前年に高島は鉱山寮にいったん依頼退職を出し、生野で学んだ技術と理論を実践にうつす国内旅行を計画する。高島は「山陽山陰地質記事」を完成させ、さらに大々的に日本全国の地質と森林調査をしたいと思うようになっていた。
生野を発つとき、コワニエの妻、マリーはふっくらとした丸顔に微笑をうかべ、両手で高島の手をとった。
「高島さん、フランスに来なさい。生野で学んだ小さなフランスを、本当のフランスに来て自分の眼で確かめてください。日本語にもあるでしょう、百聞は一見にしかずってね」
マリー夫人の実家はリヨンの名家だった。彼女にはムーセ夫人にはない優雅さがあった。美人ではなかったが、人をくつろがせるあたたかい雰囲気があった。
「リヨンの私の実家にも来てくださいね。リヨンは二つの川が流れていて、赤レンガの家が建つ、そりゃ美しい町ですよ。織物の町だから女性たちもとってもおしゃれなのよ」
マリー夫人は遠くに視線を泳がせ、夢を追う少女の眼になった。
コワニエ夫妻は高島が生野を去った2年後に、コワニエのぜんそくが悪化したこともあってフランスに帰国した。高島にとってコワニエと出会ったことが、フランス留学を決定づけた。自分の方向性をみつけたのだ。生野銀山のフランス人に可愛がられてことも、彼の自信につながった。コワニエ夫妻は高島にとって終生の師となった。
山岳調査を一緒にした田中壌(のちに画家)との絆
生野銀山を出た高島は、官有林の調査のため、「草履を脱ぐ間もなく全国の山林を歩き回っていた」その頃、兄の張輔は、萩中学の教師をやめ、宮内庁につとめていた。張輔はただひとりの肉親に早く所帯をもたせたいと思っていたが、弟に連絡がつかなかった。それほど高島は、この時期多忙をきわめていた。
高島は工部省から山林局に移り、部下の田中壌(1857~1903)と一緒に森林調査に励んでいた。田中は日本洋画の先駆者、高橋由一と同じ倶楽部に所属し、後に彼も画家になる。山林局時代、植物帯調査報告には挿絵を描きこむことが多かったが、田中の画才もいかされた。ふたりの挿絵は、よく似ていてどちらがえがいたのか区別がつかないほどである。
高島は、自分と同じ絵心を持った田中と気持ちのうえでも意気投合していた。調査は楽しかった。コワニエやムーセに教えられた地表にあらわれた断層から地質をよみとり、植物帯とどう関連しているか記録した。ふたりは土地の木こりに案内され、山から山へと歩きまわった。
一度山中で雨にあい、それがもとで田中が風邪をひき、高熱をだした。すでに日が暮れていた。早く医者にみせないといけない、高島は田中を背負って山をおりた。このことが一層ふたりの絆を強くした。相模国官林調査報文、上野国林調査報告文、三州北設楽郡
殖林意見概略など、高島は次々と報告書を提出した。明治12年から明治17年の6年間に全国20余県の山林調査書を出すほどの勤勉ぶりである。
当時、日本の森林は宮内庁、天皇家のものと昔からのその土地の地元所有林に分かれていた。明治政府はなるだけ宮内庁の所有林にしたかったので、森林調査、特に正確な地図は重要だった。しかし森林の境界線は昔からの言い伝えによって線引きされていたので、あいまいな部分がおおかった。そのため長野県では、地元と政府の食い違いから明治9年には「木曽御料事件」がおきている。そのことを高島はしっているので、正確さに徹した。正確に調査する、この姿勢は高島の性分にあっていた。高島は森林調査がおもしろくてしかたがない。彼は気の会う田中と一緒に調査に励んだ。ワラジの底から伝わってくる感触で玄武岩の地表なのか花崗岩なのかを言い当てられるほど岩石の知識は確かなものになっていた。
この調査書には、官有林の実態の報告だけでなく、植物帯区分によって適地適樹種による植林をおこなうための資料、意見が添えられていた。日本の山林歴史の中の画期的な調査であり、他に類をみない優れた報告書であった。この報告書は、イギリスのクレメンツによってとかれた植生連続(plante succession)の理論と同じものであるが、クレメンツより高島らの報告書の方が15年も先に発表していたことになる。
日本全国の森林を歩き、官林報告書を作成しながら、高島の気持ちのなかには絵画への野心も芽生えていた。いくつもの山を縦走するたびに彼の絵画への情熱はふくらんでいった。高島は、山林調査で自分が得た感覚や知識を山岳絵画の中にいかせられないかと考えていた。彼は山川の風景を写生帳に納めることを怠らなかった。『自分の専門知識から火山岩の山はどう、花崗岩の山はどうというふうに、一見してその特殊な差別が明瞭に分るようになってくると同時に、画家としての山岳もしくは自然に対する考えも段々と深くなって』いった。高島には、日本の画家が誰もなしえなかったことを今、自分が実行しているという自負があった。
山岳図を絵画展に応募するが落選
明治15年(1882年)10月、第一回内国絵画共進会が開催されたが、高島は忙しい仕事の合間をぬって、写生帖からおこして「山水」と「蓮」を出品した。「山水」には自信があった。しかし高島は落選した。無名の彼の作品は、審査員の目にとまらなかった。彼は自分の力量を反省するより、入選しなかったのはどの画派にも所属していないからだと考えた。それほど彼は自分の描いた山に自信があった。長州藩の画家で自分の力になってくれる人はいないかと考えた。すぐに防長出身の狩野芳崖が浮かんだ。今回、芳崖も出品していた。力作だったが、賞はとっていなかった。芳崖の落選が、高島に自信を与えた。維新の志士たちの長州は政治家を多く排出していたが、芸術家はいなかった。高島の頭に同郷の大庭学遷(1820~1899)の作品が浮かんだ。
ひとり娘の美津子に一目ぼれする35歳の高島
学遷は早くから徳山藩の御絵師について絵を習い、京都では小田海遷の門に入って修行していた。南北両派を合わせた画風で山水、花鳥を描き、名前を売っていた。明治維新後は東京に住んでいたが、学遷ならつてはあった。
高島は学遷を訪ねた。今起きたばかりだというので、玄関の間で待たされた。
「お待たせしました」
学遷は洗面が終わったばかりで髪が濡れていた。着物の前がはだけ河原のススキのように飄々としていた。売れっ子画家の脂ぎったところがないのが、高島の緊張を解いた。高島が作品を見せると、ほぉと言いながら丁寧にみてくれた。
「画室の方が落ち着きますね。場所を移しましょう」
学遷は女中に指示した。初めての者に画室をみせるのは、手の内を明かすようなものだったが、学遷は気さくでおおらかだった。長州の井上馨の紹介であることにすっかり安心していたのだ。
高島は画室に入ろうとして頭をぶつけた。天井から吊るされていた籠が揺れた。大小の籠が天井から吊るされていて、画材道具が入っていた。画材に使うのか柿の枝までぶらさげてあった。画室というより物置小屋だった。
「そこの物をすみに寄せて、あいているところに座ってください」
学遷はどこまでも気さくだった。萩の蓮正寺で学遷が奉納した絵馬をみたことをいうと
「萩の菓子を昨日もらったのですよ。お出ししましょう」
と、手をたたいて女中を呼んだ。間もなく襖があいて桃割れに結った13, 14の少女が茶菓子をもってきた。
「ひとり娘の美津子です」
学遷はこの時だけ身をそらして娘を紹介した。黒い繻子のような光沢のある髪の下に、新月のような額があった。娘の目は、水に濡れた黒曜石のようにひかり、口元は杏の蕾のような紅だった。小さな口元に似合わず気性の激しさを表す両顎の線が発達していた。よそいきのお行儀のよさのなかに、すでに他人にみつめられることの快感を知っている女のふるまいがあった。
「いらっしゃいませ」
美津子はまっすぐに顔をあげ、高島を見た。雨上がりのあやめ畑を身をひるがえして飛び去るツバメのような嫣然とした雰囲気があった。その美しさは不敵でさえあった。
高島は、自分がこんな小娘の前でひどく緊張していることが腹立たしかった。
美津子は、夏みかんを砂糖に漬け込んだ“萩乃薫”を置いてでていった。
学遷のもとから帰ってからも、彼の脳裏から美津子の姿は消えなかった。森を歩いていても、報告書を書いているときも、不意に美津子が現れるようになった。
高島は用事を作っては大庭家を訪れたが、なぜかその日以来、美津子は現れなかった。そのため、玄関に美津子の草履が揃えてあるのをみたり、美津子が弾く琴の音が聞こえてくると、胸が早鐘のようになった。すでに女の体を知っている三十をすぎた男である自分が、いくら美しいとはいえまだ十三や四の小娘に腑抜けになるのを、半ば自嘲的にみつめる目もあった。しかし自嘲や自虐が、美津子の美しさを彼の中で不動のものにしていった。
美津子に求婚するがことわられる
高島は、結婚して長男もできている兄の張輔に美津子のことを打ち明けた。張輔は人を介して学遷のもとにいかせたが、その返事は実にそっけないものだった。
「娘はまだ十五歳だから嫁にはだせません」
それは、ごく自然なことわりかただったが、高島は落胆した。口惜しかった。初めて味わう敗北、拒否の一撃だった。
チャンス到来 エジンバラ森林万博の視察とフランス留学
そんな時、高島の生活が急変する出来事がおこった。山林局長の武井守正が、イギリスのエジンバラで開催される第一回森林万博に出席することになり、通訳の大久保業と共に高島も随行することになった。
武井守正は、森林調査の高島の仕事を高く評価していたので、今回、彼を抜擢したのだった。
武井から森林万博の後、フランスに渡りフランスの森林学校に留学してはどうかという話が打診された。高島はすぐさまこのことを大庭学遷に報せた。
「四年間、ヨーロッパに行ってまいります。先生も美津子さまもお元気であらせられますように」
高島は、そこに美津子がいないのに、わざと彼女の名をつけ添えた。四年後に帰国したとき美津子は十九歳になっている。自分は三十九歳。その時まで美津子が嫁に行かないという保証はない。大庭家から帰る時、思いがけず美津子が出てきた。玄関先で
「お体に気をつけて行ってきてくださいませ」
と、決まりきった挨拶をした。学遷の大きな餞(はなむけ)だった。
「お体に気をつけて」か、高島は人力車に揺られながら、美津子の言葉を何回も反芻していた。